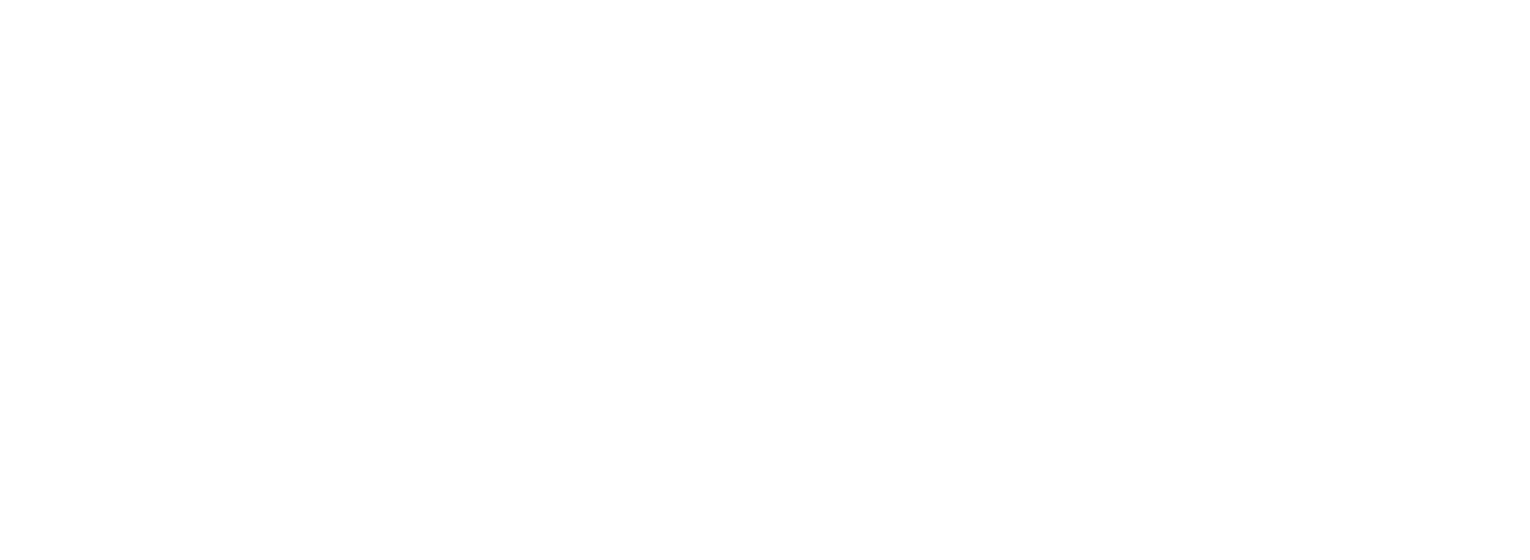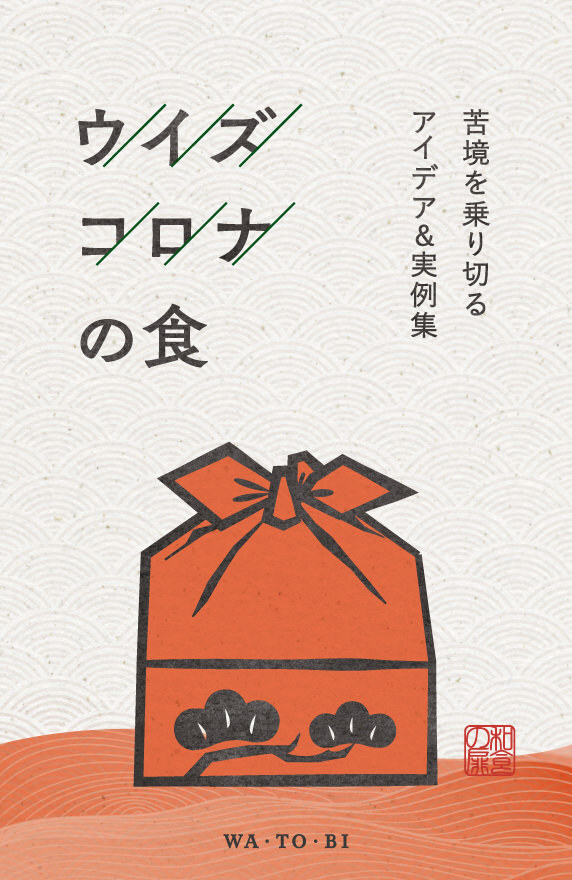“産まれた土地”で最高の酒造りを目指す
早朝の新幹線に乗り、新大牟田(おおむた)駅で下車。福岡と熊本の県境を超え、車で約15分走った和水町(なごみまち)に『花の香酒造』はある。
今回、同行いただいた『ぬま田』の店主・沼田和也さんと、沼田さんの右腕として系列店の『天星 はなれ』の店長を任される坂田勇太さんは、ともに熊本・天草の出身。全国から極上の食材を厳選する中で、自然と熊本の食材も組み込むようになったという。
「私たちのお店でも、『産土』を使わせていただいていますが、すっきりとした呑み口で、天ぷらの油をスーッと切ってくれるんです。お客様からも大変美味しいとお褒めの言葉をいただいています。その『産土』の蔵元であり、昨年11月にリリースされた『肥後御国酒 赤酒 花ノ香』のことも教えていただけるとあって、とても楽しみにして来ました」と、沼田さんたちは目を輝かせる。
一方、「昨日まで馬耕(馬と共に土を耕す作業)をしていたんですよ」と話すのは、『花の香酒造』六代目の神田清隆さん。2011年に経営難の蔵を継ぎ、2015年には日本酒の「花の香」を、2021年には「産土」をリリースするなど、国内外で注目を集める杜氏の一人だ。
「『産土』とは、日本に古くから伝わる“産まれた土地”“土地の神々”という意味の言葉。産まれた土地で、土着の環境と文化を守りながら、ここにしかない最高の酒造りを目指すというのが、『花の香酒造』の哲学です。今年から馬耕を始めたのも、この『産土』という哲学に基づいているんですよ」と、神田さん。
江戸時代の赤酒を現代に蘇らせる
そもそも、赤酒とはどのようなお酒なのか。大きな特徴の一つとして、灰持(あくもち)酒であることが挙げられる。灰持酒とは、木灰を投入して保存性を高めた日本古来のお酒で、熊本の赤酒の他にも、鹿児島の「地酒」、島根の「地伝酒」が現存する。
灰で酒の酸を中和することで、もともと酸性だった酒が中性、もしくは微アルカリ性に変わり、成分中の糖分が褐変反応やメイラード反応を起こす。酒の色が茶褐色に変化することから、赤酒と呼ばれるようになったとか。
「南九州では古くからこんにゃくや灰汁(あく)巻きなど、食品の保存性を高めるために灰を用いる文化がありましたので、お酒に関しても保存性を高めるために木灰を入れるというのは当然の流れだったのでしょう」と、神田さん。加熱(火入れ)することで殺菌し保存性を高める「火持酒」の製法が生まれる以前は、灰持酒が全国で造られていたという。
「私たちの地元・天草でも、お正月にはお屠蘇として赤酒をいただいていました。熊本県内の多くの家庭では、年末になると赤酒を常備するんですよ」と、沼田さん。
かつてフランスでワインの醸造哲学を学んだ神田さんは、テロワールという言葉と出合い、受け継いだ蔵で赤酒を復刻させることを決意する。
「土地それぞれに永く守り伝えられていた文化、その哲学と意志こそがテロワールの根幹です。日本の『産土』を考えた時、現代に蘇る江戸時代の赤酒のイメージが明確に湧いてきました」。
構想から約3年。2022年11月29日、「肥後御国酒 赤酒 花ノ香」は復刻を遂げた。
米と木灰のみで醸す極めて貴重で高貴な酒
『花の香酒造』では、6月から7月にかけて「赤酒」づくりが行なわれる。この時季は、日本酒の「花の香」や「産土」の造りが終わり、9月から始まる仕込みまでの期間だ。
伝統的な木桶を用い、江戸時代の製法に習って清酒と同じ製法で醸される赤酒。異なるのは、「五水(ごみず)」で醸されることだ。五水とは、米10石に対し、仕込み水5石を使用したもの。清酒は「十水(とみず)」で醸されたため、赤酒は米に対する水の量が約半分となり、米の濃厚な甘みと、まろやかなとろみが強い酒となる。近年、多くの赤酒が醸造用アルコールやうま味成分を添加して製造される中、『花の香酒造』では米と水、木灰のみで造られている。
「元禄時代までの酒宴は、甘く粘稠(ねんちゅう)な酒だけを少しずつ嗜むスタイルで、料理と共に楽しむものではなかったようです。細川家の庇護により品質を高めてきた赤酒は、大変貴重で高貴なお酒でした。私たちは、徹底的に味わいを追求し、その当時の赤酒を復活させたいと考えました」と、神田さんは語る。
また、味わいを追求した結果、一般的な三段仕込みに3〜5年物を加える四段仕込みを行なうことで、極めてきれいな甘さを引き出すことに成功したのだ。
料理酒としてはもちろん、デザートワインとしても活躍!
木灰を投入する様子や田んぼなどを見学し、「赤酒」を用いた料理を試食した後に訪れたのは、かつて使われていた道具や造りの工程を展示するギャラリー「花回廊」。沼田さんと坂田さんは、立派な庭を臨むテイスティングバーで試飲を行なった。
「とても美味しいですね。子どもの頃から慣れ親しんでいた赤酒とは全く違います。これは料理酒としてだけでなく、ソーテルヌのようなデザートワインの代わりにもなるし、チーズやバニラアイスと共にいただくのもいいかもしれません」と、沼田さん。
その様子を見た神田さんは嬉しそうに笑みを浮かべる。
「大自然に囲まれた蔵だからこそ、和水町と菊池川流域の自然環境や生態系を守っていかなければいけません」と、熱く語る神田さん。
土着の環境と文化を守りながら「ここにしかない最高の酒造りを目指す」神田さんたちにとって、赤酒の復刻は、まだ序章に過ぎないのかもしれない。






【住所】熊本県玉名郡和水町西吉地 2226-2
【公式HP】https://www.hananoka.co.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/hananokashuzo/
【Facebook】https://www.facebook.com/profile.php?id=100057197150643
フォローして最新情報をチェック!
会員限定記事が
読み放題
月額990円(税込)初回30日間無料。
※決済情報のご登録が必要です
この連載の他の記事産地ルポ これからの和食材
月額990円(税込)初回30日間無料。
※決済情報のご登録が必要です