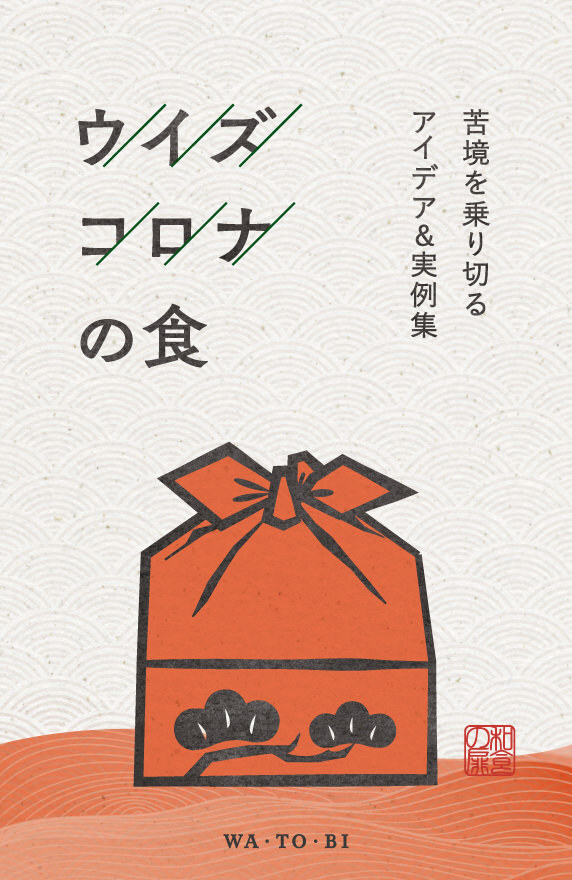【レシピ付き】東京・銀座『金田中 庵』其の三:冬瓜のっぺい
大正15年に創業した料亭『新ばし金田中』の食い切り料理を銀座で受け継ぐ割烹『金田中 庵(あん)』。夜の品書きには数十種類の旬の一品が並びますが、その中に料亭の料理をアレンジしたものが潜んでいて、古くからの常連を喜ばせます。料亭の夏の名物は「冬瓜のっぺい」。大ぶりの冬瓜をくり抜き、冬瓜と共にエビや石川子芋、合鴨などを盛って、のっぺい汁を張った華のある料理です。座敷で取り分ける演出も魅力の一品を、渡邉 厚料理長は割烹版として仕立て直したのです。
柏原光太郎(かしわばらこうたろう):1963年東京生まれ。慶應義塾大学を卒業後、株式会社文藝春秋に入社。『東京いい店うまい店』編集長、食のEC『文春マルシェ』立ち上げの後、独立。食の社交倶楽部「日本ガストロノミー協会」を設立し、会長に。食べログフォロワー5万人以上。外食産業、地方創生関係者との繋がりも深い。著書に『ニッポン美食立国論』(日刊現代)。
料亭『新ばし金田中』の夏の名物
「冬瓜のっぺい」が『新ばし金田中』の名物になったのは四半世紀以上前。渡邉 厚料理長が入社した25年前にはすでにあり、先代当主の岡副鐡雄(おかぞえ てつお)さんが考案した仕事と言われている。
カウンター割烹と違い、料亭では調理の様を見せることができないため、調理場で仕上げた料理を仲居が運び、座敷で取り分けるのが、もてなしの華になる。冬ならば鍋がその役割を果たすが、夏にはそうした名物がなかった。そこで考案されたのが「冬瓜のっぺい」である。
この日用意されたのは3㎏超の冬瓜。濃緑の表皮をセルクルで薄く削り、萌黄色のきれいな色を見せるところから料理は始まる。そして、蓋と釜に切り分けた冬瓜をくり抜くのだが、その実を具として使うのではない。
どうしてもきれいにくり抜けないため、これはまかない用とし、お客にはわざわざもう一つ冬瓜を用意し、その実を使う。また、熱いまま提供できるよう、食材を盛る前に熱湯を何度も注ぎ入れ、冬瓜の釜を温めておく。そんな手間暇をかけていることはお客には言わないが、分かる人には分かる。それが、『新ばし金田中』のおもてなしの矜持である。
汁をたっぷりと張った冬瓜のっぺいは、4㎏近い重さになる。これを、北大路魯山人(きたおおじ ろさんじん)作の鍋敷きに載せて座敷まで運び、目の前で取り分けるのだ。
鍋敷きを合わせると7㎏もあるという料理をおごそかに運ぶのは、仲居にとっては大変だが、お客から見れば座敷だからこそ味わえる眼福。紐を付けた冬瓜の蓋が開けられた瞬間の、お客の驚きと喜び。料理人や仲居の苦労を吹き消すような、華やかな演出である。
 大きな冬瓜の皮を、小さなセルクルを使ってカリカリと薄く削る。表皮の下に薄皮があり、その下まで削ると、中からキレイな萌黄色が見えてくる。
大きな冬瓜の皮を、小さなセルクルを使ってカリカリと薄く削る。表皮の下に薄皮があり、その下まで削ると、中からキレイな萌黄色が見えてくる。
小冬瓜を釜にした、割烹的アレンジ版
『新ばし金田中』の「冬瓜のっぺい」を、カウンター割烹でどう再現するか。渡邉料理長は小冬瓜を使って一人前ずつ供することとした。半割にすることで、冬瓜一つが2人分となる。中に入れる冬瓜の実は、大きな冬瓜を別に用意するのだと言う。
『金田中 庵』の品書きにこのメニューが載るのは、毎年7月の半ば頃から。
「石川子芋が美味しくなって初めて出せる料理なので。米のとぎ汁で茹でると、弾けるように少し割れ目が入るくらい、力のある子芋が出てくるまで待ちます。いい子芋は真白に茹で上がる。それが美味しい証拠です」(渡邉料理長)。
中に入れる食材は料亭と同じで、石川子芋の他には冬瓜、車エビ、合鴨、どんこ椎茸、オクラ。小冬瓜釜の萌黄色の表面と白い断面、車エビの赤、椎茸の黒、オクラの緑が鮮やかなコントラストを見せて美しい。

車エビは生きたまま背ワタをとって茹で上げ、鮮やかな赤に発色させる。干し椎茸は戻して含め煮、オクラは八方地浸しにする。一つ一つの食材に適した下準備をするのは、料亭と同じだ。
合鴨だけは注文が入ってから葛を打ち、軽く茹でて、他の具材と共に八方地でさっと煮て冬瓜の釜へ。その煮汁にとろみを付けて注いでから、割烹ならではのひと工夫を。蒸し器で釜ごと蒸して、熱々をお出しすると言う。
目の前で仕立てられていく臨場感は、カウンター割烹ならでは。これが、『金田中 庵』流の「冬瓜のっぺい」の世界である。
のっぺい汁は“しんみりめ”に仕立てる
「のっぺい」とは、野菜を煮て、その煮汁にとろみを付けた料理のこと。
『金田中』では、八方地がベースとなる。八方地は、カツオ昆布だしに淡口醤油・みりんが基本。のっぺい汁にする場合は、さらに淡口醤油とみりんを加え、濃いめに調味する。
その汁の塩梅を、渡邉料理長は「しんみりめに味を付ける」と表現する。
「“金田中用語”かもしれませんが、しっかりとした味にするということです。うちは、一番だしもカツオ節を贅沢に使って、しっかりと引くことが特徴ですからね」。
“しんみりめ”に味付けされた八方地に葛が入ることで、さらに味わいの濃度は増すが、猛暑の中で食べるにはこれくらいの加減が有難い。それでいて、各々の食材の味が際立つのは、いい食材に的確な仕事が施され、持ち味が十二分に引き出されているからだろう。しかも、全体で調和も取れている。
夏の名物と聞いて、私は当初、冷製仕立てなのかと思ったが、料理をいただいて不明を恥じた。冷製であれば一時の清涼感は味わえるかもしれないが、食材それぞれの味を生かすには温度が低すぎる。全体的に調和せず、ばらばらな印象になってしまうのではないか、と思う。
「冬瓜のっぺい」は、味の付け方、温度帯、供し方、いずれも長い年月をかけて『金田中』が作り上げた“食の総合芸術”なのである。そして渡邉料理長が『金田中 庵』で今、カウンター割烹の料理に昇華させている。

月額990円(税込)で限定記事が読み放題。
今なら初回30日間無料。
フォローして最新情報をチェック!
会員限定記事が
読み放題
月額990円(税込)初回30日間無料。
※決済情報のご登録が必要です
この連載の他の記事老舗の名物ものがたり
月額990円(税込)初回30日間無料。
※決済情報のご登録が必要です