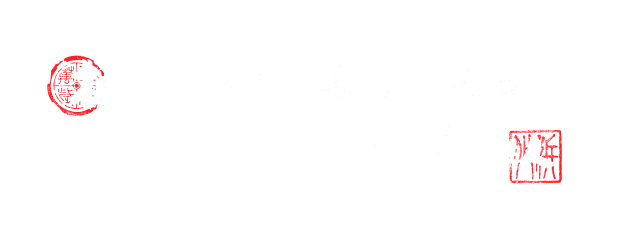【料理編】焼き物vol.2 サワラの幽庵焼
京都『浜作』のサワラの幽庵焼は、ひと口目から印象的です。表面はパリッとキャラメリゼされて香ばしく、続いてサワラの凝縮した旨みが口いっぱいに広がります。主人・森川裕之さんは「これは、サワラをおいしく食べるための幽庵焼です」と語ります。切り方、漬け方、焼き方すべてに森川さん独自の考えが息づき、どの工程をとっても理に適っており、思わず膝を打つことばかり。料理人人生40年をかけて築き上げた哲学を紐解きます。
森川裕之さん:京都『浜作』三代目主人。1962年、京都・祇園町生まれ。初代・森川 栄が創業した日本初の板前割烹を1991年に継ぎ、一期一会の精神で日々板場に立つ。お客には川端康成や谷崎潤一郎といった文豪、英国のチャールズ皇太子やチャールズ・チャップリンなど、三代にわたって国内外の貴紳に愛されてきた。通常営業のほか、受講生が延べ4万人を超える「浜作料理教室」も主催。「現代の名工(平成29年度 厚生労働省 卓越技能者)」として表彰される。NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」などのテレビ出演多数、著書も「愛蔵版 和食の教科書 ぎをん献立帖」(世界文化社)など、多数執筆している。
身厚なサワラを味わう、幽庵焼
幽庵焼や味噌漬け焼きなど、魚を地に漬けてから焼き上げる料理や、タレをかけながら焼くかけ焼きがあります。召し上がって「よぉ漬かってる」とか「〇〇の味が利いてる」などお客さまがおっしゃるシーンを見かけることがありますが、私からしたら漬け地やタレの味が前面に出てたらアカンのです。
何を食べるのかというと、魚でしょう。魚そのものの味を引き立て、「おいしい」と感じていただかないといけないんです。ですから、地に漬ける時間やタレをかける回数は最低限にとどめ、口に含んだ時に漬け地やタレの風味によって魚の味が際立つ。そんな味わいを目指さねばなりません。
そのためには、いい魚を使わねばならないのは当然のこと。今回使うサワラは瀬戸内海のものですが、身厚で、サワラの味がしっかりしています。
下の写真は、左が塩を振って2時間置いたもの、真ん中が塩をした後3時間ほど地に漬けた幽庵漬け、右が塩をした後、味噌床に18時間漬けたものです。店によってはもっと長時間漬けるところもありますが、うちではこれくらいの時間漬けた後、焼いていきます。
 味噌床は、白味噌(精製前の粒状のもの)500g、酒70ml、みりん50mlを合わせたもの。東京では白味噌のことを西の京、すなわち西京味噌というので「西京漬け」と呼ぶが、京都では「味噌漬け」と呼んでいる。
味噌床は、白味噌(精製前の粒状のもの)500g、酒70ml、みりん50mlを合わせたもの。東京では白味噌のことを西の京、すなわち西京味噌というので「西京漬け」と呼ぶが、京都では「味噌漬け」と呼んでいる。
続きを読むには
無料で30日間お試し※
- 会員限定記事1,000本以上、動画50本以上が見放題
- ブックマーク・コメント機能が使える
- 確かな知識と経験を持つ布陣が指南役
- 調理科学、食材、器など専門性の高い分野もカバー
決済情報のご登録が必要です。初回ご登録の方に限ります。無料期間後は¥990(税込)/月。いつでもキャンセルできます。
フォローして最新情報をチェック!