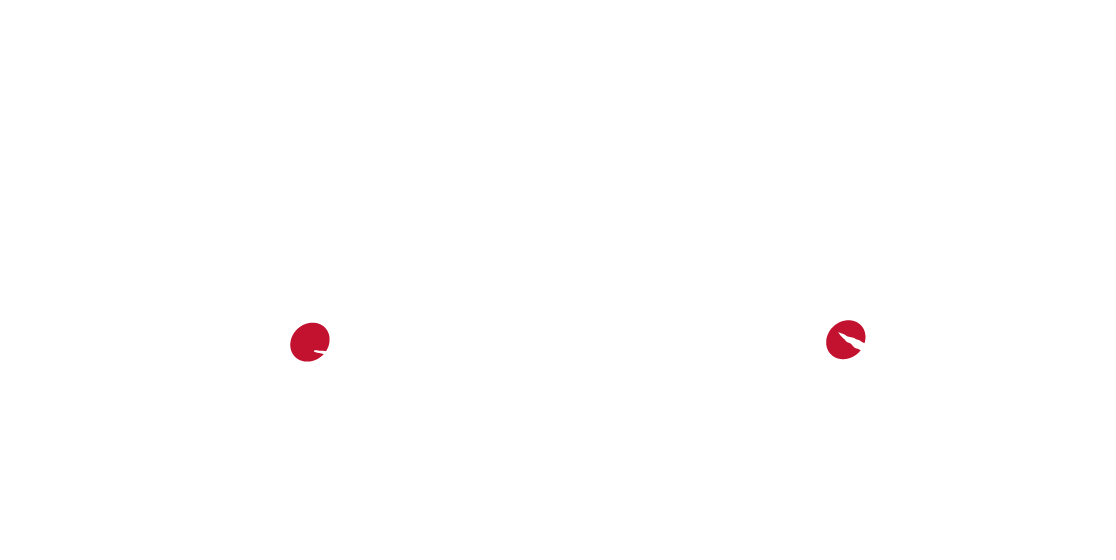大阪『伏見町 栫山』栫山一希さんに聞く【5問5答】
江戸時代から商人の町として発展してきた大阪・船場に店を構える『伏見町 栫山(かこいやま)』の栫山一希さん。土地に所縁のある料理や文化を取り入れた献立は、お客をその世界観に引き込む力があります。今回の5問5答では、主に献立の立て方や器の選び方についてお聞きしました。唯一無二の料理を生み出そうとする、栫山さんの思いが見てとれます。
献立はどのようにして組み立てますか。
月末か月初の休日に「器遊び」をしながら考えます。この時間が本当に楽しくて、一日中飽きずにやっています。
「器遊び」とは、コースの始めから終わりまで料理と器の組合せを決めること。10月の献立では重陽の節句の菊のモチーフや十五夜の月など歳時を取り入れ、季節が移ろうように構成。材質も前半にガラスや染付を組み込んで涼やかに、焼き物を入れつつ、終盤では温かみのある赤絵の器を使いました。
10月は、このような流れ。右下から左へとご覧ください。

右下のガラスが前菜の器です。アール・デコで、パッと見た感じは普通のボウル型なんですが、淵に装飾が施され、上から見たら菊のようでしょう。これに鱧やアワビ、菊菜、猿梨の実、石榴(ザクロ)、胡桃(クルミ)を「重ね重ね」盛る。重陽の節句にかけています。
二皿目は樂家十二代弘入(こうにゅう)造の菊梅の向付。懐紙を被せ、菊の着せ綿をのせて提供します。料理は鮎の茶焚きです。三皿目はご紹介した「奉書包み 松の葉蒸し」で、その次の染付と長皿にはお造り、北大路魯山人造の木の葉皿は取り皿です。下の現代作家さんの器では焼き栗を提供し、椀は萩の蒔絵。ワタリガニの蕪蒸しと松茸を盛りました。
一番大きな器は、月見に見立てた八寸。ここが10月の献立の山場ですね。八寸は必ず取り分けスタイルで、季節の景色を楽しんでいただきます。その下の絵付けの器には鮎の頭と尾をカリカリに揚げて鮎うるかを塗り、薬草をたっぷりのせた料理を。三日月の器は豆腐とにえばな、卵黄を盛ってこちらも月見の見立て。満月から月が欠けた、という趣です。赤絵の鉢にはスッポン料理で、最後に香の物と食事です。
骨董はもちろん好きなんですが、そればかりだと「枯れ」すぎるので、ところどころ現代作家さんの器を差し込みます。ちなみに、お造りの長皿はフランス人作家さんのもの。
主となる器だけでなく、合わせる小付けや取り箸、あしらいなど、付属のものも同時に考えます。
一貫性が必要なので、まずテーマを決めます。どこを山にして、引いて……と考えながら、骨董や現代作家さんのもの、色や材質が偏らないように、とバランスを取ります。
一度たたき台を作って、そこから入れ替え差し替え。一つ入れ替えると崩れる、というくらい根を詰めて決めるので、確定したら、めったなことがない限り1カ月同じ器で通します。
続きを読むには
無料で30日間お試し※
- 会員限定記事1,000本以上、動画50本以上が見放題
- ブックマーク・コメント機能が使える
- 確かな知識と経験を持つ布陣が指南役
- 調理科学、食材、器など専門性の高い分野もカバー
決済情報のご登録が必要です。初回ご登録の方に限ります。無料期間後は¥990(税込)/月。いつでもキャンセルできます。
フォローして最新情報をチェック!