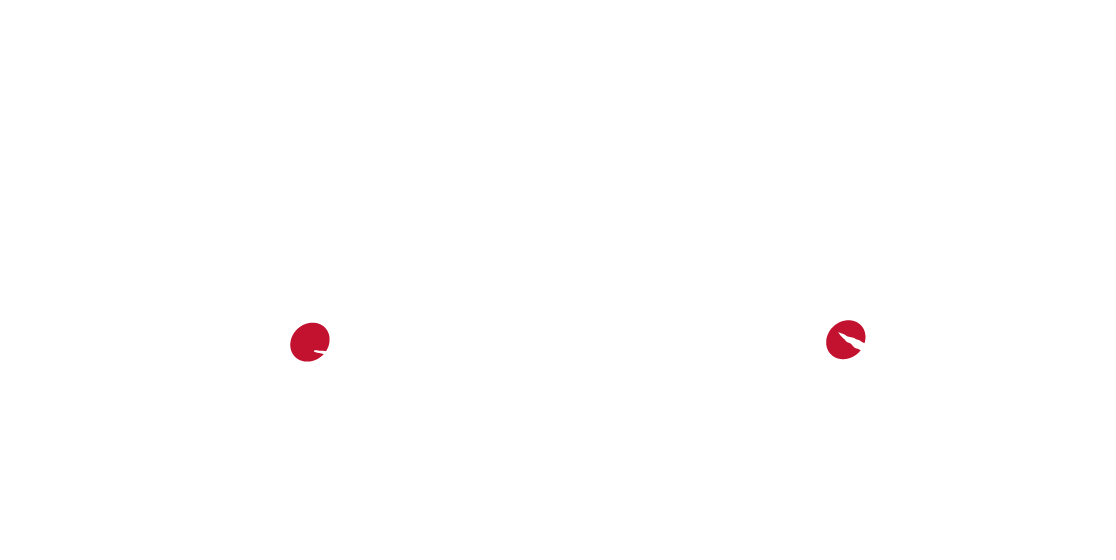能登・輪島『海辺の杣径』北崎 裕さんに聞く【5問5答】
能登・輪島『海辺の杣径(そまみち)』料理長の北崎 裕(ゆたか)さんに迫る5問5答。「素材そのものの持ち味」を大切にする北崎さんの野菜を中心とした料理、調味料の使い方や器のことをはじめ、輪島塗の塗師・赤木明登(あきと)さんと開業した『茶寮 杣径』『海辺の杣径』と能登半島地震の影響についてお話をうかがいました。
どのような料理を意識していますか?
野菜を中心とした料理を提供しています。学生時代に美術史を学び、室町・安土桃山時代の文化に惹かれ、茶懐石に興味を持ったことから料理の道に入りました。大学卒業後は京都下鴨『京懐石 吉泉』で修業させていただきました。
曹洞宗の精進料理では「淡味」を重視します。淡味の解釈はさまざまありますが、「素材そのものの持ち味」といえばいいでしょうか。単なる薄味を指すのではなく、過剰に味を付け足さず、また何もしないことでもありません。自然の恵み、命の輝きに満ちた味のことです。
この「淡味」がよりわかりやすいのは野菜なので、僕の料理は野菜が中心。野菜そのものの淡い味、食感、香りなどを活かすというより、消さないように、使う調味料もごく少量です。

2024年元日の能登半島地震の影響で建物が損壊し、営業を続けることができなくなった『茶寮 杣径』では日本料理のコースディナーを中心に、震災後に開店した『海辺の杣径』では気軽なランチを中心に予約制でディナーも提供。野菜中心で「淡味」を意識した料理のスタイルは変わっていません。
変わった点としては、震災以降は食材の入手が少し難しくなったこと。生産者がいないから料理はできませんとは言えないので、入手範囲を少し広げて加賀野菜なども使っていましたが、地元産が手に入るときは能登のものばかり使っています。
この辺りの夏野菜はスタートが遅く、終わりも割と遅くて9月まで手に入ります。市場に出回り始めた頃から使っていると、地元の露地ものが出てくる頃には料理人も食べる人も飽きてしまうため、地元で採れ出したら使い、無理して早い時期から他所のものを仕入れてまで使わないようにしています。
海産物においても少しずつ港が回復してきたので、能登町の宇出津(うしつ)港や富山湾側と日本海側の両方から入荷がある七尾港から魚介を仕入れています。
続きを読むには
無料で30日間お試し※
- 会員限定記事1,000本以上、動画50本以上が見放題
- ブックマーク・コメント機能が使える
- 確かな知識と経験を持つ布陣が指南役
- 調理科学、食材、器など専門性の高い分野もカバー
決済情報のご登録が必要です。初回ご登録の方に限ります。無料期間後は¥990(税込)/月。いつでもキャンセルできます。
フォローして最新情報をチェック!