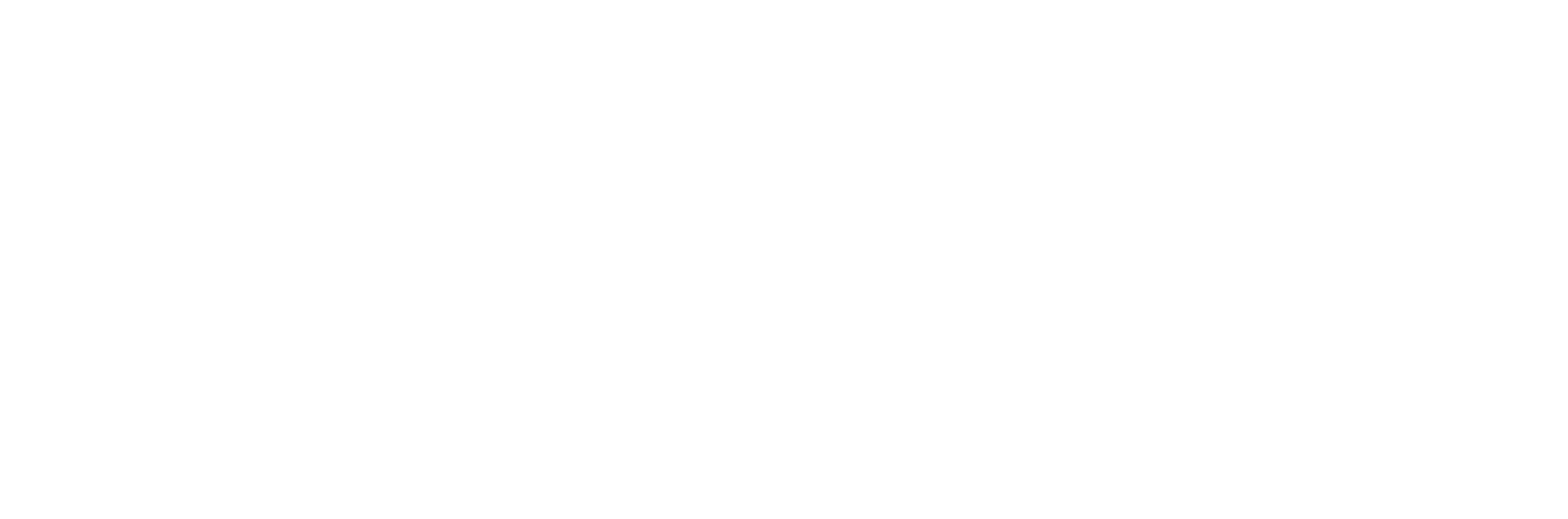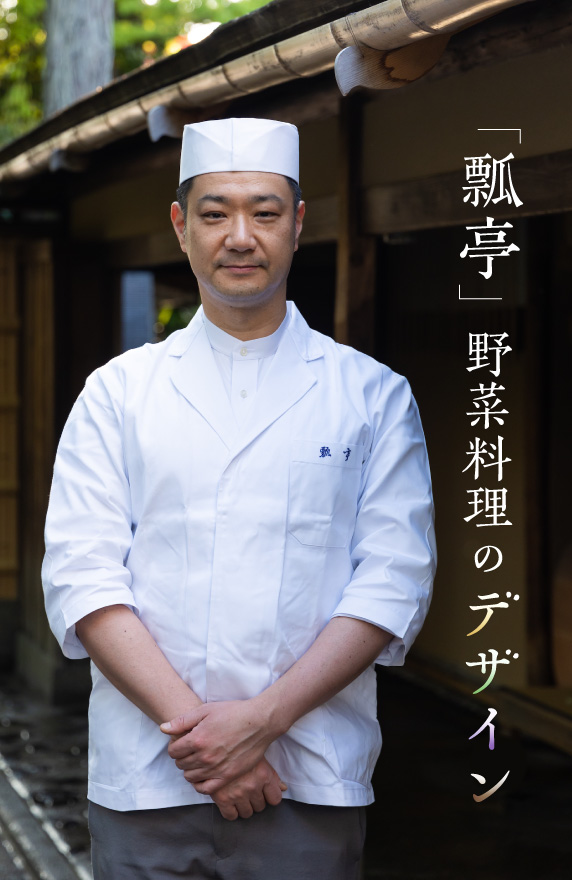懐石のうつわの名品を、懐石の流れに沿って体感する展覧会
「懐石」は、茶事で濃茶の前に、お腹を和らげるために食べる質素な食事のことです。亭主自らが温かいものを温かいうちに一品ずつ出すという給仕の方法、献立に季節を取り入れるという心遣い、そして、多彩なつくり手が共演するうつわなど、和食のもてなしに大きな影響を与えました。
今回は、滋賀・信楽の『MIHO MUSEUM』にて開催されている、所蔵の名品を用いた「懐石の器」展をご紹介。懐石のうつわの本来の使い方や盛り付けなどが学べる展覧会です。
うつわだけでなく、懐石の流れやうんちくも学べる展示

懐石の流れに沿ってうつわを展示。実は、陶磁器よりも漆器が重用されていたという。
展示の第1章では、懐石の流れに沿ってうつわと料理を解説。料理屋文化の中で醸成された宴会料理の「会席」では前半に前菜のような扱いで出すことが多い「八寸」が、懐石では終盤にシンプルな酒の肴として登場。会席がいかに懐石からヒントを得て、現在のような豪華なコース料理のスタイルに至ったのか、ということに注目すると面白い。
懐石では最初に、折敷にのせた飯椀、汁椀、向付が出てくる。ふたつの塗りの椀の“向こう”に置かれる焼き物のうつわが向付。ここには刺身やなますを盛るが、食べた後も折敷の上に残し、焼き物の取り皿としても用いる。長い時間、折敷の上にあり、最も強く印象に残ることから、懐石のうつわの中で、向付のデザインには特に工夫がこらされる。

向付はうつわの名前であり、盛り付ける料理の呼び名でもある。
続きを読むには
無料で30日間お試し※
- 会員限定記事1,000本以上、動画50本以上が見放題
- ブックマーク・コメント機能が使える
- 確かな知識と経験を持つ布陣が指南役
- 調理科学、食材、器など専門性の高い分野もカバー
決済情報のご登録が必要です。初回ご登録の方に限ります。無料期間後は¥990(税込)/月。いつでもキャンセルできます。
フォローして最新情報をチェック!