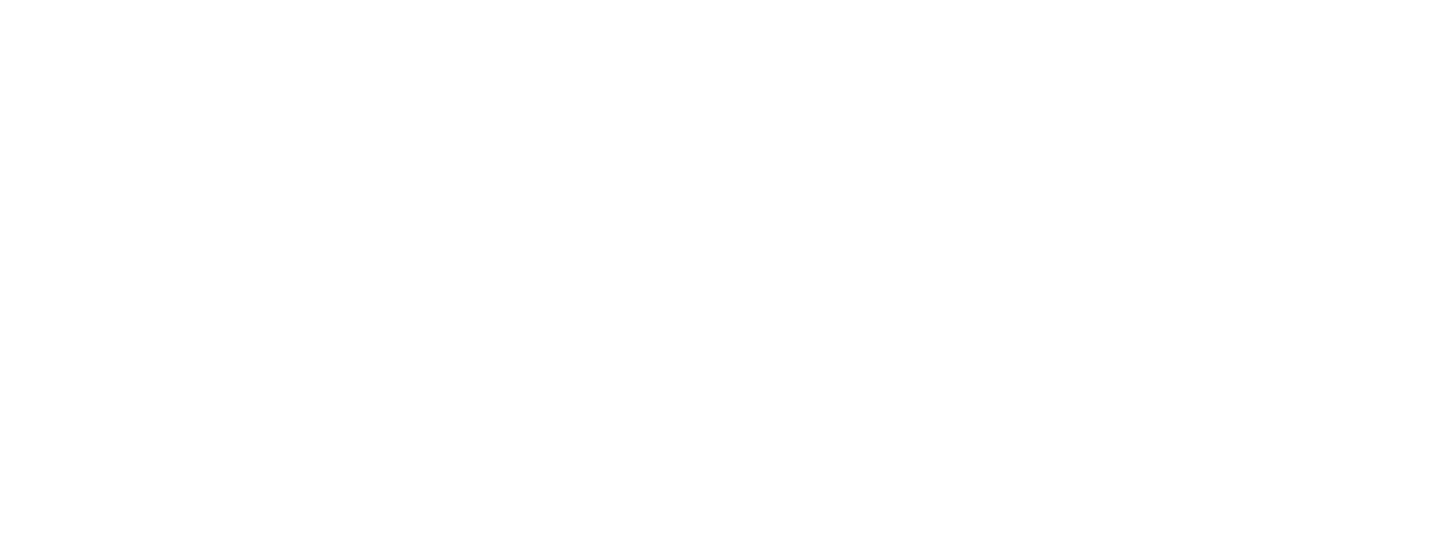鯛のアラだしに塩〆の下処理は必要か?
魚のアラでだしを取るのに、アラを塩〆しますか? 霜降りはしますか? 農学博士の川崎寛也先生は、「どちらも臭み取りが目的の慣習的な下処理だと思うので、新鮮な魚を使うなら必要ないのでは?」と示唆します。それを聞いた大阪・北浜の日本料理店『弧柳(こりゅう)』の松尾慎太郎さんは唖然。そこで、下処理なしと塩〆した鯛のアラでだしを取り、比較実験を行いました。まずは、霜降りせずに煮出した鯛アラのだし比べ。続いて、焼いてから煮出すと…。アラを塩〆する本当の意味に迫ります。
文:中本由美子 / 撮影:香西ジュン
-

-
松尾慎太郎さん(大阪・北浜『弧柳』店主)
1975年、大阪府吹田(すいた)市生まれ。調理師専門学校卒業後、法善寺横丁『浪速割烹 㐂川(きがわ)』に入り、12年間、腕を磨く。他ジャンルの料理店でも経験を積んで2009年、北新地にて独立。22年、北浜に移転し、瀟洒な館を新築。大阪産の食材を駆使し、センスある仕事を施した料理を、骨董や現代作家のうつわで提供。持ち前の誠実さと探求心で、新たな大阪料理をコースで提案している。
-

-
川崎寛也さん(農学博士)
1975年、兵庫県生まれ。京都大学大学院農学研究科にて伏木 亨教授に師事し、「おいしさの科学」を研究。「味の素㈱」食品研究所エグゼクティブスペシャリストであり、「日本料理アカデミー」理事。「関西食文化研究会」での基調講演でも活躍している。専門は、調理科学、食品科学など。近著に「おいしさをデザインする」「味・香り『こつ』の科学」(柴田書店)。
アラだしを取る前の塩〆は逆効果?
- 川崎寛也(以下:川崎):
- 以前から、魚のアラだしを取るのに塩〆の下処理はいるのか?と疑問に思っていまして。塩〆すると、だしが出にくい状態になるはずなんですよ。
- 松尾慎太郎(以下:松尾):
- えっ! そうなんですか? うちの鯛だしは、アラに約2%の塩をして一晩おき、霜降りしてからカツオ昆布だしで15分煮出して取ります。味はいいと思うのですが…。
- 川崎:
- 流通がよくなかった時代はアラに臭みがあったため、それを取り除くために塩をして脱水させてから煮出す方法が良しとされた。
でも、現代の魚は鮮度がいいので、必要ないんじゃないかな?
- 松尾:
- 僕は塩〆は臭み抜きより、旨みを抽出しやすくするための工程だと思ってました…。
- 川崎:
- 「塩〆と昆布〆、焼物における効果とは?」で、塩〆のメカニズムを説明しましたよね。
魚の身に塩をすると、浸透圧が起こって脱水もしますが、細胞膜が壊れて塩が拡散することで保水もする。この水分はアミノ酸などのうま味を含んだ結合水で、加熱しても出てこないんですよ。
- 松尾:
- 確かに、塩〆した鱧はしっとり焼き上がって、旨みが身に留まっていました。ということは…そうか、だしの場合は旨みを引き出したいから、塩〆は逆効果になるのか…。
- 川崎:
- そうでしょう! 塩〆した身は煮出しても旨みがたっぷり残って、出がらしにはならない。その分だけ、だしの旨みが弱くなるはずなんですよ。
- 松尾:
- 俄然、興味が湧いてきました! 鯛のアラだしで実験してみましょう。
この記事は会員限定記事です。
残り:2864文字/全文:3766文字
続きを読むには
無料で30日間お試し※
- 会員限定記事1,000本以上、動画50本以上が見放題
- ブックマーク・コメント機能が使える
- 確かな知識と経験を持つ布陣が指南役
- 調理科学、食材、器など専門性の高い分野もカバー
決済情報のご登録が必要です。初回ご登録の方に限ります。無料期間後は¥990(税込)/月。いつでもキャンセルできます。
フォローして最新情報をチェック!