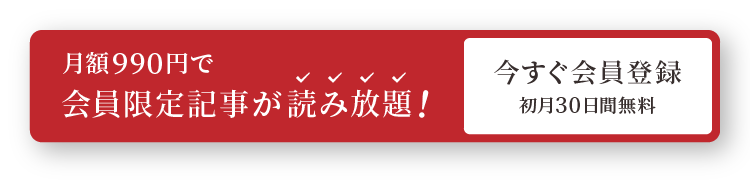パリ15区『茶懐石 秋吉』の挑戦vol.1
今年の1月24日、パリ15区にフランス初の茶懐石店がオープンしました。店主は、京都・南禅寺の『瓢亭』で10年の修業を重ねた秋吉雄一朗さん。日本屈指の料亭で茶道を学び、「一期一会」のもてなしに触れ、渡仏。大使館の公邸料理人を経て、独立を果たしました。6月、大きな茅の輪を玄関に据えて客を迎える『茶懐石 秋吉』。彼の地で、茶懐石と、その精神を伝えるべく、日々、奮闘する秋吉さんの挑戦を、2回にわたるルポルタージュでご紹介します。
パリの街中で“茅の輪くぐり”を

パリの6月吉日、清々しい晴天。エッフェル塔のお膝元、ユネスコ本部にもほど近い15区の静かな住宅街に『茶懐石 秋吉』を訪ねた。杉の木を張った清新な外観の玄関口には、夏越の祓(なごしのはらえ)のための茅の輪が据えてある。
茅の輪くぐりは、心身を清め、残り半年の無病息災や家内安全を祈願するという夏越の祓を象徴する行事だ。
『茶懐石 秋吉』店主・秋吉雄一朗さんの奥様で、女将の三鈴さんが、「この時期が来ると、あの店には大きな輪のようなものが飾られる、と気付いてくださるだけでもいいんです」と笑って迎え入れてくれた。
日本の季節を映す、しつらえに込めたもの
玄関口の上がり框(かまち)の先に、床の間を模した場所がある。掛け軸と迎え花に、自然に目が引き寄せられた。掛け軸には「白雲中」の文字と、滝の落ちる様子が描かれている。
 「この掛け軸には風帯がない。なぜかと思っていたのですが、描かれている滝をそれに見立てているのかと」と秋吉さん。
「この掛け軸には風帯がない。なぜかと思っていたのですが、描かれている滝をそれに見立てているのかと」と秋吉さん。
「和漢朗詠集の中の一句で、説法なのですよ」。その句は「泉声遥落白雲中(せんせいはるか、はくうんのうちにおつ)」。たなびく白雲から、とどろき落ちる滝の音がはるかに聞こえてくる、という意だそう。6月にふさわしい涼しげで力強い描写であると共に、「遠くの水の声に耳を傾けなさい」と説かれたよう。自身の心と向き合う時間が始まりを告げたような気がした。
「どんなところにも意思がある、という心を分かっていただけるとより喜びがあります」と秋吉さんは言う。オープンしてまだ半年だが、先日、フランス人のお客から、「自分たちは食事をしているだけだが、陰の仕事の膨大さを容易に想像できる。本当にありがとう」と言われたそう。心尽くしのもてなしは、少しずつ伝わり始めている。
 カウンターの内側の中央には、茶を点てるためのスペースが設えてある。
カウンターの内側の中央には、茶を点てるためのスペースが設えてある。
約50平米弱の店内には、楠の木のカウンターが2本、個室のように設えた空間には一枚板の栃の木のテーブルが置かれている。杉の木と、漆喰の壁、床板は暖色の栗の木。板場の上には、伊勢神宮の神棚が祀られていた。伝統工芸を受け継ぐ『鹿田室礼』の簾(すだれ)も届いたばかりだ。神聖な空気が漂い、一瞬にして街の喧騒が遠のいていく。
 プライベートな空間を演出したテーブル席。栃の一枚板の天板が存在感を放つ。
プライベートな空間を演出したテーブル席。栃の一枚板の天板が存在感を放つ。
『瓢亭』で学んだ一期一会のもてなし
秋吉雄一朗さんは1984年、福岡・飯塚市に生まれた。父も和食の世界に身を置き、料亭『茶寮このみ』の料理長をしていたという。
京都・南禅寺の老舗料亭『瓢亭』の門を叩いたのは、その父がきっかけだった。
『瓢亭』の十四代目・髙橋英一さんは、かつて年に2回、飯塚で茶懐石の料理教室を開催していた。同市には有名な茶道具商があり、その主人が髙橋さんと同じお茶の先生に師事していたことからの縁である。
料理教室のサポートをしていたのが、雄一朗さんの父だった。高校3年の時、料理への思いが高まる中、創業から400年以上という『瓢亭』の歴史を調べて驚き、「好奇心が芽生えました。実際に行って見てみたいと思ったんです」。
父を通してその声が届き、調理師学校には行かず、『瓢亭』で働くことになった。2003年のことだ。髙橋さんからは、料理人としての精神をたくさん学んだと感謝する。当時はすでに調理場に立っておられなかったそうだが、お花のこと、しつらえのことを学んだ。多くのレストランや料理人との繋がりも持たせていただいたという。
『瓢亭』では毎月1~2回、お茶の稽古をしており、おかげで茶道にも親しむことができた。その中で、「一期一会」を旨として、誠心誠意料理を仕立てる精神をも学んだという。「千利休が求めていた侘び茶の精神が持つ、静寂の力に徐々に感銘を覚えました」。
400年以上前からあるという『瓢亭』の茶室には、特別の思いを持った。
「土壁は、藁を混ぜて塗り固められたものです。時間が経つと藁の灰汁が表面に浮き出てきて、しみになる。これは、新しい壁では生まれ得ない、何百年もの時間が醸し出した景色です。小さな茶室ですが、時空を超えたスケールに圧倒されたのです」。
パリで独立するにあたって、料理にもしつらえにも、おもてなしにも、そうした心を具現化したいと、秋吉さんは強く思っている。
 懐石料理のクライマックスは、秋吉さんが自ら点てる一服の抹茶。厳粛なムードが漂うシーンだ。
懐石料理のクライマックスは、秋吉さんが自ら点てる一服の抹茶。厳粛なムードが漂うシーンだ。
 宇治の『丸久小山園』や秋吉さんの母の出身地である福岡・八女(やめ)の『星乃製茶園』の抹茶を使用。真葛焼 宮川香齋三代目作「祥瑞(しょんずい)腰捻茶碗」で、渾身の一服を。
宇治の『丸久小山園』や秋吉さんの母の出身地である福岡・八女(やめ)の『星乃製茶園』の抹茶を使用。真葛焼 宮川香齋三代目作「祥瑞(しょんずい)腰捻茶碗」で、渾身の一服を。
ヨーロッパのガストロノミーに刺激を受けて
『瓢亭』に入って6年目、秋吉さんは別館の料理長になった。
「先輩たちが卒業する時期に当たったため、テンポよくステップアップできたのは幸運でした」。
同時期、日本料理アカデミーが発足。海外の料理人やジャーナリストが『瓢亭』の厨房に訪れるようになると、英語ができた秋吉さんは進んでコミュニケーション役を担った。
この頃から、海外で料理人としての自分を試してみたい、という願望が芽生えてきたという。修業期間も10年になろうとしていた頃、在パリOECD(経済協力開発機構)大使公邸料理人の話が舞い込んできた。2013年11月に渡仏し就任、という急展開だった。
日本に比べてパリは、旬を表現できる素材が圧倒的に少ない。流通システムも一通りでないため、食材を揃えるのも一苦労。けれど、日本から離れることで、視野が広がったと秋吉さんは言う。
パリでは他業種の人々と盛んに交流し、知見を広げることができた。世界最高峰と言われるフランス料理や、各地の高級レストランを体験し、感性も刺激された。
例えば、イタリア・ピエモンテで味わった、アーティチョークのペーストとトリュフを入れた茶碗蒸し仕立てのロワイヤル。繊細でありながら、鮮烈にトリュフが香るこの料理と、バルバレスコの赤ワインは最高のペアリングだった。
アラン・パッサール率いる3つ星レストラン『アルページュ』では、野菜だけなのに力強い味わいを表現するラヴィオリに衝撃を受けた。パリの2つ星シェフ、ダヴィッド・トゥタンの料理も、繊細な味わいと香りの組合せに大きな発見があった。
3年の任期を終えて帰国。自分の城を持ちたいと強く思うようになっていた。勝負をするならよく知る場所で、と考えた時、京都ではなくパリに軍配を上げた。パリでは和食への希求も高まっており、挑戦しがいがあると感じたのだ。
投資家の方々の支援を力に、19年10月、やっと契約にこぎつけた。ヨーロッパでも実績のある建築家や、佐賀の数寄屋大工との信頼関係を紡ぎ、内装は日本で造り、現場で組み上げる体制を整えた。実に3年の月日を経て、ようやくパリ初の茶懐石店は完成した。
 屋号の文字は『瓢亭』髙橋英一さんによるもの。感謝の想いを込めて、引き戸には『瓢亭』でも用いられる瓢箪(ひょうたん)の意匠を凝らした。
屋号の文字は『瓢亭』髙橋英一さんによるもの。感謝の想いを込めて、引き戸には『瓢亭』でも用いられる瓢箪(ひょうたん)の意匠を凝らした。
スペシャリテはライブ感のある鯖寿司
『茶懐石 秋吉』のおまかせは、昼も夜も一斉スタートだ。席入りしたら、まずは汲(く)み出し。心を整えていただくための一杯の茶が振る舞われ、茶懐石の品書きに則って料理が供される。
その中で、とりわけ座が沸く一幕がある。
スペシャリテの鯖寿司が目の前で仕立てられ、熾(おこ)った炭を皮目に当てるシーンだ。立ち上がる煙、芳しい香り。そのパフォーマンスに一同が目を奪われる。

鯖はノルウェーから冷凍で届いたものだ。日本で気に入って使っていた、脂のりの素晴らしい韓国・済州島の冷凍鯖によく似ているのだと言う。
生魚を食べ慣れないフランス人に、きずし(〆鯖)はハードルが高い。分かりやすい寿司にして、皮目を炭火で炙るパフォーマンスを加えた。
フランス人は淡い味わいが続くことに慣れておらず、一品ごとにメリハリが必要だと考え、シャリは黒酢と米酢をブレンドし、初摘みのプレムアムな海苔、シソ、ゴマの風味を添えた。薬味は、前後の料理の味わいによって、ショウガ、柚子胡椒などに変えるという。
 器は唐津焼の陶芸家、『雷山房』の内村慎太郎作。瓦のような力強さだ。
器は唐津焼の陶芸家、『雷山房』の内村慎太郎作。瓦のような力強さだ。
秋吉さんは、パリでワインの美味しさに開眼し、ペアリングも用意している。
鯖寿司には、この日、ブルゴーニュの赤ワイン、メルキュレイ「フランソワ・ニコラ」の2019年を。ピノ・ノワールのスパイシーな風味と見事な相性を奏でていた。
(vol.2に続く)
【住所】59 Rue Letellier,75015 Paris FRANCE
【お料理】懐石料理おまかせコース:昼:平日160ユーロ~、夜:平日240ユーロ~。
【公式HP】https://chakaiseki-akiyoshi.fr/ja/
【Instagram】https://www.instagram.com/chakaiseki_akiyoshi/
フォローして最新情報をチェック!