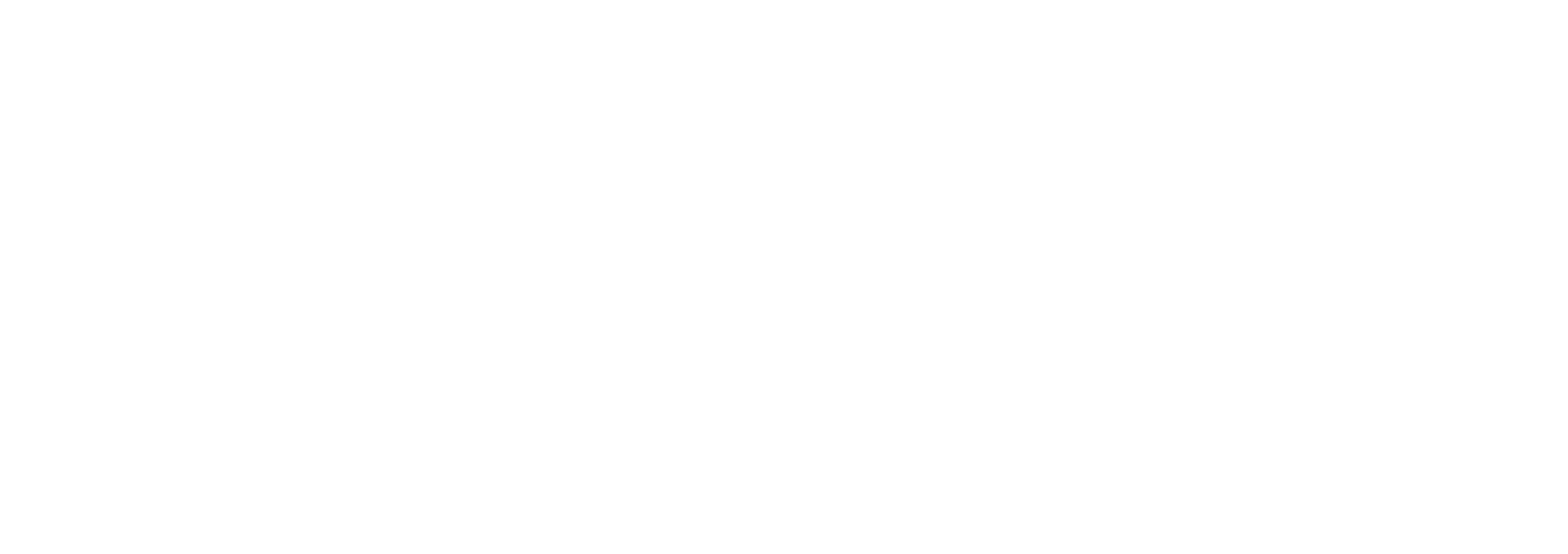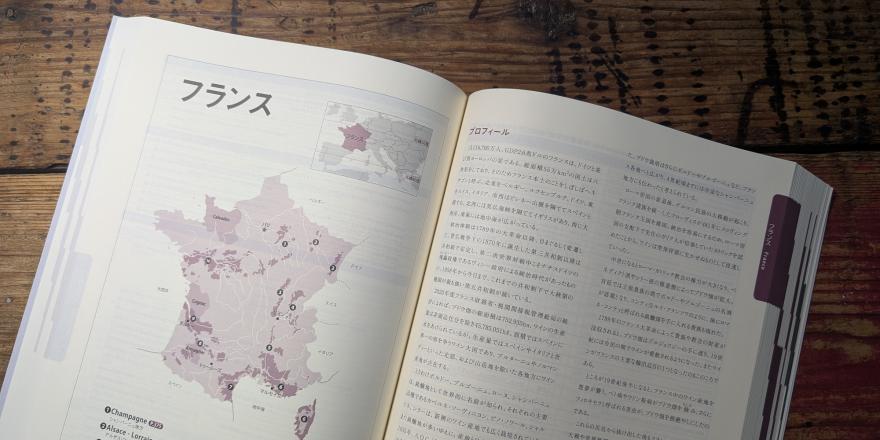料理人のためのソムリエ試験対策 Vol.13 二次試験を意識したテイスティング
ソムリエの松岡正浩さんから学ぶ「料理人のためのソムリエ試験対策」第13回目は、二次試験の実践に即した対策について。問われる項目や、解答までの思考の流れをご伝授いただきます。イメージしながら練習を繰り返すことで、「合格」への道がぐっと近くなります。
-

-
松岡正浩(「合同会社 まじめ2」代表 / 大阪・北新地『空心 伽藍堂』シェフソムリエ)
兵庫県出身。山形大学に進学後、県内のホテルに就職。東京『タテル ヨシノ 芝』にて本格的にフランス料理の世界に入り、その後、渡仏。『ステラ マリス』を経て、パリの日本料理店『あい田』ではシェフソムリエとして迎えられた。帰国後、和歌山『オテル・ド・ヨシノ』にて支配人兼ソムリエを務め、2016年、日本料理『柏屋』へ。こちらでも支配人兼ソムリエを務め、ワイン・日本酒を織り交ぜたペアリングコースを提案。レストランガイド「Gault&Millau(ゴ・エ・ミヨ)2021」にてベストソムリエ賞受賞。2022~23年、京都・御所東のフランス料理『Droit(ドロワ)』においてギャルソンとして勤務。23年6月より、大阪・北新地の中国料理『空心 伽藍堂』にてシェフソムリエを務める。
二次のテイスティングは、例年ソムリエ呼称においてはワイン3アイテム、その他のお酒2アイテムが出題され、試験時間は40分。エキスパート呼称はワイン4アイテム、その他のお酒1アイテムで50分となっております。
「その他のお酒」に関しては銘柄のみを選択肢から選ぶため、それほど時間がかからないとしても、ワイン1アイテムに対して十数分の時間しか割り当てられず、悩んでいる暇はないと言っても過言ではありません。
その限られた時間内に外観、香り、味わい、評価の各コメントに加え、収穫年や主なブドウ品種等、合計100以上の項目についてマークしなくてはなりません。ですから、できるかぎり簡素にパターン化して、事前に手順をイメージしておきたいわけです。
この試験時間に対応するために、試験本番を意識したテイスティング方法についてお伝えします。
外観
もしかすると、ワインの情報の中で最も重要な要素は「外観」かもしれません。外観は最初に視覚によって得られる情報であり、この段階でワインの方向性をある程度想像することができるからです。
入場時とオリエンテーション時にワインを観察する
二次試験は多くの場合、ワインやその他のお酒が注がれたグラスがテーブル上に並べられた状況で席に案内され、定刻になるとオリエンテーションが始まります。
この入場時とオリエンテーションの時間にしっかりと外観を観察しましょう。さらに、外観で選択すべき「色調」「濃淡」などのコメントをさっとイメージし、ワインの方向性について大まかに検討します。
試験開始前のこの時間に、これから始まるテイスティングの流れをイメージすることが、短い試験時間を有効に活用する重要なテクニックの一つです。
二次試験における外観の項目
二次試験において外観で問われる項目は下記の通りです。
「清澄度」
「輝き」
「色調」
「濃淡」
「粘性」
「外観の印象」
「清澄度」と「輝き」はほぼ選ぶコメントが決まっているため、特に「色調」と「濃淡」を見極められるようになることが重要です。
白ワインの外観について
白ワインの場合、外観で最初に意識すべきことは「グリーン」のニュアンスを感じ取れるのか、そして「淡い」のか「濃い」のかという点です。この細かな違いをスムーズに判断できるようになると、白ワイン対策はかなり前進したと言えます。
白ワインの「色調」は主に以下の選択肢(コメント)から選ぶことになります。
“グリーンがかった”
“レモンイエロー”
“イエロー”
(その他にも選択肢がありますが、概ねこの3つからの選択です)
なによりも“グリーンがかった”を選択するかどうかが大きなポイント。そして次に、「濃淡」はどのレベルであるのかを判断するという流れです。
そのためにもいろいろなワインを経験して、「淡く、ほんのり黄緑っぽい」「濃くも淡くもないけど、グリーンは感じない」「完全に黄色、暖かさを感じる」など、ご自身の基準をしっかりと持てるようになることがとても大切です。
白ワインの色調の変化について
白ワインの色調はブドウ品種由来の場合もありますが、一般的に新しいワインほどグリーンの印象が強くなります。そして、年月が経つにつれてそのグリーンが失われ、熟成するにつれてイエローが強くなり、最終的には褐色に近くなります。
同じブドウ品種でも暖かい産地で栽培されたブドウから造られたワインは色調が濃くなり、アルコール分も高くなるため「粘性」も強くなります。
また、樽熟成させた白ワインは、それなりの期間熟成させることになるため、フレッシュなワインの特徴であるグリーンが少なくなり、樽からの影響と酸化熟成により色が濃くなります。
ですから、例えばグリーンのニュアンスで、淡いと感じたなら「冷涼な産地のソーヴィニヨン・ブランかな…」、一方でグリーンを感じず、イエローで濃いと感じた場合、「樽で熟成させた温暖な産地のシャルドネかな…」と、この時点でイメージするわけです。
赤ワインの外観について
赤ワインに関しては、とにもかくにも「淡い系」なのか「濃い系」なのかを判断します。
「淡い系」→ ピノ・ノワール
「濃い系」→ カベルネ・ソーヴィニヨン、シラー(シラーズ)
まずは、この公式です。ソムリエ試験に出題されるアイテムとしては「淡い系」でカベルネ・ソーヴィニヨンは絶対にありえませんし、反対も然りです。
その後、「淡い系」でピノ・ノワール、もしくは「濃い系」でカベルネ・ソーヴィニヨン、またはシラー(シラーズ)とはどうしても考えられない、大いなる違和感を覚えた時のみ、その他の可能性を考えましょう。
それでも、経験の少ない方なら、この違和感を無視して、上記の公式の通りに解答を進めた方が正答率は高いと経験上感じております。同じブドウ品種でも様々なワインが世界中で造られているため、ブドウ品種の個性がわかりやすいワインとそうではないワインが存在するからです。
一方で、「淡い系」とも「濃い系」とも判断できない微妙なワインも出題されるのですが、これらは一次試験突破後に余裕があれば取り組みましょう。
赤ワインの「色調」は、以下のようにコメントを二つ選択する場合があります。
“紫がかった” “ガーネット/ダークチェリーレッド”
“縁が明るい” “ルビー/ラズベリーレッド”
この選択数に関しては、マークシート用紙に記載があるので注意が必要です。
ということで、これまで以上にしっかりと外観を観察することから始め、外観の段階である程度ワインのタイプやブドウ品種をイメージした状態で香りに進むという流れが二次のテイスティング攻略のコツといえます。
香り
ワインのテイスティングにおいて、慣れないうちは「言葉にすること(コメントにすること)」が最も難しいのが「香り」ではないかと思います。だからこそ、口を酸っぱくして「テイスティングして書き留めてください」と言い続けてきました。言葉に変換する訓練が必要だからです。
二次試験における香りの項目
香りで問われる項目は下記の通りです。
「第一印象」
「特徴(果実・花・植物)」
「特徴(香辛料・芳香・化学物質)」
「香りの印象」
とはいえ、「特徴(果実・花・植物)」「特徴(香辛料・芳香・化学物質)」の各コメントは、概ねワインのタイプごとに決まっているため、過去の模範解答や各テキストの記載を基本的に丸暗記しましょう。このコメント対策は一次試験通過後に始めても十分に間に合います。
一次試験を突破するまでは、上記の「特徴」の項目で選択する細かいコメント以上に、主要ブドウ品種ごとに特徴的な香りを二つほど理解することがとても大切です。人はそれぞれ感じやすい香り、味わいがあるようで、万人が同じように感じるわけではないようですが、ご自身で得意な香り、感じやすいポイントを見つけて欲しいのです。
例えば、ソーヴィニヨン・ブランといえば「フレッシュハーブ」、「ライム」といったように、主要ブドウ品種ごとに、ご自身で感じ易い香りを見つけてください。残念ながら同じブドウ品種であっても当てはまらないワインも多数存在するのですが、最大公約数的な特徴を知ることに意味があります。
外観から香りへの流れ
「外観」である程度ワインのタイプに目星をつけておりますから、その流れの通りに香りを感じることができるかどうかがポイントになります。
白ワインにおいて、例えば外観で「グリーンがかった」「淡い」「(粘性)やや軽い」とイメージ(コメントを選択)して香りに進んだ場合、香りの第一印象で「濃縮感のある」や「複雑な」、「力強い」を選ぶ可能性は限りなく低く、爽やか系白ワインのコメントを選ぶ流れになります。
赤ワインの場合、「淡い系」と判断した場合、ピノ・ノワールを想定することがセオリーですから、華やかな赤系果実の香りが感じ取れるとホッとするわけです。
このように外観で得た情報のイメージ通りにテイスティングが進むことによって、テンポ良く分析を続けることができます。このことからも外観から得られる情報がいかに大切であるかをご理解いただけるかと思います。
味わい
外観で大まかなイメージ、方向性を感じ取り、香りでその流れが正しかったのかどうかを確認しました。この外観から香りに至る過程が順調であれば、味わいで最終確認です。ただ、すんなりと進まないことも多いのですが。
一方で、いくらイメージ通りに進んでも、ワインのタイプやブドウ品種を決めつけて視野を狭めてはいけません。
さて、一呼吸おいてから味わいに進みます。
味わいで問われる項目
味わいで問われる項目は下記の通りです。
「アタック」
「甘み(アルコールのボリューム感も含む)」
「酸味」
「苦み」白ワインのみ
「タンニン分」赤ワインのみ
「バランス」
「アルコール」
「余韻」
外観、香りのコメントの選択も慣れないうちは大変なのですが、味わいのコメントは、味覚という個人差の大きい感覚に頼ることになるため、ある意味難しいように思います。これは味わいに限ったことではありませんが、ご自身の感覚とソムリエ協会のコメントをよりすり合わせなければならないからです。
味わいの評価順序
「アタック」は口に含んだ最初の印象、「余韻」は最後に感じ取るものなので、以下の順で評価を進めます。
「アタック」→「甘み」→「酸味」→「苦み」(白ワインのみ)/「タンニン分」(赤ワインのみ)→「バランス」→「アルコール」→「余韻」
一次試験を突破するまでは、それぞれの項目について、弱・中・強の三段階くらいを意識してテイスティングを続けましょう。
そして、味わいもこれまでと同様に、外観・香りで得たイメージが、そのまま違和感なくつながっているかを確認します。
白ワインの場合、外観で「濃い」「イエロー」を、香りで「凝縮感のある」や「力強い」を選択した場合、温暖な産地のシャルドネをイメージしているでしょうから、味わいも全体的に強いコメントを選択する方向であれば概ねうまく進んでいるということです。ただ、酸味に関しては温暖産地は反比例するため、「シャーブな」や「爽やかな」ではなく、「なめらかな」などのコメントを選択することになります。
このように外観から味わいまでの流れ、パターンを意識することで、より二次試験的なテイスティング方法に近づきます。
二次試験について過去の受験者から学ぶ
インターネット上には、数多くの過去の二次試験情報がアップされております。これまでに受験された方の感想や苦悩に目を通しつつ、試験の流れを改めて理解し、より実践的なテイスティング方法を身につけましょう。以前にも紹介した「ちょっとまじめにソムリエ試験対策こーざ」にも過去の十年間ほどの受験報告を掲載しております。
また、同様に二次試験時に配布される「テイスティング用語選択用紙」もネット上を探せば手に入れることができると思います。「テイスティング用語選択用紙」の内容を頭に入れた上でテイスティングを行うことで、より試験本番に即したワインのタイプ分け、ブドウ品種の分析が可能になると思います。
ソムリエ試験対策も佳境に入ってまいりました。次回は、二次のテイスティングを突破するための最重要ポイントの一つ、「ワインのタイプわけ」について、白ワイン編からお伝えいたします。
▼料理人のためのソムリエ試験対策 他の回はコチラから。
Vol.1 概要編
Vol.2 一次試験対策前にすべきこと
Vol.3 一次試験対策の準備と春先までの勉強法
Vol.4 一次試験対策、教本と過去問を利用した勉強法
Vol.5 二次試験対策の準備
Vol.6 二次試験対策として意識すべきワインについて
Vol.7 テイスティングして書き留める
Vol.8 ワインの酸とアルコール
Vol.9 主要白ブドウ品種の特徴
Vol.10 主要黒ブドウ品種の特徴 その1
Vol.11 主要黒ブドウ品種の特徴 その2
Vol.12 ラストスパート!一次試験前二ヶ月間の一次試験対策
Vol.14 白ワインを3つのタイプに分ける
Vol.15 赤ワインのタイプ分け
Vol.16 二次のテイスティング対策最終章~「模範テイスティングコメントを暗記する」
Vol.17【最終回】三次試験・サービス実技対策
フォローして最新情報をチェック!