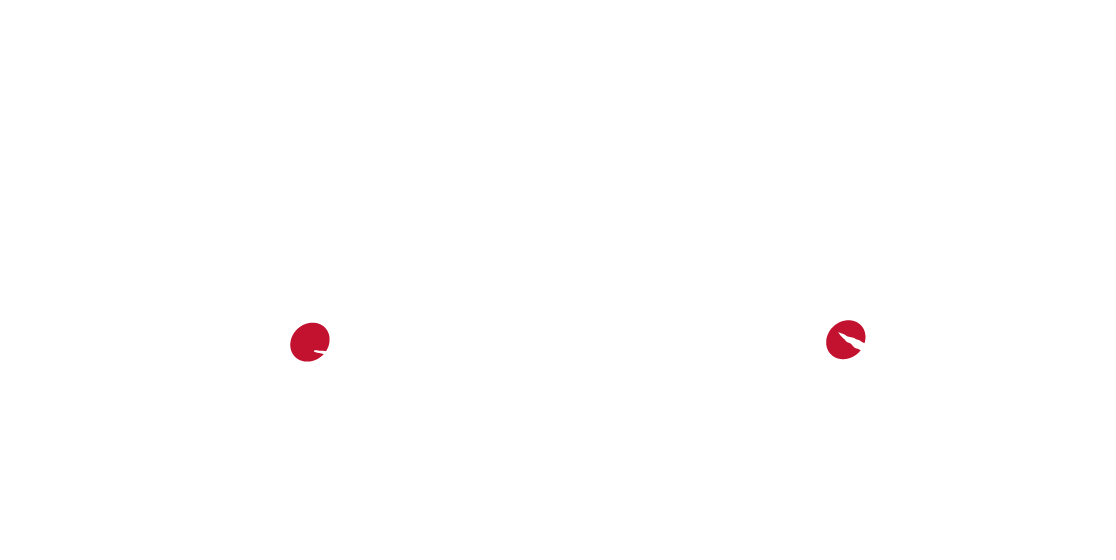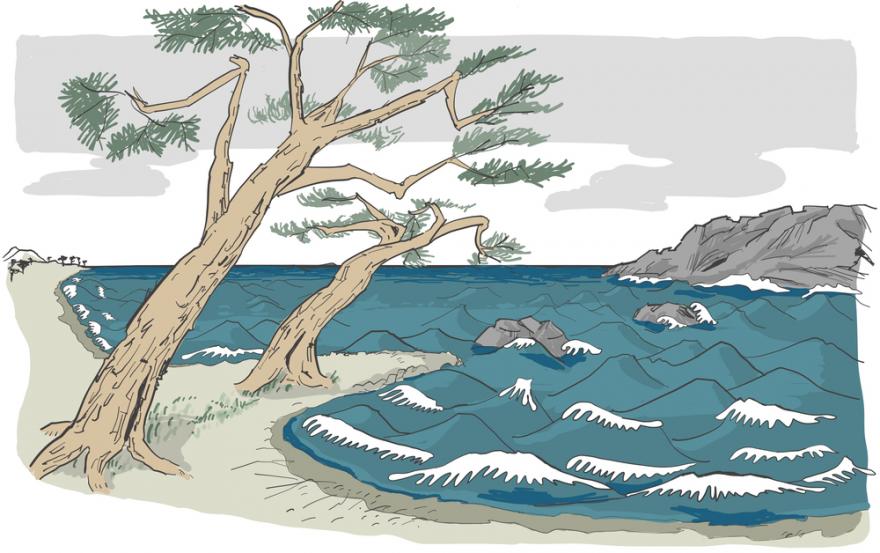【レシピ付き】栗名月の一品 Vol.1 京都『二條 みなみ』の「丹波栗の飯蒸し」
2025年11月2日(旧暦9月13日)の夜は十三夜にあたります。この日に昇る月は中秋の名月(十五夜)に次いで美しいとされ、わずかに欠けた月を愛でるという、日本独自の趣き深い風習が今も息づいています。十五夜が「芋名月」と呼ばれるのに対し、十三夜は「栗名月」。この時季に旬を迎える栗を使った料理が食卓を彩ります。歳時を大切にする京都『二條 みなみ』でも、兵庫・丹波産の栗をたっぷり使った飯蒸しが供されます。栗の香りと自然な甘み、そしてほのかな芳しさが漂うもち米。滋味深い味わいに仕上げる調理の工夫を教わりました。
京都『二條 みなみ』南 建吾さん作
丹波栗の飯蒸し
京都、二条通の路地奥にて2023年に暖簾を掲げた『二條 みなみ』。店主の南 建吾さんは祇園の粋筋が贔屓にする名割烹『祇園 川上』で25年にわたり腕を磨いた実力派だ。先代・松井新七氏の教え「華美に走ることなく質実の味を守る」——その精神を軸に、伝統的な技と歳時の表現を大切にしながら、新作も少しずつ織り交ぜてコースを展開する。
今回紹介する「丹波栗の飯蒸し」は、『祇園 川上』で供される「白小豆の飯蒸し」のレシピを応用した料理で、質実な味わいの中に独自の進化を感じさせる。提供するのは9月から11月にかけて。コース中盤、アラ焚きや焼き物、煮付けなど直球で力強い料理の後、口を優しく整え、季節を伝える役目を果たす。 仕立ては極めてシンプルで端正。調理の一つ一つを見直して丁寧に磨き上げ、栗名月を象徴する逸品へと昇華している。
「調味だし」を用いて、もち米に香りと下味を付ける
飯蒸しというと、もち米を一晩浸水させ、蒸す間に乾かないよう何度か吸水させるのが一般的だが、その際、南さんは水ではなく調味だしを用いる。「もち米にだしの香りと下味をつけます。色を付けたくないので、薄口醤油はほんの少しだけ」。マグロ昆布だしの量に対して、塩1%と薄口醤油少々。具材が栗以外のものでもこの割合は変わらない。ほど良い塩味がもち米の甘み、具材の味わいを引き立てる。
 もち米は京丹後産を使用。
もち米は京丹後産を使用。
続きを読むには
無料で30日間お試し※
- 会員限定記事1,000本以上、動画50本以上が見放題
- ブックマーク・コメント機能が使える
- 確かな知識と経験を持つ布陣が指南役
- 調理科学、食材、器など専門性の高い分野もカバー
決済情報のご登録が必要です。初回ご登録の方に限ります。無料期間後は¥990(税込)/月。いつでもキャンセルできます。
フォローして最新情報をチェック!