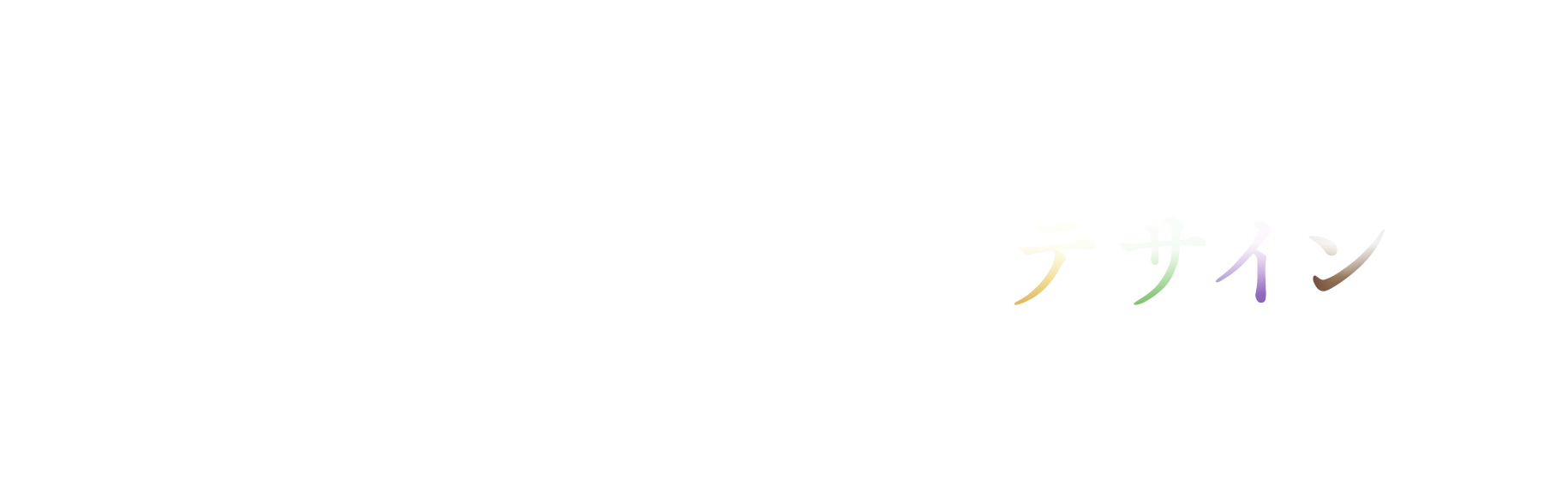【レシピ付き】冬瓜2品——冷やし冬瓜包み&蒸しスープ風の冬瓜と鱧の炊合せ
京都きっての名料亭『瓢亭』の当代・髙橋義弘さんに、旬の野菜をテーマに「守るべき仕事」と「深化させた仕事」を施した2品をご紹介いただく今企画。第4回目は冬瓜がテーマです。炊合せやすり流しにすることが多い食材ですが、『瓢亭』では見た目が涼やかで、もてなしに向く上品な仕立てで供します。色鮮やかな具を冬瓜で包んだ一品と、蒸して発色良く仕上げる炊合せの2品を教えていただきました。
髙橋義弘:創業450年を超える老舗料亭『瓢亭』の15代目当主。1974年、14代目髙橋英一氏の長男として京都に生まれる。東京の大学を卒業後、金沢の日本料理店『つる幸』で修業を積み、1999年帰洛。海外のシェフたちとのコラボレーションなど国内外を問わず、京都の懐石料理を伝える活動に尽力。2015年、15代目に就任し、2018年に東京店を出店。老舗の味を守りながら、時代に即した現代的な日本料理にも取り組み、新しい美味しさの提案を続けている。
冷やし冬瓜包み——色鮮やかな具材がうっすら透け、食べ手の心を誘います

料理/冷やし冬瓜包み 器/染付南京深鉢
冬瓜は、6月から10月頃まで、産地は限定せずにその時にいいものを選んで使っています。ずっしりと重くて、瓜らしい形のものがいいですね。大振りで、皮の色が濃くて分厚い方が、青い香りも強いです。実の中でも茎に近い部分は硬くて少し苦みがあり、真ん中辺りは柔らかい。ワタや種は食感が悪く、瓜くささがあるので、取り除いて使います。
体を冷やす野菜ということもあって、夏に好んで使います。涼しげな色やみずみずしさを生かし、冷やしてお出しすることが多いです。単体より他の食材、特に動物性のものと組み合わせると持ち味がアップしますし、ご馳走感が増します。今回の2品は鰻や鱧を合わせました。
父が考案した「冬瓜包み」は、煮浸しにした冬瓜で具材を包み、喉越しの良い冷たいあんで味わっていただく料理。透明感のある果肉から鮮やかな具材の彩りが透けて見え、涼感溢れる一品です。
この料理は一工程でも加減を間違うと上手く仕上がらない、結構ハードルの高い料理です。冬瓜は面積を広くとるように切り分け、表面の緑色を生かすために皮は薄くムラなく剥きます。皮側の面が硬いので、1cm弱ほどの深さで鹿の子状に切り込みを入れるのですが、細かすぎると具材を包む時に崩れてしまうので、2㎜ほどの等間隔で。そこに塩をすり込んでしばらく置けば、汗をかくと同時に青みが立ち、茹でた時に火が入りやすくなります。
茹でる鍋に銅板を入れる、もしくは銅鍋を使うことも色鮮やかに仕上げるポイント。絹サヤやオクラを湯がく時にも使えますよ。皮側を下にして入れ、落とし蓋をし、湯がき時間は30分を目安に。皮側に竹串を刺して食感が残る程度の硬さに茹で上げます。これを水にさらして瓜くささを取り、やや甘めのだしで炊いて一晩煮浸しにします。
そして一番神経を使うのが、冬瓜をのばして具材を包む工程。
続きを読むには
無料で30日間お試し※
- 会員限定記事1,000本以上、動画50本以上が見放題
- ブックマーク・コメント機能が使える
- 確かな知識と経験を持つ布陣が指南役
- 調理科学、食材、器など専門性の高い分野もカバー
決済情報のご登録が必要です。初回ご登録の方に限ります。無料期間後は¥990(税込)/月。いつでもキャンセルできます。
フォローして最新情報をチェック!