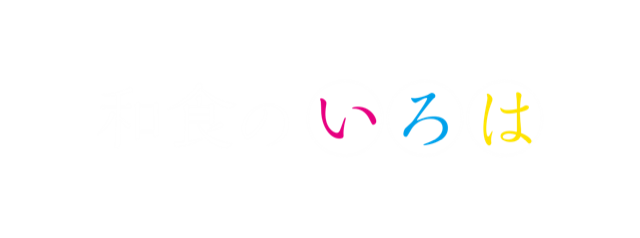冬(12~2月)の和食に彩りを添える飾り葉・かいしき
料理に季節感や彩りを添える植物「かいしき」。冬(12~2月)頃に使うのは、年中、青々とした常緑の葉や、正月を迎えるにあたって縁起の良いものが多いです。代表的な松葉や裏白(うらじろ)、南天(なんてん)、ゆずり葉などの特徴や使い方を「辻󠄀調理師専門学校」日本料理主任教授を務めた畑 耕一郎先生に解説していただきました。
畑 耕一郎(はた こういちろう):大阪生まれ。「辻󠄀調理師専門学校」理事・技術顧問。「大阪料理会」会長。TBS「料理天国」やABC「上沼恵美子のおしゃべりクッキング」など多くのTV番組に出演。『プロのためのわかりやすい日本料理』(柴田書店)など著書も多数。
冬(12~2月)のかいしきの特徴とは?
多くの植物が落葉する時季なので、常緑植物の葉がよく使われます。一年中青々として枯れないことから、祝いの料理にも用いられます。
特に今回紹介する松葉や裏白、南天、ゆずり葉などは、その形状や名前などの特徴から縁起が良いとされ、この季節、正月の料理に添えられることが多いです。
また、時季的に雪が降り、葉に残ることがあるので、葉を水で濡らして片栗粉やコーンスターチなどを付け、初雪や残り雪を演出するのも趣きがあって良いでしょう。
冬(12~2月)によく使われるかいしき
常緑植物は年中使っても良いのですが、今回は縁起が良く、正月に使われるものを中心に、冬のかいしきを紹介します。
松葉

松はその昔、竹、梅と合わせて中国で「歳寒三友(さいかんさんゆう)」と呼ばれ、冬の厳しい寒さの中でも生命力を持つものとして讃えられました。平安時代に日本に伝わり、縁起物としてお祝い事などの象徴になったとされています。
冬の寒さの中でも松は緑の葉を保つので「長寿」の象徴。竹は折れにくく、早く伸びることから「成長」、梅は、春にいち早く香りの良い花を咲かせることから「華やぎ」の象徴です。
松葉は一対になっているので、「生きるのも一緒、枯れて落ちるのも一緒」と、夫婦になぞらえて使うこともあります。また、漢数字の「八」に見えることから、末広がりで、おめでたいとされてきました。
種類は赤松や黒松などがありますが、五葉松は葉が5本で一組になっていて立派です。「御用を待つ」とかけて、「良い仕事が来ますように」という願いを込めて用いることもあります。葉が30㎝もの長さになる大王松は、金銀や紅白の水引と組み合わせると立派な飾りかいしきになります。
祝い事や結婚式、正月のかいしきとして使われることが多く、器に敷いて焼き物をのせたり、黒豆や銀杏(ギンナン)を刺した「松葉刺し」はよく目にする用い方です。祝い事の時には、金箔を付けて料理に添えることもあります。
続きを読むには
無料で30日間お試し※
- 会員限定記事1,000本以上、動画50本以上が見放題
- ブックマーク・コメント機能が使える
- 確かな知識と経験を持つ布陣が指南役
- 調理科学、食材、器など専門性の高い分野もカバー
決済情報のご登録が必要です。初回ご登録の方に限ります。無料期間後は¥990(税込)/月。いつでもキャンセルできます。
フォローして最新情報をチェック!