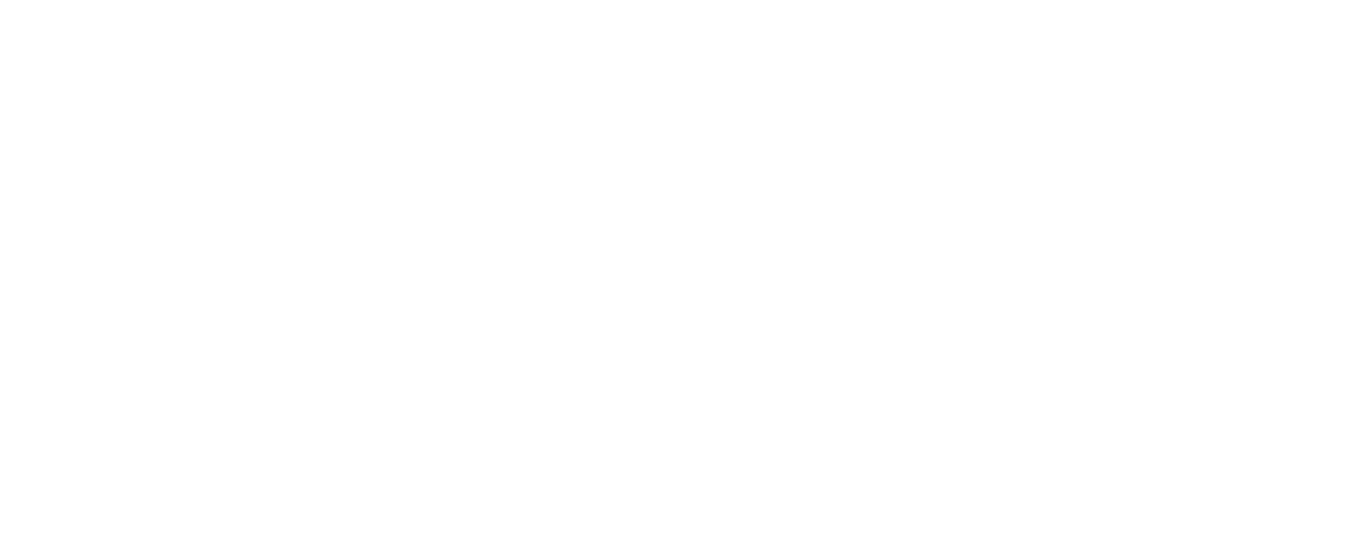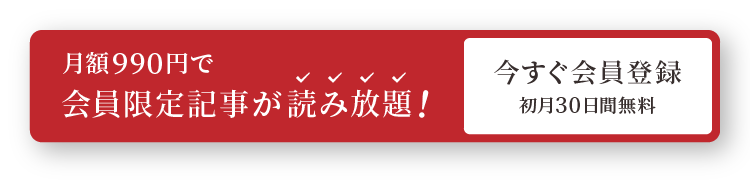蔵元 稲岡敬之さん
1971年 加西市にて誕生
1989年 東京農業大学醸造科に進学
2001年 『富久錦』飲食部門 『ふく蔵』責任者に
2007年 『富久錦』民事再生法を申請
2013年 社長就任。蔵入り
2017年 木桶仕込み開始

ゼロからの出発でも蔵は残したい
「全然隠していないんですけどね」と話し出す稲岡敬之さんの表情も口調も穏やかだ。
「2007年に民事再生法の申請をしました。それが僕の原点です。もう失敗できないと思ってますし、従業員の人生を背負う責任も感じてます」。
先々代であった父が、時代に先駆けて「純米酒宣言」を発したのは1987年。それから5年かけて全量純米蔵への移行を実現した。しかし、思うように消費は伸びない。さらには、阪神・淡路大震災の被害に追い打ちをかけられる形で経営は悪化していく。
「父は、退路を断つ覚悟を持って純米酒宣言をしたと思います。当時、僕はまだ学生で、そのことにどんな意味があるのか分からなかったのですが」。
宣言から20年後の2007年。民事再生の報告に廻った先々で、敬之さんは父親への感謝の言葉を耳にし、驚いたと言う。
「『お父さんに、これからは純米酒や、と言われて良かったと思ってんねん』とか『あなたのお父さんにはホンマに助けてもろた』と言って下さる酒屋さんが多かったんです。当時は借金もあって、うちはボロボロの状態やったんですが、『お父さんの作った繋がりがあるやろ』と励まして下さる方もいて」。
しかしながら、蔵の存続を巡っては、父、兄と議論を重ね、考えあぐねる日々が続く。当時の敬之さんは、会社直営の飲食店『ふく蔵』の責任者で、蔵とは離れた立ち位置にいた。初めて蔵仕事を手伝ったのは、高校生の時。「酒造りは面白い!」と思い、東京農大の醸造科に進学したという経緯もあったが、「自分は次男」という気持ちもあり、酒造りの中枢には入らぬままだった。
「融資するから、人生をやり直せ、と申し出てくれた人もいました」。
“やり直せ”というのは再建ではない。蔵を閉じ、別の職種に就けという意味だ。
「でも、兄(幸一郎会長)も僕も蔵を閉じようとは思わなかった。それで、もし駄目になるにしても後悔がないように、僕も蔵人として働かせてくれと頼んだんです。そうしたら兄は、お前が社長になれ、と」。
木桶仕込みで“土地を表現する酒”を
社長交代は2013年7月。就任した際、敬之さんは父に「親父がやってきたことは正しかったと、これから証明していく」と話したという。そして、同年秋。蔵元であると同時に一人の蔵人として酒造りの現場に入る。
「40歳を過ぎてのスタートですからね。人よりも10年も15年も遅れている。しかも、経営者が蔵に入るわけですから、蔵人たちはやりにくかったろうと思います。『浮いてるな、オレ(笑)』と思いましたが、とにかく、認めてもらうには結果を出すしかないので黙って働こうと思っていました」。
翌年には、全量地元産米を用いた生酛仕込みの純米酒のシリーズ「純青」をリリース。
「いくら蔵が変わったといっても、中身の変化を知ってもらうのには時間がかかる。ならば新しい銘柄を立ち上げる方が早いと」。
酒質を上げるための、原料米の仕入れルートの見直し、新しい洗米機や甑(こしき)の導入、原料処理の変更、麹室内の改革。蔵の中は、短い間に変化に次ぐ変化を受けいれざるを得ない状態となったが、救いは、杜氏の村崎哲也さんが良き理解者となってくれたことだ。
「彼自身も良いものを造って結果を出したいと考える人間で。僕の様々な提案に反対しないでいてくれた。むしろ、いろいろ新しいことができて嬉しいと言ってくれたんです」。
16年には、かつて蔵内にあった木桶を解体。使える部分を選抜し、組み直しをして、翌年には木桶仕込みの酒を復活させた。
「地元の米と水、この木桶で“土地を表現する酒”を造りたかったんです」。
その木桶の周囲の足場を作ってくれたのも、美しい木桶と調和するような柿渋の柱をきれいに塗り直してくれたのも蔵の人たちだった。
「ある時、ふと気付いたら、蔵がすごくきれいになっていて。ああ、うちの蔵、変わった! と強く思いました」。
この台詞に蔵元としての敬之さんの大きな手ごたえを感じる。そして蔵人としては、もう浮いた存在ではないでしょうね、きっと。






【住所】加西市三口町1048
【電話番号】0790-48-2111
【アクセス】北条鉄道播磨下里駅から徒歩24分
※敷地内に直営店&飲食店『ふく蔵』あり、蔵見学は要予約。
http://www.fukunishiki.co.jp
フォローして最新情報をチェック!