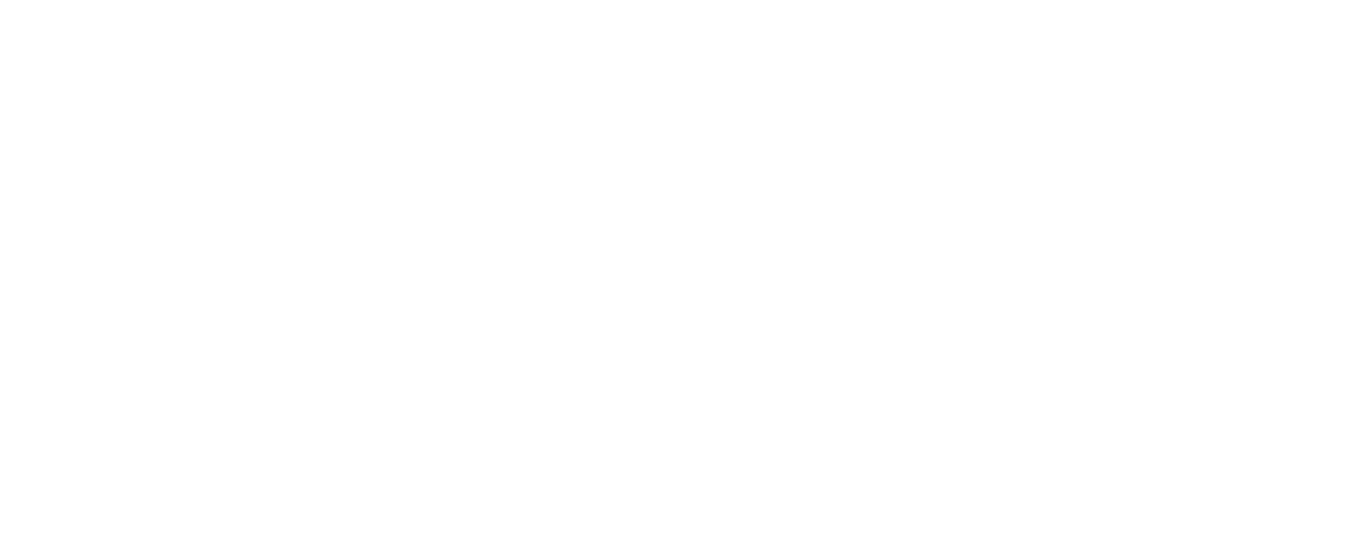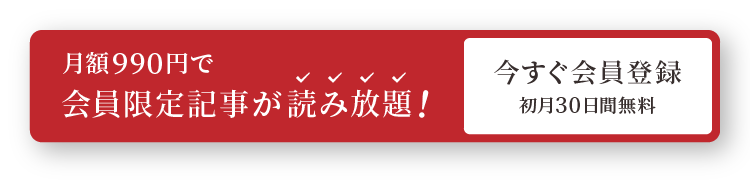1989年 滋賀県東近江市生まれ
2011年 同志社大学経済学部卒業
(株)ミツカンホールディングスに入社
2015年 生家である『喜多酒造』に入社
2018年 「蔵元の娘と楽しむ日本酒入門」出版
2020年 蔵が創業200周年を迎える

後継者、女性蔵人だからできること
女性が一人で。なんと、けなげな。
麹室で黙々と作業を続ける喜多麻優子さんの姿を見た時の印象だ。むろん、麻優子さんは立派な大人なのだが、白いTシャツ姿で白い麹に触れている姿は、その手先が優しく丁寧な動きを延々と続けていることもあって、胸打たれるものがあった。
酒の味わいの要となる麹室での仕事。それを能登杜氏の四家 裕(しいけ ゆたか)さんから任されるようになって、今期で3造り目。
「味わいの複雑さとたおやかさの基となるものですから、麹に求めるものは奥が深いんです。それを私にやらせてもいいと思ってくださった。そのことが本当に嬉しかったです」。
次期蔵元であると共に、一人の蔵人として杜氏の下で働くようになって5年が過ぎた。
「蔵に入った頃は、他の男性たちと同じように仕事をしようとしたけれど、でも、どうしてもできない力仕事もありました」。
さて、どうするか。麻優子さんが努めたのは筋トレではなく、蔵内の道具や仕事環境の見直しだった。荷台に滑車を付ける。2階にあった酛場(もとば)を1階へ移動させる、などなど。
「私でも力仕事ができるような工夫をすることで、パワーがあるなしに関係なく誰もが働きやすい環境が作れると気が付いたんです」。
蔵元としての行動を取る時に、蔵人の視線も持てるのは、酒造りに従事したがゆえ。冬の間は、他の蔵人たちと食事も宿舎も同じ場所で過ごす。八代目蔵元である父の良道さんは「自分の意志とはいえ、そこまでやるとは」と、一途な後継者の気概を汲む。
杜氏との絆が照らす10年先
麻優子さんに幼い頃の記憶として残っているのは、優しい蔵人たちが集う賑やかな様子。
「天保さんと父とが、ああしよう、こうしようとお酒造りの話をしている姿は、子ども心にも楽しそうに見えました」。
天保正一さん。その人こそ、約半世紀にわたって、この蔵の酒を造り続けた能登流の杜氏。いわば「喜楽長」の伝統の味わいを守り続けてくれた人だ。酒造りの技に秀でていただけでなく、常に穏やかな人格者でもあった。
その温柔で優しい杜氏が蔵に入る時には、キリッとした緊張感に包まれる。
「蔵は、他とは違う、神聖な場所なのだということが伝わってきました」。
蔵を継ごうと思ったのは、中学生の時。
「おかしいですよね。まだお酒も飲めない年頃なのに。でも、神聖な場所は誰かが継いで守らないと、と思っていました」。
その後は、「マグロのようにグングン進んでいく」と自覚する性格から、経営者を目指し、同志社大学の経済学部に進学。卒業後は、醸造業界の企業に就職し、自ら営業部を志願した。26歳で『喜多酒造』に入社、その冬に蔵入り。当初は「女性らしい酒」を求める声もあり「ピンクの酒を造らないといけないのかな?」と考えたこともあったそうだ。……が。
「どうも、しっくりこなかったんです。うちには『喜楽長』という、ここでしか造れない味がある。私はそれが好きでした。ならば、回り道をしている時間はない。それよりは、真っ直ぐにすべきこと、やらねばならないことを目指したいと思いました」。
その「喜楽長」らしさとは何かといえば、一つには「たおやかな酒」であること。麹による深い味わいがなめらかに、柔らかに広がる。そして、心までもが優しくなるような酒。そんな酒を造るために、父が守り続けてくれていたのが蔵の環境だった。
「父は蔵を継いでほしいとは一度も言わなかったのですが、能登杜氏さんとの絆、原料米を作ってくださる農家さん達との一代では終わらない関係など、いろいろなことを整えてくれていました。だから、私は恵まれた環境からスタートできたのだと思います」。
父がこの人、と見込んだ四家杜氏と麻優子さんとのタッグは来期で6年目に入る。
「四家杜氏は大らかな方で、この蔵をどういう方向へ持っていくか、10年先まで見てくれています。なので、商品設計や醸造プランも共有しやすくて、有難いですね」。
その四家杜氏からの「麻優子さんは次期蔵元さんですが、蔵人としても大事な人」という言葉は、今までの奮闘あってこその勲章だ。





【住所】滋賀県東近江市池田町1129
【電話番号】0748-22-2505
【アクセス】近江鉄道八日市駅から車で15分, 近江鉄道バス湖国バス如来バス停下車徒歩 2分
https://kirakucho.com/
フォローして最新情報をチェック!