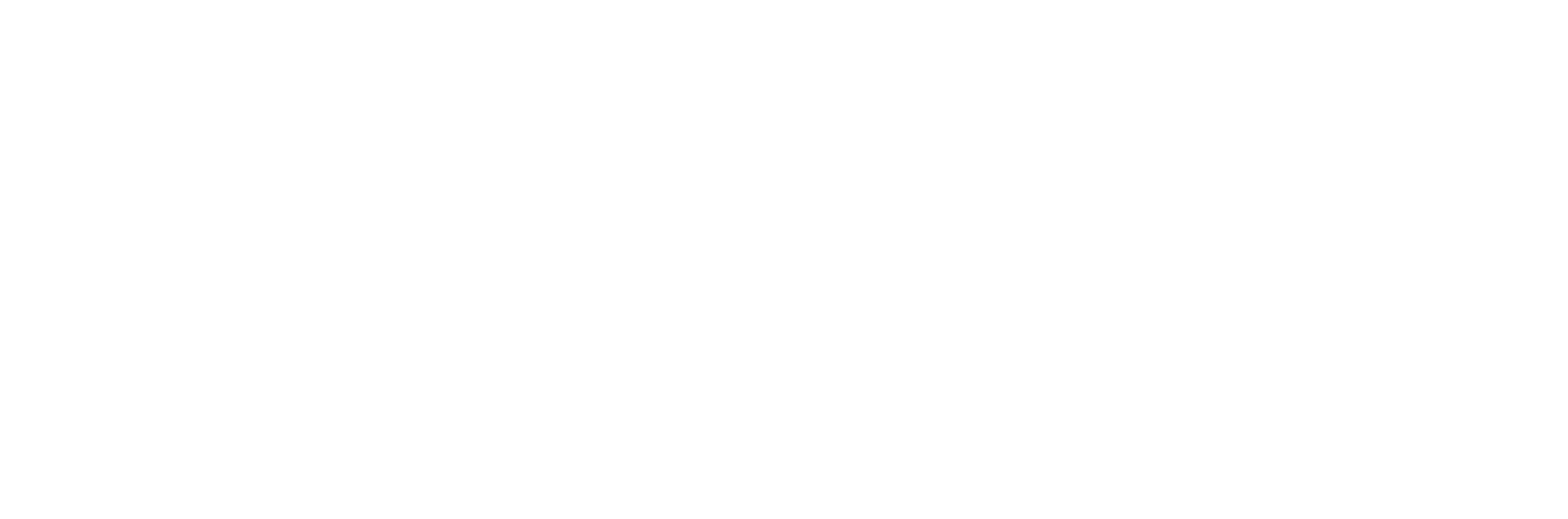専門店が提案! 漆(うるし)に親しむ第一歩、「金継ぎ」のススメ
欠けたり、割れたりと傷ついたうつわを、漆を使って修復する「金継ぎ」。エコ、リサイクルという点からも注目され、趣味として楽しむ人も増えています。料理人が、お客様に出すうつわの金継ぎをするとなれば、知っておきたいこともあります。京都の漆専門店『堤淺吉(つつみあさきち)漆店』に、漆のこと、金継ぎのことをお聞きしました。
漆器は“絶滅の危機”に瀕している!

和食料理人にとって欠かせないうつわといえば、漆の「お椀」。欧米で陶器が「チャイナ」と呼ばれるのに対して、漆が「ジャパン」と呼ばれるほど、日本での漆の文化は長く深い。なんと縄文遺跡からも漆器が発掘されているというから、その耐久性も驚くべきもの。しかし、いつもお世話になっているお椀の原料の漆について、ご存じだろうか?
漆は漆の木の樹液。樹齢10〜15年の成木に傷をつけて、そこから少しずつ垂れる樹液を掻いて集め、精製して使う。樹液は1本の漆の木から牛乳瓶1本分ほどしか採れない上、漆の木も、それを手で採取する漆搔き職人も激減した。日本で使われている大半を占める中国産の漆でさえ、需要が減少し、価格が高騰。将来的な安定供給にも一抹の不安がある。
料理の食材の将来について危機感を抱く料理人は多いが、漆と漆器もまた危機に瀕していることを意識している料理人は、多くはないだろう。
明治時代創業の『堤淺吉漆店』では、「このままだと日本の漆文化がなくなってしまう」と、漆の魅力を発信する「うるしのいっぽ」という広報活動、漆の木の植栽なども行っている。
本来なら、作り手である職人さんに漆や材料を供給する裏方の立場なのだが、取締役の森住健吾さんは「業界の外にも、漆のプレゼンテーターとして、素材の良さをアピールしたい」と言う。
 漆だけでなく、道具とその職人も貴重。棚上段、漆刷毛の素材は人毛。
漆だけでなく、道具とその職人も貴重。棚上段、漆刷毛の素材は人毛。
 ショールームには漆芸の素材、道具のほか、昔ながらの漆掻きの道具も展示している。
ショールームには漆芸の素材、道具のほか、昔ながらの漆掻きの道具も展示している。
続きを読むには
無料で30日間お試し※
- 会員限定記事1,000本以上、動画50本以上が見放題
- ブックマーク・コメント機能が使える
- 確かな知識と経験を持つ布陣が指南役
- 調理科学、食材、器など専門性の高い分野もカバー
決済情報のご登録が必要です。初回ご登録の方に限ります。無料期間後は¥990(税込)/月。いつでもキャンセルできます。
フォローして最新情報をチェック!