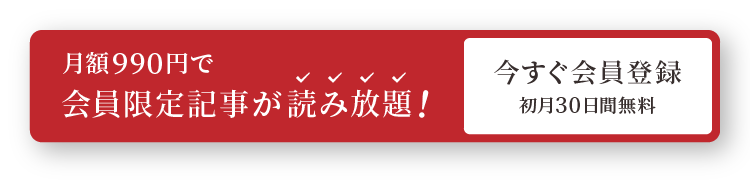【レシピ付き】東京・赤坂『津やま』其の三:沢煮椀
東京の日本料理は大正時代までは座敷料理が基本でした。しかし、昭和初期に関西割烹が進出し、カウンターで喰(く)い切り料理を展開。あっという間に和食界を席巻しました。赤坂『津やま』もその系譜を継ぐカウンター割烹。初代が修業した銀座の名店『わたき』のスタイルに倣い、“旨いもんや”の気軽さで人気を博してきました。豚角煮、エビフライといった家庭料理が品書きに並ぶ中、名物として名高いのは沢煮椀。『津やま』を象徴する一品です。
柏原光太郎(かしわばらこうたろう):1963年東京生まれ。慶應義塾大学を卒業後、株式会社文藝春秋に入社。『東京いい店うまい店』編集長、食のEC『文春マルシェ』立ち上げののち、独立。食の社交倶楽部『日本ガストロノミー協会』を設立し、会長。食べログフォロワー5万人以上。外食産業、地方創生関係者とのつながりも深い。著書に『ニッポン美食立国論』。
銀座の名店『わたき』直伝
ウドと三ツ葉の白と緑のコントラストが美しい。吸い地には豚の脂の旨みが溶け出ており、コクが深く、野菜は絶妙な歯ざわりだ。最後に白コショウの香りが追いかけてくる。
沢煮椀を『津やま』で初めていただいたのは、30年以上前のことだ。すっかりこの味の虜になった私は、他の割烹でも品書きに載っていると頼むようになった。だが、『津やま』の味を超えるものには出合えていない。
『津やま』の沢煮椀は、初代の鈴木正夫さんが修業先の『わたき』で習ったレシピを踏襲したもの。「『わたき』のおやじから、沢煮椀、豚の角煮、鯛茶さえ会得すれば、いつでも料理屋はできると言われてきました」と、正夫さんがよく話していたことを覚えている。それくらい、この沢煮椀はシンプルだが、味わい深い、心に残る一椀なのだ。
➡『津やま』の店ものがたりはコチラ。
 『津やま』の創業は1967年。「沢煮椀」は開店以来、この店の名物として半世紀以上愛されている。
『津やま』の創業は1967年。「沢煮椀」は開店以来、この店の名物として半世紀以上愛されている。
「沢煮椀」が名物になったワケ

沢煮椀とは、千切り野菜と豚の脂を使って作った汁物のこと。猟師が日持ちする塩漬けの豚肉を持って山に入り、具沢山の汁を作ったことが始まりという説もある。
魚介や豪華な食材を主役として用い、付加価値を高めた沢煮椀を見ることがあるが、『津やま』は昔ながらのシンプルな仕立てだ。野菜を食べるためのお椀というスタンスを創業以来、変わらず貫いているのだ。
忙しい都会人にとっては、お椀で野菜をたくさん摂れることはありがたい。豚脂の旨みとコショウの香りが絶妙で、居住まいを正して味わうお椀とは違った、ほっこりとした美味しさ。それこそが、『津やま』の沢煮椀が長く愛されてきた理由だろう。
二代目の鈴木弘政さんも、「沢煮椀と鯛茶がうちの二大名物です」と語り、誇りを持って作り続けている。『わたき』から初代、そして二代目へと、名物の味はしっかりと受け継がれている。
シンプルな、いぶし銀のレシピ
野菜は、通年、椎茸、筍、ウド、三ツ葉の4種。ゴボウやニンジンは合わないそうだ。先代の著書には、「白と緑の色合いを大切にしたいし、シャリシャリとした食感がほしいから」と書かれている。
逆に言えば、4種の野菜だけで旨み、香り、食感をベストの状態に持っていけるかが、この料理の生命線ということだ。野菜は細く、そして同じ大きさに切り揃える。「見た目も大事ですが、それ以上に食べた時の存在感を揃えたいと思っています」と、二代目の弘政さんは語る。
 1人前の沢煮椀に使う野菜は、この分量。手前左から時計回りにウド、三ツ葉、椎茸、下茹でした筍。野菜をたっぷり味わえる椀であることが分かる。
1人前の沢煮椀に使う野菜は、この分量。手前左から時計回りにウド、三ツ葉、椎茸、下茹でした筍。野菜をたっぷり味わえる椀であることが分かる。
味の決め手は、豚脂を少量のカツオ昆布だし・酒・薄口醤油に溶かし、野菜を加えて炒め煮すること。生から吸い地で煮ると、野菜のシャキッとした食感が失われてしまうからだ。この少量の煮汁を切って器に盛り、新たな吸い地をかけて仕上げる。このひと手間で、クリアな味わいとなり、品の良さが出るのである。
神は細部に宿るというが、こうした細かい仕事の積み重ねが沢煮椀を『津やま』の名物料理に押し上げているのだろう。私は初代の頃から食べ続けているが、今でも変わらぬ味の裏には、こんなに緻密な仕事があったことを今回、初めて知った。
続きを読むには
無料で30日間お試し※
- 会員限定記事1,000本以上、動画50本以上が見放題
- ブックマーク・コメント機能が使える
- 確かな知識と経験を持つ布陣が指南役
- 調理科学、食材、器など専門性の高い分野もカバー
決済情報のご登録が必要です。初回ご登録の方に限ります。無料期間後は¥990(税込)/月。いつでもキャンセルできます。
フォローして最新情報をチェック!