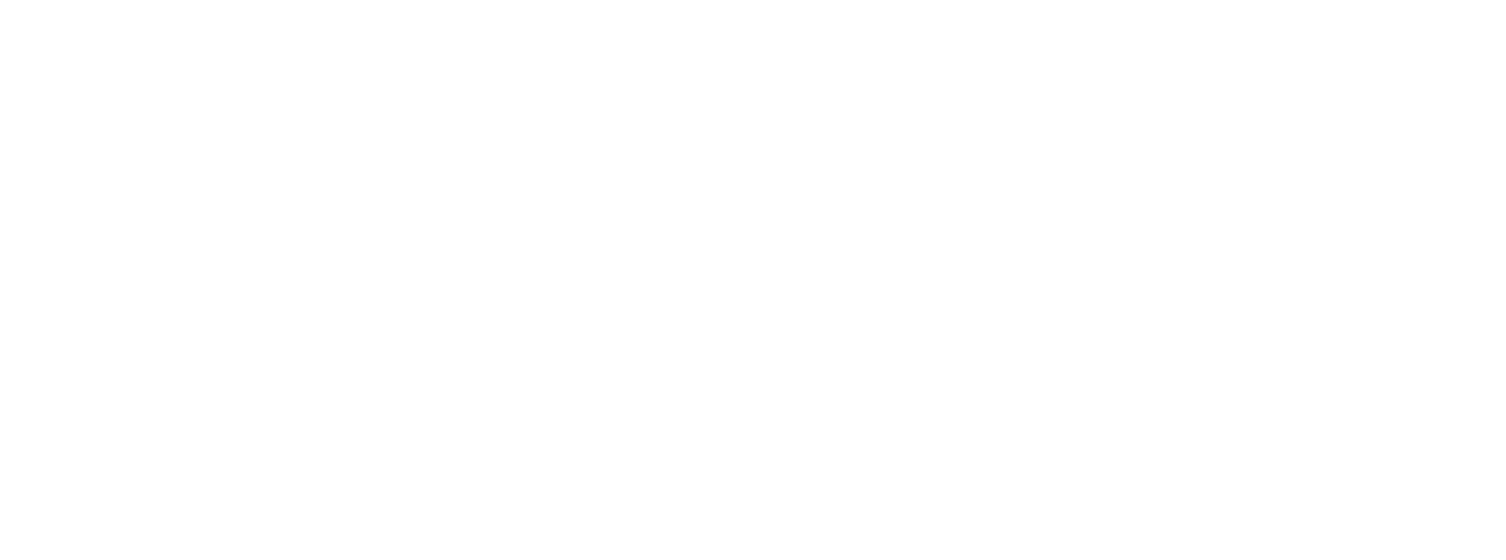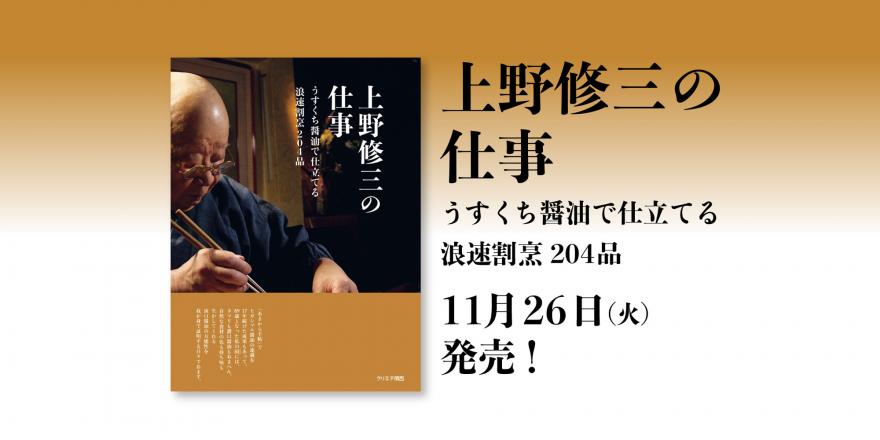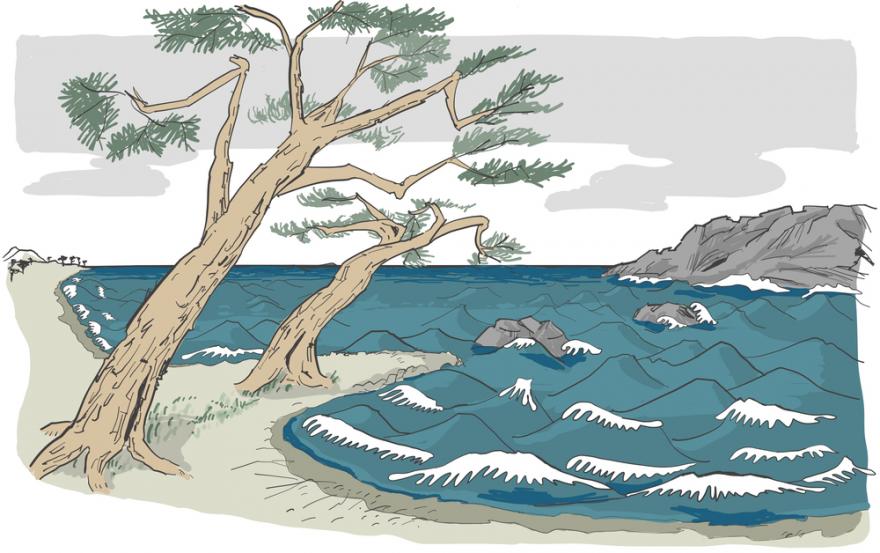【レシピ付き】大阪湾の代表魚・チヌ(黒鯛)を割烹の技で
大阪湾の古称は「茅渟(ちぬ)の海」。この湾が黒鯛の好漁場だったことから、大阪では黒鯛を「チヌ」と呼びますが…。「正真正銘のタイ科の魚やのに、真鯛とえらい差をつけられてしもて…。昔は独特な通好みの味わいが受けたけど、今は大阪でもそれほど食べられなくなりましたな」と上野修三さん。そこで今回は、チヌの真味を知ってほしい!と腕まくり。とりわけ旨いと言う“梅雨チヌ”を使った、割鮮(お造り)、焼物、煮物をご披露いただきました。上野さんの昔語りと共に、古き佳き割烹の技をご覧ください。
上野修三(うえのしゅうぞう):昭和10年、大阪・河内長野に生まれる。ミナミでの修業時代を経て、1965年、『㐂川(きがわ)』を創業。なにわ伝統野菜を発掘するなど、大阪らしい料理を追求し、浪速割烹のカタチをつくる。60歳で開店した『天神坂上野』は伝説の割烹として名を馳せた。現在は、なにわの食文化を綴る随筆家としても活躍。近著に「浪速割烹㐂川のおいしい野菜図鑑」春夏編・秋冬編(共に西日本出版社)がある。

黒鯛薄引き洗い——夏ミカン酢油と蓼(タデ)タレで妙味を愉しむ
「茅渟の海」には由来となるお話がおましてネ。神武天皇の御代、お兄様が矢傷を受けた手をこの内湾で洗ったことから「血沼の海」、転じて「茅渟の海」となったそうだすが…。料理屋としては、あまり気持ちのいいお話ではおまへんなぁ。それで私ゃ、勝手にこう解釈してますねん。古代の大阪湾は葦(あし)が群生する浅海。葦の総称が茅(かや)であることから、「茅が生えて水が渟(とど)まる」海ってネ。ちょっと強引ですかなぁ(笑)。
茅渟の海でよぉ獲れるから黒鯛をチヌと呼ぶというのは、有名な話だすな。昔は通好みの味として、人気のある魚やったんやけどネ。今じゃ真鯛に押されっぱなしや。
真鯛とチヌは旬が逆でしてネ。桜鯛と紅葉鯛に対して、チヌの旬は冬と初夏。2月頃は脂がのっていて、造りにすると旨い! 皮ぎしに少し臭みがあるから、お造りの場合は必ず皮は引いておくれやす。私流は、表面をしごくようにしてから薄塩をして1時間、スダチ果汁で軽く洗って水気を拭いたら、脱水シートでさらに数時間。しっかり締めてから造り身にするとよろしいな。
今の時季も“梅雨チヌ”として好まれますな。磯臭さもなく、持ち味が深いから、これもお造り、特に洗いにすると旨い。身にもわずかながらクセがあるので、これを洗い流すという寸法やね。シンプルに酢味噌や梅ダレで味わうのもオススメやけど、「大阪のチヌ、こんな美味やったんかいな!」と驚かせたくて、よぉやったんがこのカルパッチョ風だす。
和食やからドレッシングとは書きたくなくて、夏柑酢油としたけど、夏柑とは夏ミカンのこと。甘みがほどよく、酸味が強いので、白身とはよぉ合いますな。ここに裏漉ししたタデと昆布だしを合わせた蓼タレを重ねてネ。新玉ネギで香味を添えると、なかなかいけまっせ。
続きを読むには
無料で30日間お試し※
- 会員限定記事1,000本以上、動画50本以上が見放題
- ブックマーク・コメント機能が使える
- 確かな知識と経験を持つ布陣が指南役
- 調理科学、食材、器など専門性の高い分野もカバー
決済情報のご登録が必要です。初回ご登録の方に限ります。無料期間後は¥990(税込)/月。いつでもキャンセルできます。
フォローして最新情報をチェック!