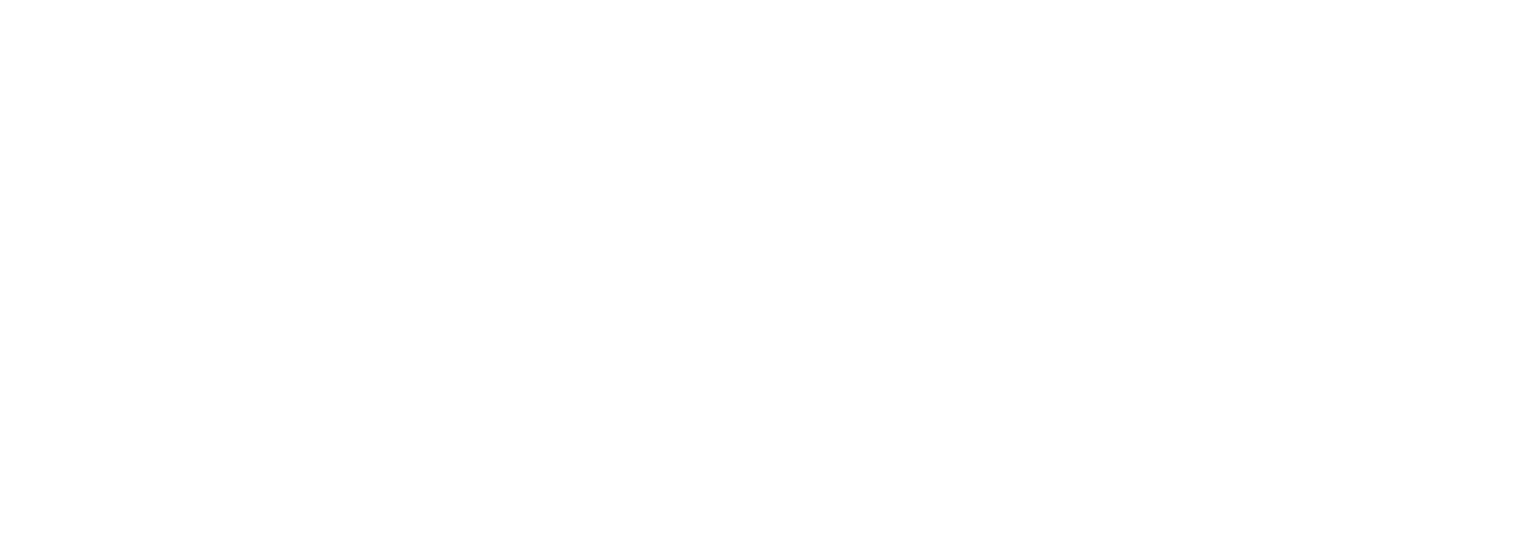名物「魚庭(なにわ)」も進化。大阪『弧柳(こりゅう)』、一軒家のもてなし
大阪・法善寺横丁の『浪速割烹 㐂川』での修業後、繁華街・北新地のビル1Fにて『弧柳』の看板を掲げた松尾慎太郎さん。それから13年もの間、大人な食べ手の胃袋と心を満たしてきました。そんな松尾さんがかねてより望んでいたのが、一軒家での営業。館・器・料理——自身のこだわりを結集した店が2021年11月に完成。その心尽くしのもてなしが、話題になっています。
ビルの1Fから、念願の一軒家へ
「弧を描いて撓(しな)る柳のように」——店名に込められたのは、店主・松尾慎太郎さんの“ありたい姿”。柳の根のようにしっかりとした基礎と、枝のように柔軟でしなやかな発想。両者を併せ持つ、大阪ならではの日本料理を発信したいという想いだ。北新地に路面店として創業して13年。2021年11月に新しい館を得て、松尾さんはその手腕を全開に披露している。
 松尾さんは調理師専門学校卒業後、大阪・法善寺横丁『浪速割烹 㐂川』の門を叩き、約13年の修業を重ね、2009年に『弧柳』を開店した。
松尾さんは調理師専門学校卒業後、大阪・法善寺横丁『浪速割烹 㐂川』の門を叩き、約13年の修業を重ね、2009年に『弧柳』を開店した。
「ずっと、一軒家で勝負したいと思っていたんです」と、松尾さんは言う。
6~7年探した末に縁あって見つけたのは、東横堀川沿いの物件。店内に入れば、カウンター内にはおくどさんが鎮座。川を眺められる大きな窓が切られ、網代天井はゆるやかにカーブを描く。
「私の料理に、数寄屋造りは似合わないと思って。和が7、モダンが3というイメージで作っていただきました」。
 一軒家の前には、柳の木が一本植わっている。2階には個室が2部屋。「住所の番地が3-3-3で。娘の誕生日や、前店のオープン日が3月3日だったこともあり、この物件に運命を感じました」と松尾さん。
一軒家の前には、柳の木が一本植わっている。2階には個室が2部屋。「住所の番地が3-3-3で。娘の誕生日や、前店のオープン日が3月3日だったこともあり、この物件に運命を感じました」と松尾さん。
 1Fのカウンターは12席。南アフリカのアサメラという木材を使用。椅子は、徳島の『宮崎椅子製作所』のもの。ゆったりと座り心地よく、軽いのが特徴だ。席の後ろには、床の間も。
1Fのカウンターは12席。南アフリカのアサメラという木材を使用。椅子は、徳島の『宮崎椅子製作所』のもの。ゆったりと座り心地よく、軽いのが特徴だ。席の後ろには、床の間も。
品書きも一新、こだわりの器名を記載
品書きにも変化が。ずらりと並ぶは、料理名に加え、それぞれに使われる器の名。
「器は料理の着物です。記載することで、興味を持っていただけたら嬉しいな、と思って」。
樂や永楽など骨董の中に、わずかに現代作家のものを差し込んでいる。器好きには、文字を眺めているだけでワクワクするラインナップだ。
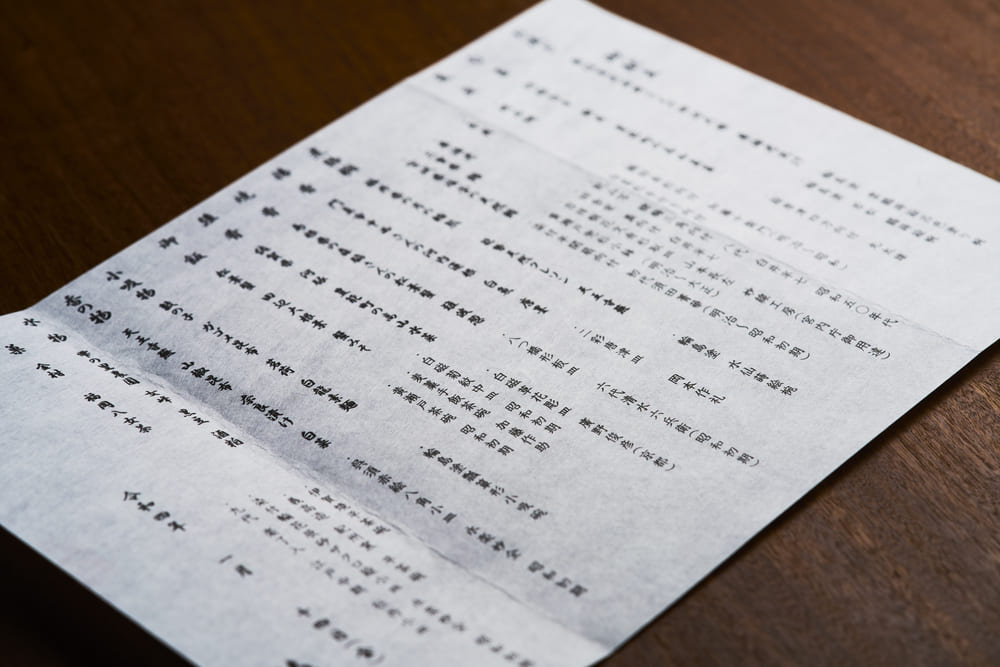 20代の頃からコツコツと器を集めていたという松尾さん。「前店は狭くて器を置く場所がなく、使えていなかったものがたくさんあるのですが」、今回の店では、地下にスペースを作り、思う存分、好きなものを使う。
20代の頃からコツコツと器を集めていたという松尾さん。「前店は狭くて器を置く場所がなく、使えていなかったものがたくさんあるのですが」、今回の店では、地下にスペースを作り、思う存分、好きなものを使う。
中には、1つの料理名に対して2つの器名が記されているものがある。
「カウンターに並ぶ器をすべて同じもので揃えるのも美しいのですが…。骨董を購入する際は、どうしても5客や10客という単位になり、全席分揃えるのはかなり時間がかかってしまいます」。
そこで松尾さんが考えたのは、料理1品に対して2種の器を使い、交互に出していくという手法。
「自分に供された器と隣の人のものが異なると、器に注目するきっかけになるんです。カウンターの景色も華やかになりますしね」。
例えばこの日なら、強肴(しいざかな)の「河豚 豊能町の高山水菜」を盛ったのは京都の現代作家・廣野俊彦作の「白磁草花彫皿」と昭和初期に作られた「白磁菊紋中皿」。ご飯の「松葉蟹 田辺大根菜 蟹みそ」をよそうのは加藤作助作の「麦藁手飯茶碗」と昭和初期に作られた「黄瀬戸茶碗」。このような“仕掛け”をコースの中に何度か組み込み、その度に食べ手は心をつかまれる。
パワーアップした、魅せる「魚庭」
コースは1種のみで、全11~12品。その主役となるのが、お凌ぎ、旬菜に続いて登場する造りの盛合せ「魚庭」。「生魚を食す文化が醸成された大阪ならではの供し方を」と、魚ごとに添える調味料や仕立てを変え、5種をドラスティックに供す。前店から評判を博してきた『弧柳』の代名詞的存在だ。
その「魚庭」を移転後、パワーアップ。2月のこの日、登場したのは冬の景色。

まず、大きな煎茶盆に盛られてきたのは、明石鯛と平貝の2種。松、そして椿の蕾を飾り、上から氷餅を削って雪景色に。写真は2名分だが、明石鯛を盛っているのは加藤十衛門作の「織部舟形向付」と、「白菜形手付き向付」の2種、平貝も、八代・白井半七の「乾山写 槍梅三角向付」と「田舎家 蓋向付」の2種の器。煎茶盆の上には、鄙(ひな)の里の冬がしみじみと描かれ、食べ手の目を喜ばせつつ、「どちらの器にしようか」と選ぶ楽しみももたらす。
明石鯛は、当日に仕入れたものと、3日間熟成させて旨みと香りをアップさせたものの食べ比べ。「口に入れた時に、舌全体で旨みを享受でき、食感よく噛める厚さに」そぎ切りする。合わせるのは、兵庫・香住の海水に塩と昆布を足して煮詰めたもの。
「海水自体は塩分濃度が3%くらいですが、煮詰めて10%くらいに。醤油だと15~16%で濃度が高すぎるし、塩だけだと鯛の繊細な持ち味が生かせないような気がして」。
平貝は、一味唐辛子、ラー油、ゴマ油を混ぜた酢味噌「南蛮酢味噌」を和え、菜の花を添える。平貝はサイコロ状にすることで、パンチが利いた味噌、春の香り漂う菜の花にも負けない風味を感じさせる。
2種の造りを食べ進めるうちに次の造りをひき、調味料を添えて仕上げていく。5種同時に提供するのをやめ、順に切りたてを供するようになったのも新たな試みだ。劣化を防ぐだけでなく、眼前で素早く仕立てられる“割烹仕事”が、お客の高揚感を誘う。
 「魚庭」の明石鯛と平貝。他、ヒガシマルの醤油「龍野乃刻(たつののとき)」で30秒だけヅケにした車エビは、ウニと共に。三重県のサワラは焼き霜造りにし、四万十川の生海苔と醤油を合わせた海苔醤油で。宮城県塩釜の天然マグロは、卵黄の醤油漬けと共に。
「魚庭」の明石鯛と平貝。他、ヒガシマルの醤油「龍野乃刻(たつののとき)」で30秒だけヅケにした車エビは、ウニと共に。三重県のサワラは焼き霜造りにし、四万十川の生海苔と醤油を合わせた海苔醤油で。宮城県塩釜の天然マグロは、卵黄の醤油漬けと共に。
なにわの伝統野菜を随所に
修業先から受け継ぎ、今も大切にしているのが、なにわの伝統野菜や大阪産の野菜をコースの随所に使うこと。この日も品書きには「東住吉区西野さんの田辺大根」、「豊能町の高山真菜・高山水菜」、「天王寺蕪」、「門真(かどま)市中西さんの河内蓮根」、「難波葱」と、野菜と共に生産者の名が記されたものもある。
「なにわの伝統野菜は大阪独自の品目で、およそ100年以上前から府内で栽培されてきたもの。味や身質に特徴のあるものが多く、個性的であり、仕立てを選ぶ野菜とも言えます。もとは、『魚庭』の中でも積極的に使っていたのですが、それだと添え物の範疇を出なくて」。個性を生かした、強く印象を残す皿に仕立てる。
コースの幕開けに供すお凌ぎは、「東住吉区西野さんの田辺大根 車海老出汁」。
田辺大根に、エビのだし。大根の味を消すのでは…と思いきや、「田辺大根の風味がとても強いので、エビのだしで炊いても負けません。身質がしっかり詰まっていて、荷崩れしないのもいいですね」。上からエビの殻を粉砕したパウダーをかけるも、言葉通り、エビの旨みに負けない風味が鼻に抜け、甘みがじわっと広がる。インパクトある一品目だ。
 だしは、焼いたエビの頭をカツオ昆布だしで炊いたもの。田辺大根自体もエビのだしで炊く。白味噌、エビの殻を粉砕したパウダー、細く切ったちちゃとう、うぐいす菜を添える。椀は、輪島塗 水仙蒔絵椀。
だしは、焼いたエビの頭をカツオ昆布だしで炊いたもの。田辺大根自体もエビのだしで炊く。白味噌、エビの殻を粉砕したパウダー、細く切ったちちゃとう、うぐいす菜を添える。椀は、輪島塗 水仙蒔絵椀。
強肴のフグには高山水菜を合わせる。下から、フグの煮凝り、食感が心地良い高山水菜、焼いたフグの身を杉盛りにし、ブランデーで香りをつけた醤油をかける。
「水菜を一番下にすると、垂れた醤油の濃い味を含んで持ち味を損なってしまうので、中に挟みます」。
天には菊科のノコギリソウ、アマランサス、花穂紫蘇をのせ、フグの卵巣のへしこパウダーをかける。まるでフランス料理の一品のような、モダンな姿に。食感や風味が複雑に絡んだ一品となる。
 器には、京都の現代作家・廣野俊彦作の「白磁草花彫皿」。
器には、京都の現代作家・廣野俊彦作の「白磁草花彫皿」。
地元食材を使う、高級魚を提供するということに終始しない一段上をいく料理の創造性。新たな発見をもたらす柔軟な器遣い。五感で楽しめる、館の心地。
割烹のライブ感に、ラグジュアリーさを掛け合わせて——。“大阪らしさ”を非日常の日本料理として表現する新しいもてなしの世界は、柳のように、根を張り、しなやかに深化していく。
 入口から店内へと続くアプローチは、足音が心地良く響く石畳。「己の来た道を表現したくて」と、松尾さんの修業先『浪速割烹 㐂川』がある法善寺横丁の石畳をイメージした。大阪の能勢(のせ)黒御影石が使われている。同じ石の蹲(つくばい)も置かれ、しっとりとした空気が流れる。
入口から店内へと続くアプローチは、足音が心地良く響く石畳。「己の来た道を表現したくて」と、松尾さんの修業先『浪速割烹 㐂川』がある法善寺横丁の石畳をイメージした。大阪の能勢(のせ)黒御影石が使われている。同じ石の蹲(つくばい)も置かれ、しっとりとした空気が流れる。
【住所】大阪市中央区内淡路町3-3-3
【電話番号】050-3172-3474
【営業時間】12:00~(土曜、祝日のみ)、18:00・21:00一斉スタート
【定休日】日曜、平日不定休あり
【お料理】コース33000円。※サービス料込。
フォローして最新情報をチェック!