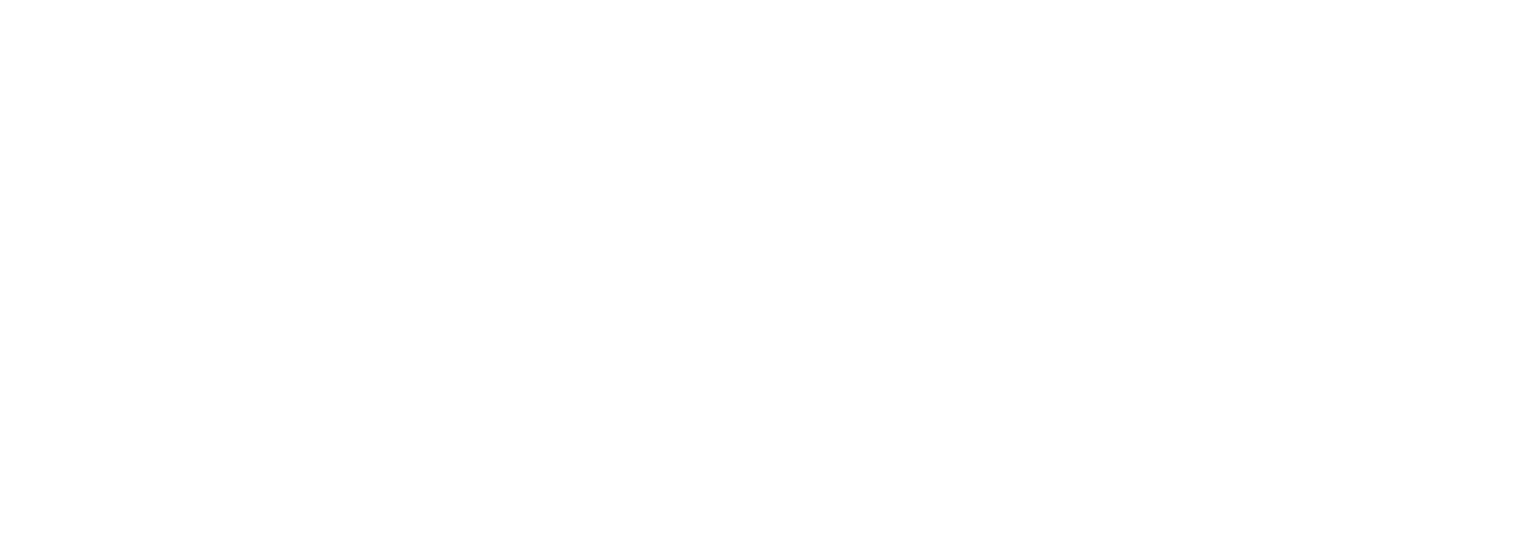能登・輪島『海辺の杣径』料理長・北崎 裕さんが作る、ここでしか味わえない“交換不可能”な料理
能登半島の北西に位置する輪島市門前町鹿磯(かいそ)。2024年元日の能登半島地震の影響で海底が4メートルも隆起し、多くの家屋が倒壊して風景が一変するほど甚大な被害を受けたこの地に、2024年9月、『海辺の杣径(そまみち)』はオープンしました。塗師・赤木明登(あきと)さんと料理人・北崎 裕(ゆたか)さんのタッグで2023年夏に開業した日本料理オーベルジュ『茶寮 杣径』が、地震によって建物が大きく損壊し、半年足らずで営業継続が困難に。そこから車で20分ほどの海辺に仮店舗として生まれたのが『海辺の杣径』です。「ここで何をどう料理するのか」——その問いと向き合いながら、『杣径』で料理を続ける北崎さんにお話をうかがいました。
美術史から懐石へ、料理を通して日本を知る
『杣径』の料理長・北崎 裕さんのキャリアは、料理人としてはかなり異色である。大学では美術史を専攻し、室町・安土桃山時代の美術や茶道に関心を持ったことが料理の世界への入口だった。
「美術を通して日本を知るより、料理を学ぶ方が裾野が広いと思ったんです。懐石や茶事に興味を持ったのが最初で、それまで料理に興味もなく、まったくの素人でした」。
料理学校にも通わず、知識もないまま、大学卒業と共に京都下鴨の『京懐石 吉泉』の門を叩いた。最初は「大卒が来る所じゃない」と言われたが、「門構えが立派だったから」という理由で面接を受けたその店で、5年間の修業を積んだ。
 北崎さんは1972年、石川県小松市生まれ。「国際基督教大学」卒業後、京都下鴨『京懐石 吉泉』で修業。石川県金沢市のホテルの日本料理部門や割烹などで料理長を経て、2009年に『六味一滴』をオープン。2014年より新潟県『里山十帖』で料理を担当し、総料理長も務めた。2023年に石川県輪島市門前町内保に開業した日本料理オーベルジュ『茶寮 杣径』、2024年に震災の影響で門前町鹿磯に移転した『海辺の杣径』で料理長を務める。
北崎さんは1972年、石川県小松市生まれ。「国際基督教大学」卒業後、京都下鴨『京懐石 吉泉』で修業。石川県金沢市のホテルの日本料理部門や割烹などで料理長を経て、2009年に『六味一滴』をオープン。2014年より新潟県『里山十帖』で料理を担当し、総料理長も務めた。2023年に石川県輪島市門前町内保に開業した日本料理オーベルジュ『茶寮 杣径』、2024年に震災の影響で門前町鹿磯に移転した『海辺の杣径』で料理長を務める。
「料理を極めることが目的ではなく、日本文化を知りたくてこの世界に入った。だから修業の厳しさも受け入れられたんです。そこに身を置くこと自体が学びだったし、意味がありました。それに、30年近く経った今も料理を続けているのは、やっぱり料理の世界が面白いと感じているからだと思います」と当時を振り返る北崎さん。
京都・金沢・新潟、そして能登へ導かれて
京都での修業の後、北崎さんは金沢へ移って割烹やホテルの日本料理店などに勤め、2009年に独立し金沢市片町で『六味一滴』という小さな店を開いた。
「本当は山の中の静かな環境でお店をやりたかったんですが、最初から人里離れた場所で開業する自信がなかったので街中から始めたんです。一般的に日本料理は魚が中心になりますが、僕は野菜料理に魅力を感じていました。だったら産地に近い方がいいと思い、田舎で料理をしたいと考えるようになりました」。
石川県小松市の砂丘地帯で育った北崎さんにとって、植物との接点はほとんどなく、料理を通じて植物や野菜に関心が湧いてきたという。知りたいことがあるから動く、北崎さんの歩む道は、いつも知的探究心から始まっている。
 輪島市門前町鹿磯の静かな海辺に佇む『海辺の杣径』。
輪島市門前町鹿磯の静かな海辺に佇む『海辺の杣径』。
「六味一滴」を5年営んだ後、新潟県南魚沼市の『里山十帖』に移り総料理長を務めた。そろそろ山の中へ移転したいという気持ちとタイミングが合ったのだという。そして以前から面識があった塗師の赤木明登さんの誘いで、2023年7月オープンの輪島市門前町内保のオーベルジュ『茶寮 杣径』料理長を務め、能登半島地震後は門前町鹿磯の『海辺の杣径』で腕を振るう。
 『海辺の杣径』の店内。建築家の中村好文さんが震災発生後すぐに駆けつけ、建物の間取りは変えずに、修繕と耐震補強を施したレストランへのリノベーションが進められた。
『海辺の杣径』の店内。建築家の中村好文さんが震災発生後すぐに駆けつけ、建物の間取りは変えずに、修繕と耐震補強を施したレストランへのリノベーションが進められた。
「よく食材の目利きと言いますが、僕は自然が生み出したものを“こっちが良くて、こっちが悪い”という選別ができない。できる人はやったらいいと思うんですが、僕にはそんな能力がないので、今いる環境で、目の前にあるものを使うスタイルをずっと続けています。
その代わり『この人が作っているものを使いたい』というのはあります。人と人の信頼関係でお付き合いができる人のものを使いたい。そして、信頼する人から出てくるものは基本的に選別することはせず、例えば苦いとか甘いとか、固いとか柔らかいという個性があっても、それをどうにかして美味しく食べられるようにするのが料理人なんじゃないかと思っています」。
 小茄子、グリーントマト、オクラ、金時草、インゲン、万願寺、ホオズキ、枝豆は、いずれも輪島周辺の農家で育った夏野菜。手前のオレンジ色の花は藪萱草(ヤブカンゾウ)。農家さんから直接購入したり直売所などを利用。地元産の野菜の味を消さない調味料、料理方法を選んで提供する。
小茄子、グリーントマト、オクラ、金時草、インゲン、万願寺、ホオズキ、枝豆は、いずれも輪島周辺の農家で育った夏野菜。手前のオレンジ色の花は藪萱草(ヤブカンゾウ)。農家さんから直接購入したり直売所などを利用。地元産の野菜の味を消さない調味料、料理方法を選んで提供する。
北崎さんが金沢で営んでいた『六味一滴』の店名は、「三徳六味」という曹洞宗の開祖・道元禅師が説いた精進料理を作る際の姿勢と味付けの心得からきている。「三徳六味」の「三徳」は「軽軟(軽くて柔らかい)」「浄潔(清潔である)」「妙法(作法やしきたりに反しない)」という料理を作る上での心構え、「六味」は甘味・酸味・塩味・苦味・辛味に素材本来の味を引き出す「淡」を加えた6つの味を指す。
「道元禅師は座禅や読経だけが禅ではなく、料理を作ることも禅であると言っています。三徳六味も、そのままでは食べにくいものも、調理することで食べやすくできるということ。苦いなら、こういう料理にしようとか、調理法を工夫する。こんな食材が欲しいから他所から取り寄せよう、という選択はない。目の前にある素材を、どうやったら美味しく食べられるかを考えています」。

都市では見えないものが、田舎では見えてくる。それは素材の力だけでなく、土地の歴史や人の営みも含めた風景そのものだ。
「僕があちこち旅をしてきて、いいなと思った場所は、必ず古代から人が暮らしてきた痕跡がある場所なんです。縄文時代の遺跡があったり、古い神社があったり。そういう場所に惹かれてしまう」。
『海辺の杣径』がある門前町鹿磯は古くは北前船の船員、その後は外国航路の船乗りが多く暮らしていた町で、店の裏手の高台には船運海産の守護神を祀る神社がある。また曹洞宗の大本山『總持寺祖院』のお膝元で、北前船の船主集落で天領でもあった黒島地区に隣接し、歴史・文化が色濃く残る地だ。北崎さんが導かれるようにこの地にやって来て、料理を続けているのも必然のように感じられる。
『茶寮 杣径』開業と地震——そして仮店舗での再出発
『茶寮 杣径』は美しき能登の風景と食文化、輪島の工藝のこれからを考え実践するために創り出された空間で、塗師・赤木明登さんの器を使い、ゆったりとした宿泊と料理の時間を提供するオーベルジュとしてオープンした。
杣径とは森の中の小径(こみち)を意味し、赤木さんの書斎兼ゲストハウスだった山あいの古民家を建築家の中村好文さんがリノベーション。漆塗りのバスタブなど唯一無二の空間作りも話題を呼んだが、2024年元日、能登半島地震で3棟ある建物のうち1棟が全壊、2棟が半壊するという大きな被害を受け休業を余儀なくされた。
 被災前の『茶寮 杣径』のカウンター席と寝室。(画像提供:杣径)
被災前の『茶寮 杣径』のカウンター席と寝室。(画像提供:杣径)
「寝室は2部屋ありましたが、ほぼ1日1組。日本食レストランは基本的に宿泊客用で、カウンター8席のみ、空席があれば食事だけのお客さまも受け入れていました。こんな田舎にどうして?と思うぐらい来店していただいていました。
2023年の営業が終了し、来年また頑張ろう、新年また会いましょうと言って別れた翌日に巨大地震が発生しました。普段、仕事があるときは単身赴任で輪島に住んでいますが、休みには家族がいる金沢へ帰るため、地震発生時は金沢にいました。金沢でも揺れがすごくて、能登は大変なことになっているだろうと思い、翌日すぐに輪島まで車を走らせました」。
 被災前の『茶寮 杣径』の本棚と外観。(画像提供:杣径)
被災前の『茶寮 杣径』の本棚と外観。(画像提供:杣径)
「道はめちゃくちゃでした。普通なら通らない道を通り、何とか辿り着きましたが、1月なので暗くなるのも早く、翌日に活動することにしました。赤木さんも県外にいて不在だったので、写真を撮って報告しました」と北崎さん。
水も電気もないため、金沢へ必要な物を取りに戻り、改めて出直すことにした。その後は門前に数日滞在して店の片付けや町の人たちの炊き出しを行い、また金沢へ補給に帰るということを繰り返した。そうこうしているうちに店舗を貸してくださると声をかけていただき、金沢で『杣径』を期間限定で営業することになった。
「お店のスペースを提供してくださったのは、以前から赤木さんと交流があった主計町(かずえまち)の『金沢 紋』のオーナーさんでした。当初2〜3月いっぱいの予定でしたが、5月まで延長営業することになりました。応援したいと来てくださった方、輪島まで行きたいと思いながら行けなかった方が、金沢で『杣径』の料理が食べられるならと大勢来てくださりました」。
その後、門前町鹿磯に仮店舗を構える準備が始まった。現在の『海辺の杣径』で、地震の前から赤木さんが出版社の編集室として使っていた建物だ。
当初『茶寮 杣径』は再建までに1〜2年かかると予測されていたが、2024年9月に奥能登豪雨も発生し、能登では大工不足で建物の修繕・再建も思うようにできない状況になった。幸いにも『海辺の杣径』は、建物の修復・リノベーションに着手したのが早く、秋からの開店に間に合った。
『茶寮 杣径』の建物は、1年半も手付かずで放置したことで修復がさらに難しくなり、今は解体の方向で考えているという。その代わり『海辺の杣径』の向かいにある建物を改装し、新たに宿とレストランを再開する計画があるそうだ。
 3種の貝料理。手前の白い皿はタコの洗いとアカニシ貝、ズッキーニの浅漬け、ワインで煮たビーツに花穂ジソを添えて。仕上げの味付けは梅干しのみ。
3種の貝料理。手前の白い皿はタコの洗いとアカニシ貝、ズッキーニの浅漬け、ワインで煮たビーツに花穂ジソを添えて。仕上げの味付けは梅干しのみ。
以前のディナー主体の『茶寮 杣径』とは異なり、『海辺の杣径』では地元の人も気軽に立ち寄れる定食スタイルのランチを提供している。
「漁師さんや地域のおじいちゃん、おばあちゃんにも来て欲しい。肩肘張らずに食べられる、もう一つの杣径をつくりたかった。しかし、仮店舗の食堂だからといってカツ丼などはやらない。味付け、素材選び、一つひとつのアイテムに施す仕事など、自分が料理で大事にしていることは変えず、これまでやってきた料理を組み合わせて、利用しやすいランチを提供しています」。
料理に宿る思想、レシピに残る文化と歴史
『杣径』の料理の中心にあるのは、地元の野菜や野草。味を消さず、素材を活かすために調味料の使い方も独特だ。
「例えば醤油ひとつとっても、甘さや香りが素材を覆ってしまうので、白醤油を使うことが多いです。砂糖やみりんを使わないのもそのため。素材の味がちゃんと伝わる料理がしたいんです」。
 茹でたサザエに、焼き茄子の芳ばしさが調味料代わり。水分を飛ばして旨みを凝縮させた焼き茄子は少量の甘露醤油で仕上げ、インゲンは茹でて白醤油と少量のスパイスをからめている。
茹でたサザエに、焼き茄子の芳ばしさが調味料代わり。水分を飛ばして旨みを凝縮させた焼き茄子は少量の甘露醤油で仕上げ、インゲンは茹でて白醤油と少量のスパイスをからめている。
塩もマグネシウムが多いと野菜や山菜のえぐみが際立ってしまうので、ミネラルのバランスで能登産の天然塩を用途に応じて使い分ける。器は赤木さんの器をはじめ、赤木さんと長年交流して来た工芸作家たちの作品を用いている。
 バイ貝は酒といしる、太キュウリは塩揉みしてヨーグルトで和えている。ヨーグルトのほのかな酸味とやわらかな油脂分で太胡瓜の淡い味をアシスト。瑞々しい枝豆の食感もアクセントに。
バイ貝は酒といしる、太キュウリは塩揉みしてヨーグルトで和えている。ヨーグルトのほのかな酸味とやわらかな油脂分で太胡瓜の淡い味をアシスト。瑞々しい枝豆の食感もアクセントに。
「ここに『杣径』があり、僕が料理をして、赤木さんの器があって、お客さんが来てくれる。全部そろわないと成り立たない。この海、この山、この空間、全部ひっくるめての『杣径』。だから、ここでやる意味があるんです。
赤木さんは『工藝は交換不可能なもの』と言います。漆器の木地を作る人も、この人でなければというのがあって、その方がいなくなったから別の人にチェンジという代わりがきかない。町並みもそうで、地震の後に建物を壊して更地にし、建て直してしまうと、能登らしさがなくなってしまう。どれも置き換えられないものなんです」。
 蓮根餅と柔らかく煮た鮑に、葛と蓮根の搾り汁でとろみを付けたあん、藪萱草を添えて。器はしっくりと手に馴染む赤木明登の地久椀(ちきゅうわん)。
蓮根餅と柔らかく煮た鮑に、葛と蓮根の搾り汁でとろみを付けたあん、藪萱草を添えて。器はしっくりと手に馴染む赤木明登の地久椀(ちきゅうわん)。
「それは料理も同じ。この場所で、どんな料理を、誰と食べるか。これも交換不可能なこと。この場所であることが大事なんですよ。
大昔の人たちが、この場所で何を食べていたのか。砂糖や甘味がない時代も、ないから貧しいわけではない。縄文時代の遺跡からクジラを食べていた痕跡が出てきたり、木の実をいろいろ集めて、とんでもない工程を経て食べられるようにしていたり。昔の人が、季節ごとに何を楽しみにして食べていたのかに興味があります」。
 能登半島の外浦は、12月末から岩海苔をはじめとするノリ類に始まり、アカモク、カジメ、ワカメ、モズクなど多種多様な海藻が現れる、日本中見渡しても珍しい地域である。またキノコや山菜の宝庫でもあるが、地震の影響で山も海も地形が変化し以前より収穫が難しくなっている。(画像提供:杣径)
能登半島の外浦は、12月末から岩海苔をはじめとするノリ類に始まり、アカモク、カジメ、ワカメ、モズクなど多種多様な海藻が現れる、日本中見渡しても珍しい地域である。またキノコや山菜の宝庫でもあるが、地震の影響で山も海も地形が変化し以前より収穫が難しくなっている。(画像提供:杣径)
「奥能登の人たちは、海藻でも山菜でもキノコでも、何でも食べます。季節ごとの食材、食べ方を教えてくれた、サザエや海藻を採っている隣家の漁師さんの話も、全部が貴重な記録です。昔の人たちが選んだ土地や暮らしの跡が、神社や祭、食材の扱い方に残っていて、昔の人たちがどんなものを食べ、どう工夫していたかという痕跡を見ることができる。料理は資料の残らない暮らしの歴史、その土地の記憶を受け継ぐものだと感じています」。
そう語る北崎さんの手で、今日も一皿ひと皿が丁寧に作られていく。それはただの食事ではなく、人と土地の記憶を受け渡す、静かで力強い営みだ。
▼能登・輪島『海辺の杣径』北崎 裕さんに聞く【5問5答】はコチラ
【住所】石川県輪島市門前町鹿磯1-17
【電話番号】090-4605-3737
【営業時間】ランチ:木・金・土・日曜11:30〜15:00(14:30LO)
ディナー:水〜日曜の完全予約制
【定休日】月・火曜
【お料理】ランチ定食2000円、ディナーコース19800円
※団体・貸切・ランチコース5500円〜の予約可
【公式HP】https://somamichi.jp
【Instagram】https://www.instagram.com/_somamichi
【Facebook】https://www.facebook.com/profile.php?id=100085571135404
フォローして最新情報をチェック!