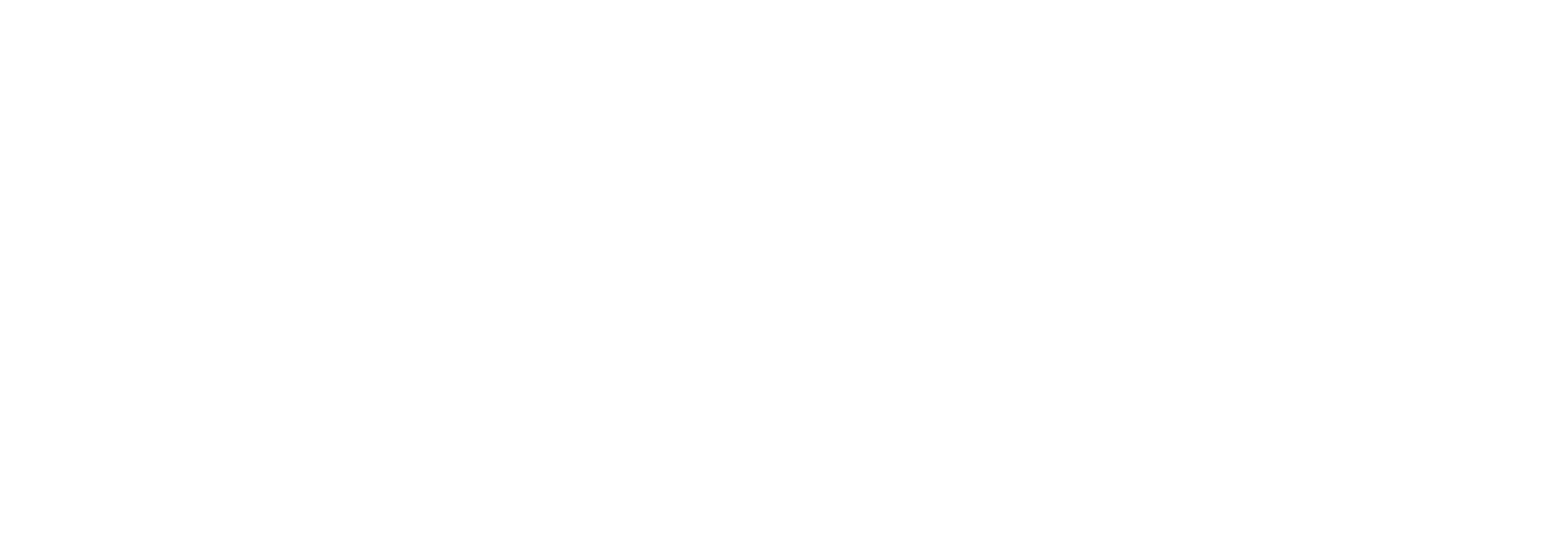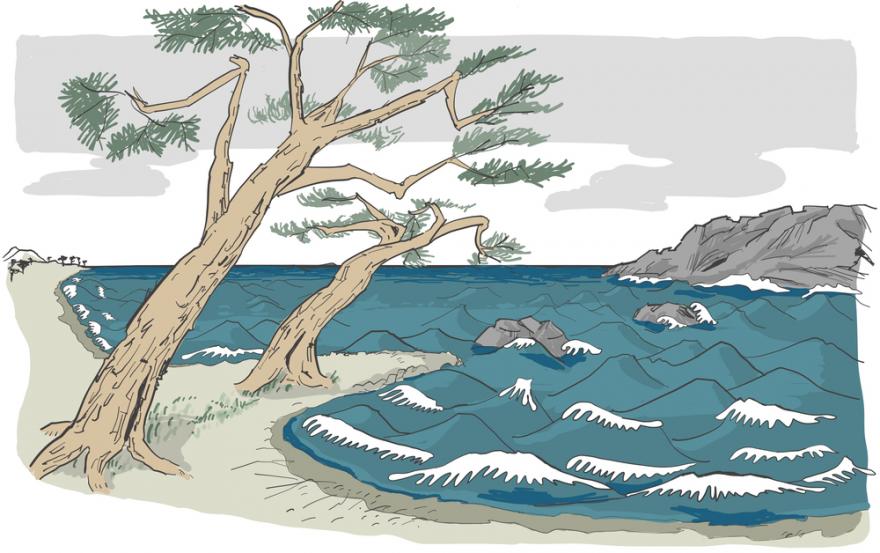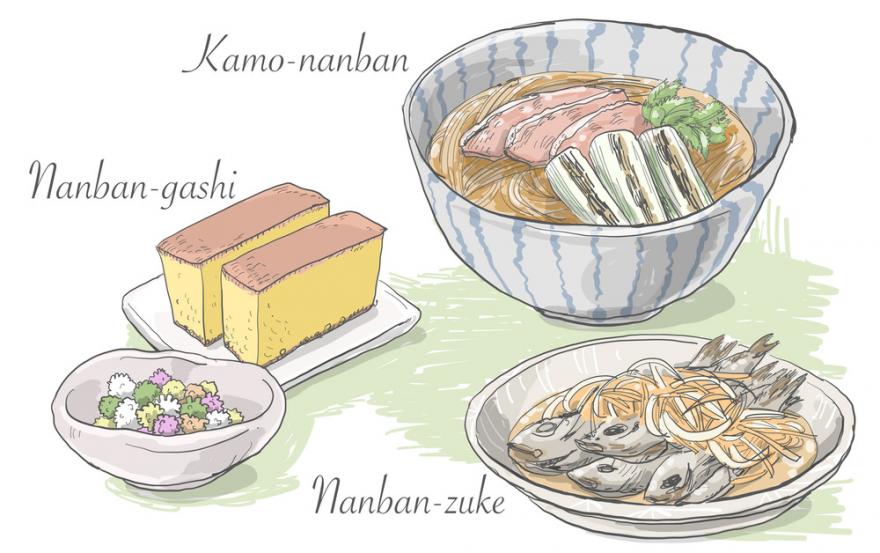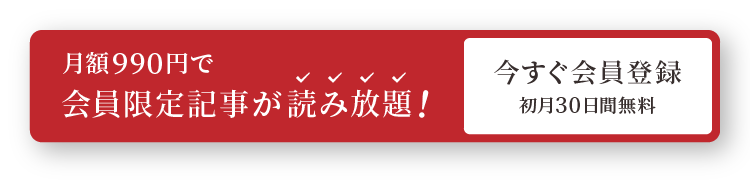「生ずし(きずし)」とは?
塩をあてた鯖や鰺を酢に漬けて締めた料理を、関西では「生ずし(きずし)」と呼びます。馴染みがない人にとっては、酢飯を用いない「すし」に驚いた、なんてこともあるでしょう。なぜ飯と切り離されて、今の姿に行きついたか。今回は、すしの語源と歴史、すしの分類と系統、生ずしに繋がっていくはなしをかいつまんで紹介し、推察していきます。

「すし」の変遷
生ずしの話の前に、「すし」について触れておきましょう。すしが指すのは、大きく分けて2つ。
①主に魚に、塩とデンプン(米飯など)を混ぜて、重しをかけて長く漬けることで乳酸発酵させた「なれずし」
②飯に酢を加えて早く酸味をつけ、主に魚介と合わせた「早ずし」
酸っぱさの出どころが、乳酸か食酢かの違いはありますが、どちらもすしです。
すしと呼ぶ理由は、酸っぱいから(酸し)、圧す石(おすいし)に由来するなど諸説あります。
①の「なれずし」は、日本においては奈良時代以前、全国から都に集まる貢納物を記した中に出てくる「鮓」と「鮨」の表記が、古い例としてあげられます。一般的になれずしは、魚を長期貯蔵する手段であり、どろどろに溶けた主に米飯の漬け床をぬぐって、魚だけを食べるものです。熟成により、魚は酸っぱく、独特のにおいがあり、身も皮も骨も軟らかくなっています。日本においては比較的早くから、単なる保存食というよりは、味や食べるタイミングを意識して仕込んで、ある種のごちそうの役割も担っていたようです。
なれずしの工程や時期、圧して置く時間などを工夫して酸味と熟成が浅い魚に仕立て、米飯を一緒に食べるすしを、「生なれずし(生なれ/生なり)」と言います。熟れた魚+米飯のスタイルの出現は、日本独自のすし文化が拓かれる大きな一歩でした。発酵を促進するために麹や酒、酢などを加えたものや、野菜と糀のなれずしも生まれ、種類を増やしていきました。
江戸期になると、すしに画期的な出来事が起こります。発酵を待たず、米飯に酢を加えて手軽に味を付けた「早ずし」が誕生したのです。魚も頭など硬い部分を除き、切り身にしたり酢をあてたりと、短時間で食べられる処理を施すように。押しずしや棒ずし、江戸の町で生まれた握りずしなど、現在イメージされるすしがこのタイプです。
生ずしは、“酸っぱい魚料理”?
今回のテーマ「生ずし」ということばは、一般的には生なれずしから発生したもので、先述の通り、速成のために酢を使う早ずしを、生ずしとも呼ぶようになったと考えられています。
江戸時代の料理書『料理網目調味抄』(1730年)には、「生ずし」の説明として、鮒(ふな)に塩をして一晩置き、米を詰めて漬けたものと書かれています。生なれずしにあたりますが、一晩寝かせるだけなので漬かり具合は相当浅そうです。
『素人庖丁』二編(1805年)には、「まながつおの生ずし」の項に、身に塩を当てて重しをかけたものを、造り身にして他の薬味などと取り合わせるとあります。料理史の専門家によると、これは酢で締める記述が省略されたと考えられるようですが、塩締めだけであっても、酢飯を使わない、締めた魚肉単体を生ずしと呼んでいる例と言えます。
こうなると「すし」を定義づける要件は、飯の有無よりも酸っぱいこと、くらいには考えられるかもしれません。
関西の「生ずし」はどこからきた?
現在「生ずし」といえば、関西においては鯖・鰆・鰺などに塩をあて、酢で締めた酢の物を指します。鯖の生ずしは、一般的には「しめ鯖」と呼ばれるもので、酢飯は使いません。先の、塩締めか酢締めにしたまながつおを生ずしと呼ぶ流れをくむのでしょうが、関西の生ずしについて描写されたものを調べると、いろんな記述や説に行き当たります。
昭和の大阪ことばについて記した辞典をひいてみると、今と同じ意味の「生ずし」の項目がありそうなものですが、早ずしを意味する記述しかありません。一方、例えば上方落語にでてくる生ずしは、魚の酢締めを表しているようです。市井の人達のなかでは、“飯なし鮨”である生ずしが広まっていったのでしょうか。
分かったのは、「生ずしとはしめ鯖のこと」とはっきり記されるようになったのは案外最近のこと、ということです。
ひとつ興味深い説があります。昭和の頃、なますやすしのブームが起こり、関西ではその流行りにのって、しめ鯖に生ずしの呼び名をあてるのが普及した、というものです。生ずしは単に酸っぱい魚料理、というだけでなく、手早くて新鮮な印象があり、しかもみんなが好きな「すし」を想起させるので、いかにも関西好みなエピソードだな、と感じます。
▼香薫 サゴシの生ずし(きずし)のレシピはコチラ
フォローして最新情報をチェック!