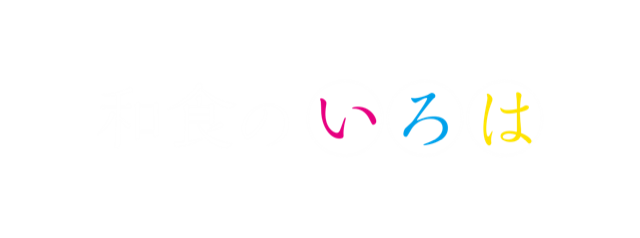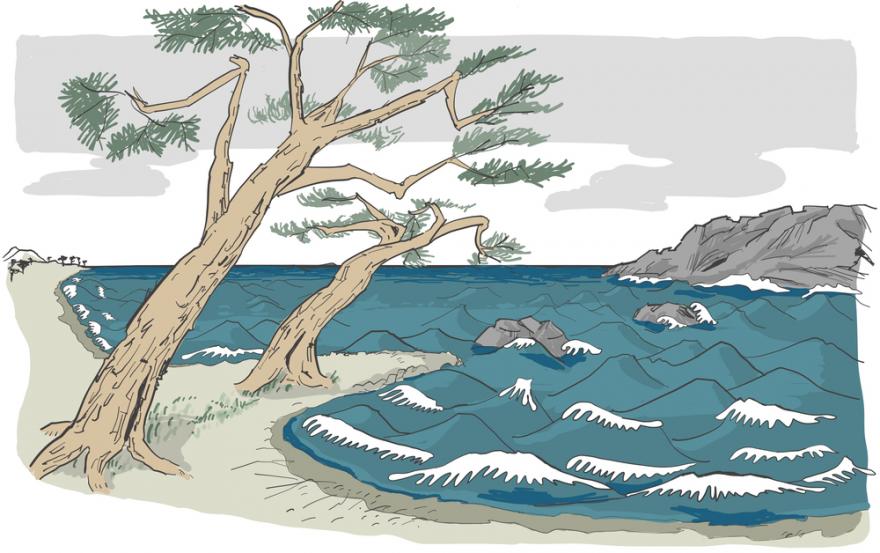日本酒造りにおける「酵母」の役割と種類とは
日本酒造りに欠かせない微生物・酵母。使う種類によって、酒の香りや味わいが異なるといいます。今回は、その役割や種類について解説。知っていると、日本酒選びの手引きとなるかもしれません。
※「あまから手帖」2020年2月号より転載
日本酒造りにおける「酵母」の役割とは?
酵母とは、発酵には欠かせない微生物。酒の醸造には、麹菌、乳酸菌など、さまざまな微生物が入り乱れてのドラマがあるが、アルコールの生成に直接関わるのが酵母なのだ。
ワインは果汁に酵母が付着し、ブドウの糖分を栄養源にして発酵、アルコールを生成するのだから単純明快。ところが日本酒の場合は、酵母が蒸し米に付いてもそのまま酒にはならない麹菌の力を借りて蒸し米を糖化させ、その糖を栄養に清酒酵母は発酵、アルコールを生成する。これが“世界一複雑な醸造”といわれる所以だ。
ちなみに清酒酵母の実態である微生物は、百億個が集まっても1グラムというちっちゃいもの。むろん肉眼では見えないその実態が確認されたのは、1660年に顕微鏡が発明されて後のことだが、そこで見えた酵母の容姿は「色白で丸顔」とのこと。なんだか、カワユイ。

「酵母」は何種類ある?
酵母は自然界に普通に生息している微生物なので、その種類はかぎりなく無数にある。昔の酒造りでは、清酒蔵に棲みついた野生の酵母を「蔵付き酵母」として使っていた。
その清酒酵母が人の管理下に置かれるようになったのは、明治末期のこと。近代国家を建設していく過程では、酒税も重要な国の収入源。それを得るためには、酒を腐らせずに確実に醸造する必要があったため、明治政府は「日本醸造協会」の前身・国立醸造試験所を設立。強い発酵力があり、その上でよい香りや味を醸し出すことができる優良な酵母を純粋分離して各地の酒蔵に頒布し、醸造の安全性を高めた。これが、現在でも多数の蔵で使用されている「きょうかい酵母」だ。

代表的な「酵母」の種類
「きょうかい酵母」の中から関西の酒蔵が好んで使用する頻度の高い酵母をご紹介。とはいえ、これがすべての清酒酵母ではなく、「地方の特性を生かした差別化を」と静岡・山形・長野・広島…と県単位で開発したものも。近年は、「もっと蔵の個性を出そう」と、蔵付き酵母で酒造りに挑む造り手も増えてきている。
6号——香りも酸も柔らか、穏やかな旨みを生む
現在使用されているきょうかい酵母の中では最古のもので、昭和5年に秋田「新政」の醪から分離。低温(10〜12℃)でも強い発酵力を維持することから、東北地方で特に支持され使用された。
「新政」8代目蔵元である佐藤祐輔さんが6号で醸す酒が大ブームを巻き起こしたことから、新たに注目を浴びた酵母でもある。端麗な酒質に向くとされるが、関西では意外やボディ感のある「京の春」の『向井酒造』がメインで使用。「華やかな香りは出ないけど、酸も控えめで、米や麹の風味が素直に出せる。うちの酒は低精白で、麹もしっかり造っていて酵母に任せたような酒造り。きっちり旨みをまとめてくれるけれど、旨すぎることなく仕上がるんですよ」とは、杜氏の向井久仁子さん。
7号——多彩な酸を生かし「山廃・生酛に」がトレンド
昭和21年、長野「真澄」の蔵で分離された酵母。発酵力が旺盛で香りも控えめ、穏やかな味わいを生む。食中酒造りに向くとされ、最も多くの酒蔵で使用されている。
7号のみ、と決めているのは兵庫「竹泉」の田治米博貴さん。「口から唾液が出るようなナチュラルな酸を生む。料理を美味しくする食中酒を醸すには7号!」とキッパリ。
同じくオール7号使用の奈良「風の森」山本嘉彦さんも「酒米や精米歩合の違いでライチ、サイダー、白ブドウ、メロンといろいろな香りが生まれます。コハク酸、リンゴ酸、乳酸などいろいろな有機酸があることで酒の輪郭が保たれる」と信頼を置く。
ここ数年の傾向としては、兵庫「播州一献」、滋賀「大治郎」など山廃・生酛向きと考える蔵が増えていること。大阪「秋鹿」の奥 裕明さん曰く「吟醸酵母として発売されたので香りも出るが、過剰な香りではないところが山廃や生酛にいい」。生酛に注力する滋賀「北島」の北島輝人さんは「シャープな酸味で、より締まった味わいになる」と7号にシフト中。滋賀「七本鎗」の冨田泰伸さんは「寝かせると腰の据わった酒になる」と長期熟成酒に使用している。
9号——香りとキレを生むオーセンティックな酵母
昭和28年に熊本「香露(こうろ)」の蔵で分離。1980年代の吟醸酒ブームの立役者となった酵母。旺盛な発酵力を持ち、リンゴのような上品な果実香を生成する。
オール9号使用の奈良「みむろ杉」の今西将之さん曰く「低温発酵にすることでメロンやラムネのような香りも得られます」。滋賀「大治郎」も「スタンダードな酵母で、派手になりすぎず、上品な香り」と9号をメインに。香り以外に、キレに注目している蔵も多い。滋賀「萩乃露」の福井 毅さんは「うちの仕込み水は超軟水なので、発酵後半は(発酵が進みにくくなり)キレない。9号を使用することでキレのある酒を目指しました」と話す。奈良の「篠峯」を醸す堺 哲也さんも「吟醸造りの定番。低温発酵性があるので、純米酒でもしっかりキレ味が出る」からと「櫛羅(くじら)」ブランドに使用。兵庫「播州一献」では、飲み飽きしないキレのある食中酒を狙って9号にシフト中。滋賀「七本鎗」の冨田さんは、「オーセンティックな酒に向く。シンプルに酒を造りたい時に使います。米の味が一番分かりやすいと思うので」という意見。
10号——白ワイン系の風味が出せる
昭和27年頃、茨城「副将軍」の蔵で分離。高い吟醸香を出す酵母だが、アルコール耐性(発酵中の醪にアルコールが生成されてきた時に酵母がどれだけ死滅しないで活動を続けられるかの目安)が低いため、取り扱いは難しいという意見も。
「関西では、うち以外は使ってないでしょ?(笑)」とは、滋賀「笑四季(えみしき)」の竹島充修(あつのり)さん。一般的(教科書的)には低酸性も一つの特徴とされるが、竹島さんは「きれいな甘みとほどよい酸のある」酒を醸せる酵母と捉えて定番商品に使用。「ブドウのような風味が出せるので、“白ワインみたいな”と言われるような酒を造るなら、この酵母だと僕は思います」。
11号——キレのいい辛口向き
昭和50年に日本醸造協会により分離。きょうかい7号の変異株で「アルコール耐性酵母」とも呼ばれ、醪の中で長く死滅せずに長期発酵に向く。
辛口でキレの良い酒を狙って用いられる酵母で、大阪「秋鹿」の奥さんは「辛口でも味がしっかり出る」と20年ほど前から使用。奈良「篠峯」の堺さんは今年が初チャレンジ。「辛口に向く酵母なので、さっぱりとした味を目指して使います。“美味しすぎない”ように、軽やかな味わいに仕上がるといいなと思って」とのこと。
14号——果実のような爽やかな香り
平成8年に金沢国税局鑑定官室で分離したため、「金沢酵母」とも呼ばれる。能登杜氏たちが“おひざ元の酵母”として赴任先の蔵で使用することが多い。
低温でも強い発酵力を保つため吟醸酒に多く使われ、マスカットのような爽やかな果実香が出るのも一つの特徴。滋賀「大治郎」の『畑酒造』では、19歳と共に醸す「19歳の酒」に使用。「香り華やか、かつ爽やかな風味なので、初めて日本酒を飲む人に好まれるだろうと思って」と、蔵元杜氏の畑さん。また、新酒として売り出す酒を醸す時にも「フレッシュ感を出すために使う」のだそう。滋賀「七本鎗」の冨田さんは定番の純米吟醸に使用。「バランスが良くて、酢酸イソアミル系(※1)の穏やかな香りがある。低酸性といわれるけれど、それなりに酸も出ますよ」とのこと。
※1主に爽やかな柑橘系と評される香り。
18号——香り華やか、鑑評会好み
平成18年に作られ、正確には1801と表記される。酵母には、発酵中に醪の上部液面にまで泡が立つ“泡あり酵母”と、泡が液中で収まる“泡なし酵母”の2種類があり、泡なしの酵母の場合は01を付けて表記する(※2)。酸とアミノ酸の生成を抑える性質と、華やかで高い香りを発生させる力を持つ。
全国新酒鑑評会の金賞を狙うには不可欠とされ、実際、現在の金賞受賞酒の多くには、この酵母が使用されている。日本酒入門編の酒として評価される一方、「カプロン酸系(※3)」と呼ばれる熟した果実や花のような甘い香りを避ける層もいて、好みは分かれるところ。滋賀「萩乃露」の福井さん曰く「香り系の代表格。含み香もあり、味も柔らかくなるんですよ」。
※2:6号の泡なし酵母は601と表記する。
※3:主にメロンやリンゴのような香り。
▼「WA・TO・BI」では、日本酒のアテに作りたい「スピード酒肴レシピ」を随時更新。ぜひ、チェックしてみてください。
フォローして最新情報をチェック!