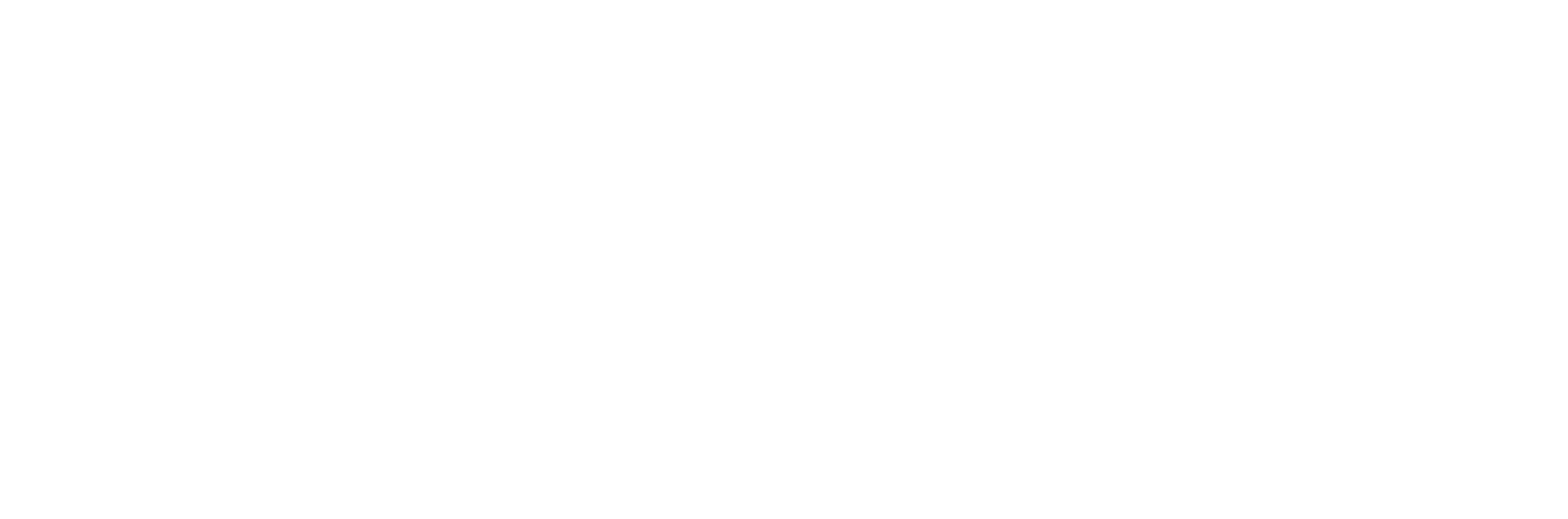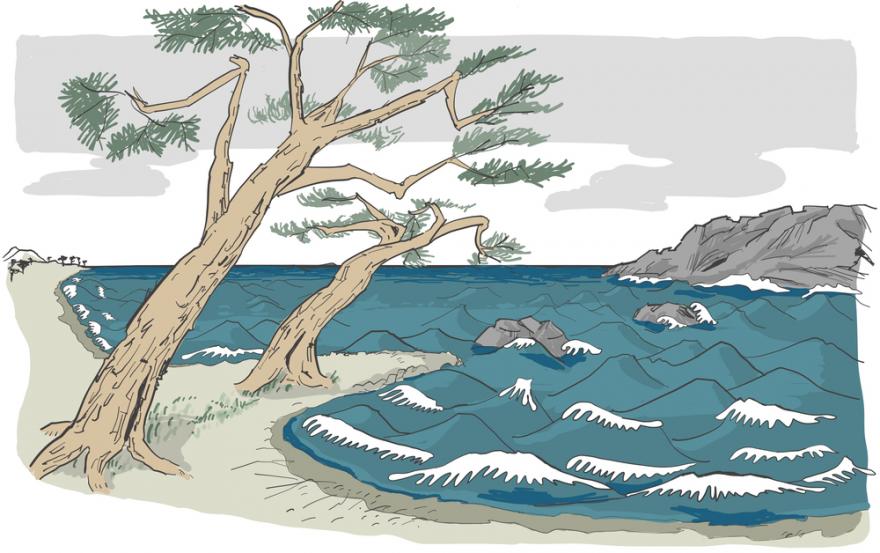うつわの作り手、窯元と会える「清水焼の郷まつり」の歩き方<10/21~23開催>
行楽シーズン、全国のやきものの産地で開催される「陶器まつり」。なかでも毎年、10月に開催されている「清水焼(きよみずやき)の郷まつり」は、今年から出店者を京都の作り手、お店に絞って開催。京焼・清水焼の多彩さを知り、個性的な作り手との接点が持てるイベントにリニューアルしました。10・11月に開催されるその他の陶器まつりについても紹介しますので、ぜひ、出かけてみてください。
「京都」に特化した陶器まつり。見どころは清水焼の多様性
清水焼団地協同組合が主催する「清水焼の郷まつり」は、40余年の歴史を持つ、京都府内最大の陶器まつりだ。当初は、在庫や市場に出せなかったB品を廉価で放出する「掘り出し物市」的な催事だったのが、ここ数年、若い出店者がSNSで発信するなどして、売り手、買い手の幅も広がり、マルシェやクラフトフェアのようなクリエイティブな彩りも生まれてきた。
(会場、売り場写真は2019年の開催時のもの)
 清水焼団地は、昭和になってやきもの関連業者が清水五条から山科に場所を移して生まれた、やきものの郷。
清水焼団地は、昭和になってやきもの関連業者が清水五条から山科に場所を移して生まれた、やきものの郷。
残念ながら2020・2021年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となったが、今年、出店者を「京都の作り手」に特化して、3年ぶりに開催されることになった。
メインの通りにはテントがずらりと並ぶ。そのテント内に展示されるうつわは、全て京焼・清水焼となる。
京焼・清水焼と聞いて、割烹など日本料理店向け、お土産、茶道具など、ちょっとコンサバな和風のうつわというイメージがないだろうか? 実際は、京都では料理人や茶人、そして一般の市場の求めに応じながら、時代に合わせてさまざなうつわが作られてきた。トレンドに敏感で、あらゆるうつわを作る技がある。それが伝統だ。2022年の「清水焼の郷まつり」では、そんな本来の京焼・清水焼らしさである多様性をアピールしたい考えだ。
 左/大規模な陶器市。お出かけ前に「欲しいうつわリスト」を作っておくと迷わない。右/「格安お買い得品」をあさるばかりでないのが、今どきの陶器市。
左/大規模な陶器市。お出かけ前に「欲しいうつわリスト」を作っておくと迷わない。右/「格安お買い得品」をあさるばかりでないのが、今どきの陶器市。
続きを読むには
無料で30日間お試し※
- 会員限定記事1,000本以上、動画50本以上が見放題
- ブックマーク・コメント機能が使える
- 確かな知識と経験を持つ布陣が指南役
- 調理科学、食材、器など専門性の高い分野もカバー
決済情報のご登録が必要です。初回ご登録の方に限ります。無料期間後は¥990(税込)/月。いつでもキャンセルできます。
フォローして最新情報をチェック!