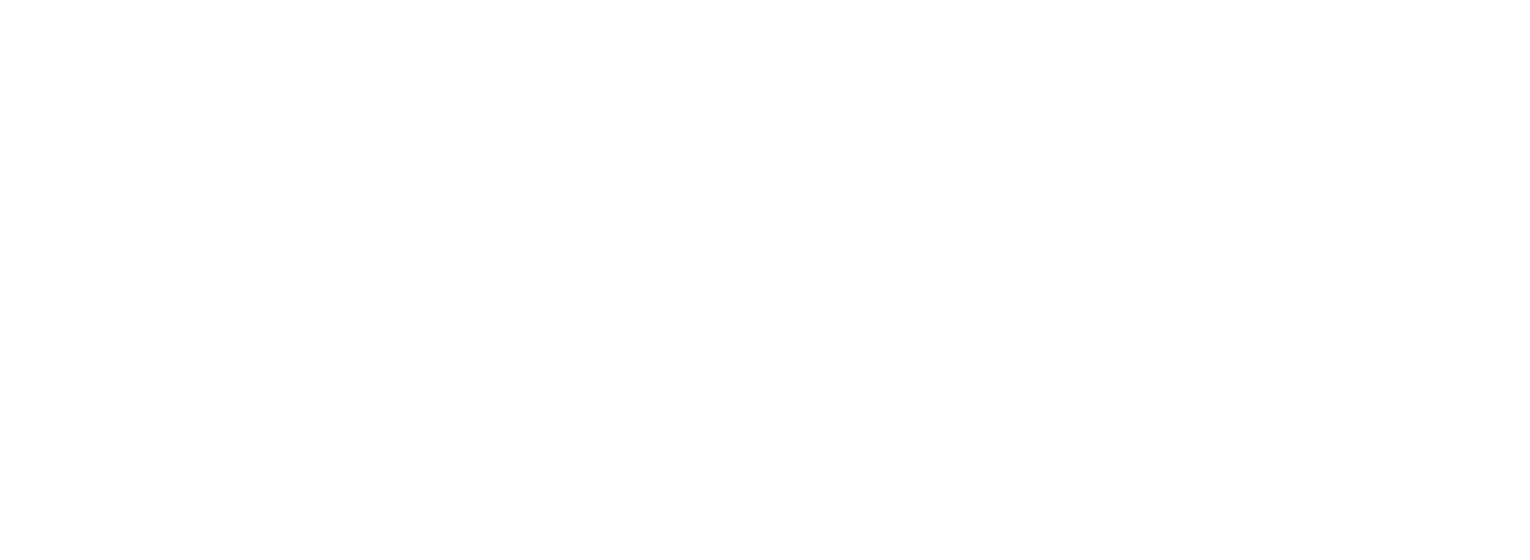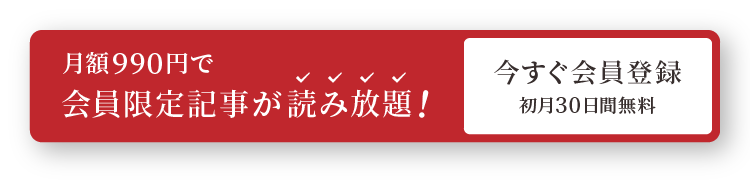真水と海水が混ざる良水に恵まれて
遊子地区の沿岸は波穏やかだが、沖には激しく潮流が渦巻いている。こうした条件はハマチや真鯛、真珠の養殖に適しており、山内家も50年前から養殖を生業としていた。
「最初はハマチ、20年前から真鯛に切り替えて。養殖真鯛の中から選りすぐりを、初代の名にちなんで歌吉鯛のブランドとしていました」と話すのは山内満子さん。
転機となったのは2016年、長男の歌吉さんと共に八幡浜市の廃校を活用したアワビの陸上養殖場を見学したこと。養殖場の片隅に緑色の藻のようなものが入った水槽があった。それがスジアオノリであることを知った山内さん親子は、水中をゆらゆらと漂う幻想的な美しさに魅入られた。その場には、たまたま高知大学のスジアオノリの研究者がいたことも幸運。スジアオノリの陸上養殖について教えてもらった。
「遊子では誰もやっていない、スジアオノリをやりたい」。跡取りの歌吉さんの言葉に、最初は難色を示していた父の平吉さん。だが、真鯛は浜値の乱高下により、出荷すればするほど赤字になることもあった。また稚魚から出荷まで3年かかり、1㎏の真鯛を育てるのに3㎏弱もの餌が必要なことも頭を悩ませていた。さらには気候変動により、水温が変化していたことも不安材料。そんな状況と歌吉さんの熱意に、平吉さんもようやく首を縦に振った。真鯛からスジアオノリへ。山内家は大きな決断をした。
山内さんらはまず、陸上養殖に必要な水を確保するために海から数mのところに井戸を掘った。すると湧き出てきたのは、ミネラル分が豊富な良水。水質調査をしたところ、2つの地層の下の地下水脈は、傾斜地から浸透した真水と海水が程よく混じり合い、スジアオノリの生育に適していることが分かった。地層が濾過の役割を果たし、海水に混じる小さなエビやカニも見られなかった。「これもウリになる!」。井戸海水は、満子さんと歌吉さんの背中を押してくれた。
清々しい風味は丁寧な手作業が生む
スジアオノリの養殖は、ラボで種苗(胞子)を取るところから始まる。一定の大きさに育ったところで屋外の養殖槽へ。スジアオノリは光合成によって生長するため、養殖槽は透明なものを探してきたという。愛媛県の柑橘は太陽光と海からの反射光、地面からの輻射熱の3つの太陽を浴びて育つことで糖度を増すと言われているが、スジアオノリもその恩恵を受けることができる。
こうした好条件を追い風に、試行錯誤の末に3年かけて独自の養殖法を確立した。その一つが、生長度合いを見極めながら、2、3度入れ替えを行うこと。その都度、スジアオノリをしっかりと洗い、養殖槽に発生する不純物を取り除くのも山内流。
「不純物というのは珪藻(けいそう:藻類)。排水が茶色になるほど、珪藻が混じっています」と満子さん。養殖槽の容量は1基が約1トン。小ロットだけに、1基ごとに細やかに管理できる。それを担うのは、故郷にUターンした次男の丈二さんだ。
四国では高知県四万十川や徳島県吉野川の天然スジアオノリがよく知られており、漁や天日干しをする情景は冬の風物詩となっている。天然と養殖。さてどちらを選ぶかと問われれば、何につけ天然の品が良いというイメージがある。だが、「自分たちのスジアオノリには、天然物にはない魅力がある」と確信した山内さん親子。
思い込みではない。理由の一つが、養殖槽で井戸海水を掛け流ししていること。赤潮や台風などの災害に左右されず、品質が保たれ、安定供給もできる。もう一つ、地層による濾過、丁寧な水洗いにより、スジアオノリは混じり気のない高い純度となる。しかもエビやカニも混ざらないことから、甲殻類アレルギーフリーを謳うこともできる。絹糸のように食感は滑らか、しかも綺麗であることから「きぬ青のり」と名付け、現在は家族総出で販路の拡大に取り組んでいる。
とはいえ「天然に比べると香りが弱いのではないか」という声があるのも事実。それが悩みの種でもある。
「きぬ青のり」は、加工前にはほとんど香りがないが、乾燥し、細胞が壊れることで強い香りが生まれてくるそうだ。実際に食してみると、主力の「手もみ」は、天然のスジアオノリのむせ返るような香りとは異なる、清々しく品のいい香り。「粉末」、「微粉末」は、その香りが一層強まる。
「この香りの秘密は、珪藻をしっかりと洗い流しているからだと考えています」と歌吉さん。繊細な料理の味を邪魔せず、多様な食材と合わせやすい。また天然物の収穫が冬から初春に限られるのに対して、陸上養殖では水温がほぼ一定の井戸海水により、一年中、新鮮なスジアオノリを約2週間で収穫できるのも強みだ。
「養殖に使った水は酸素を豊富に含んでいます。これを海に返すことで海の環境保全にも一役買っていると思っています」と胸を張る満子さん。さらに、新たに手作業で1本ずつ整えて乾燥させた商品も販売予定。こちらは板海苔のようなアレンジで、「料理の幅もきっと広がりますよ!」。“4つ目の太陽”を思わせるその笑顔と共に、「きぬ青のり」の清々しい香りが印象に残った。







【住所】愛媛県宇和島市遊子3127(事務所)
【電話番号】0895-62-0808
【営業時間】9:00~17:00
【定休日】土・日曜、祝日
【HP】https://www.utakichi.net/
※HPから購入可。業務用は要問合せ。
フォローして最新情報をチェック!