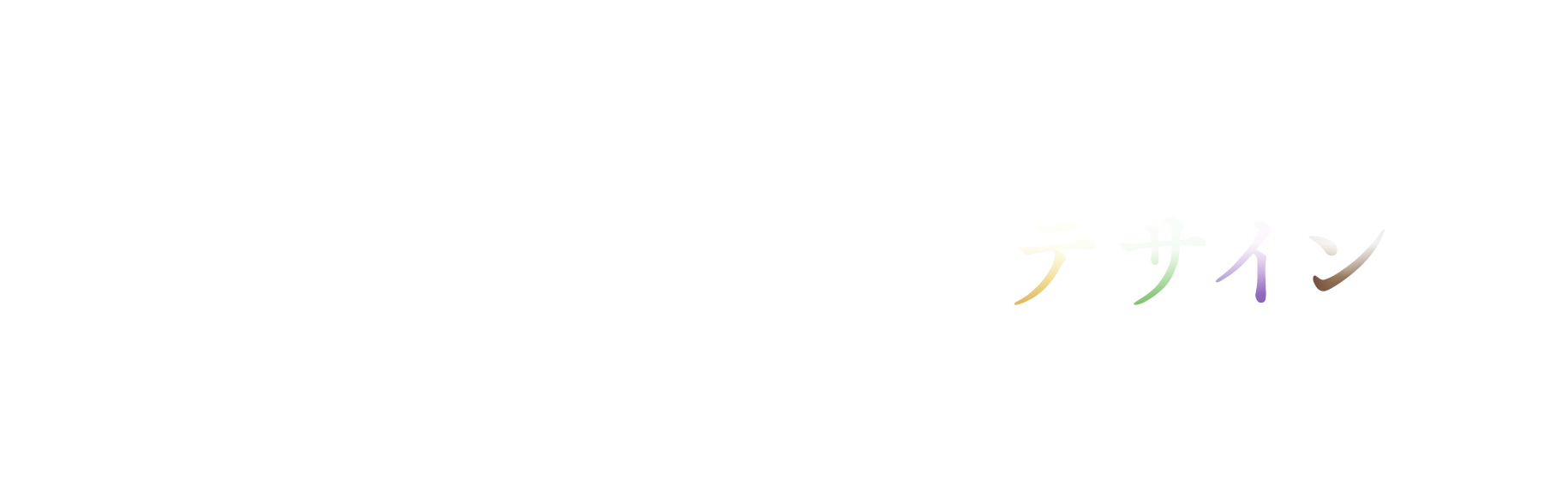【レシピ付き】『瓢亭』流、おせち料理 後編
「おせちの仕事は、店で出している料理とも、お弁当とも違う」と言う、京都きっての名料亭『瓢亭』の当代・髙橋義弘さん。12/5に公開した前編では、料理を日持ちさせる調理の工夫や華やかに見せる詰め方などのおせち仕事の心得と、毎年お重に入れるという「鶴小芋」のレシピを教えていただきました。今回は、クワイに細かな庖丁仕事を施し、松笠に見立てた「松笠慈姑(クワイ)」と、艶よく煮詰めた「キンカン蜜煮」のレシピをお教えいただきます。
髙橋義弘:創業450年を超える老舗料亭『瓢亭』の15代目当主。1974年、14代目髙橋英一氏の長男として京都に生まれる。東京の大学を卒業後、金沢の日本料理店『つる幸』で修業を積み、1999年帰洛。海外のシェフたちとのコラボレーションなど国内外を問わず、京都の懐石料理を伝える活動に尽力。2015年、15代目に就任し、2018年に東京店を出店。老舗の味を守りながら、時代に即した現代的な日本料理にも取り組み、新しい美味しさの提案を続けている。
松笠慈姑——揚げてから煮ることで、香ばしさを立たせます

個性的な姿のクワイは、初冬に収穫される、おせちに欠かせない野菜です。
芽が出る、という縁起ものなので芽を残して調理するのですが、長すぎると折れやすく盛りにくいので、適度な長さに切ります。「絵馬慈姑」の場合もそうですね。こちらはしっかり面積をとるように切って絵馬の形に整え、盛り付けの際のアクセントに使います。
 左のお重のキンカン蜜煮の上部、右のお重のぶどう豆の左と上部にあるのが、絵馬慈姑。
左のお重のキンカン蜜煮の上部、右のお重のぶどう豆の左と上部にあるのが、絵馬慈姑。
クワイの底部を切り落とし、芽に向かって側面の皮を六方に角が立つように剥いていきます。この時、底部側を少し細くするときれいに仕上がりますよ。そして、飾り切りをしていきます。
角を中心にやや下から上に角度をつけて切り込みを入れ、その下方からさらに角度をつけて庖丁を入れて切り取ります。1角ずつ空けて同じように切り込みを入れて一周し、2周目は1周目とはずらした場所に同じ要領で切り込みを入れて同様の作業を繰り返し、最後は底にも。切り込みが浅いと松笠の形に見えず、深いと割れやすいので注意します。

アク抜きをしてクチナシを加えて下茹でし、だしで煮上げるのが一般的ですが、ウチはこのまま揚げ煮にします。油で揚げることで色が付き、香ばしく、クワイの味も深まるからです。
こちらも「鶴小芋」と同じく、少し濃いめの煮汁で煮た後に一晩置き、翌日再度火を入れ、冷ましてから水分を切って盛り付けます。作り置きする場合は、必ず煮汁に浸した状態で保存します。引き上げると、味の劣化に繋がりますから。
続きを読むには
無料で30日間お試し※
- 会員限定記事1,000本以上、動画50本以上が見放題
- ブックマーク・コメント機能が使える
- 確かな知識と経験を持つ布陣が指南役
- 調理科学、食材、器など専門性の高い分野もカバー
決済情報のご登録が必要です。初回ご登録の方に限ります。無料期間後は¥990(税込)/月。いつでもキャンセルできます。
フォローして最新情報をチェック!