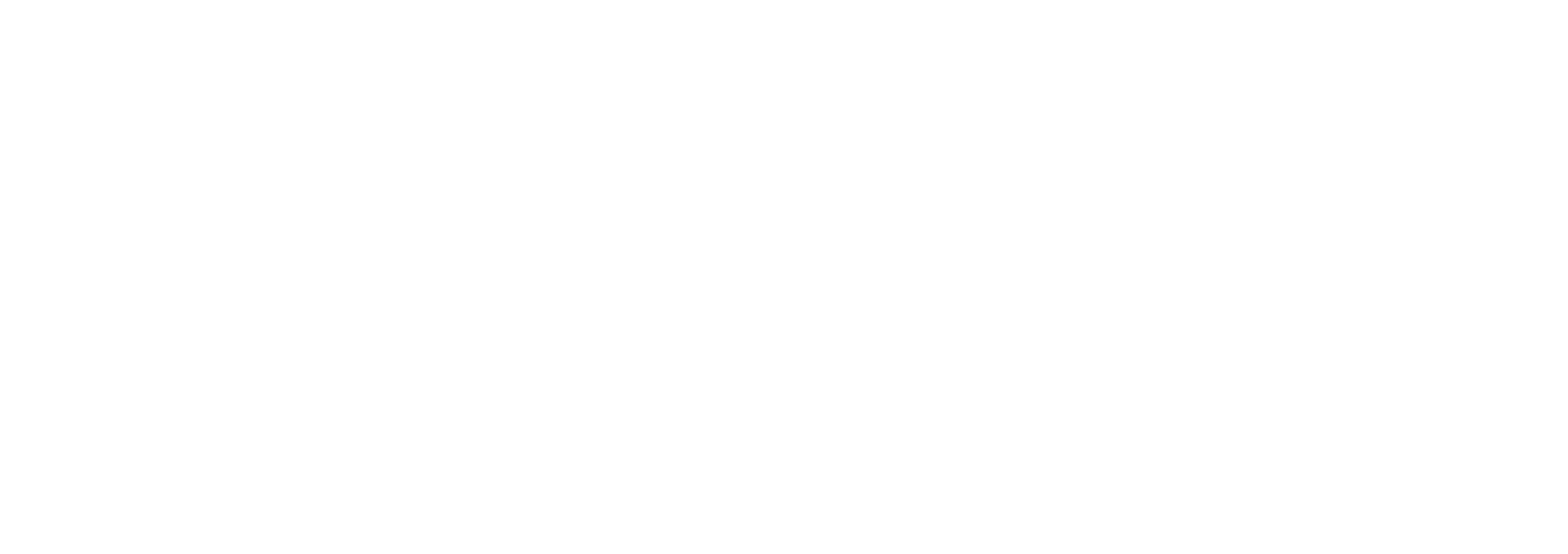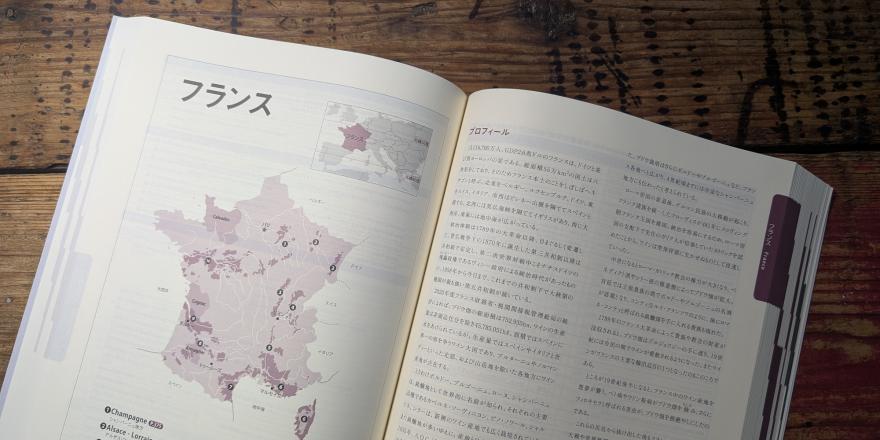料理人のためのソムリエ試験対策 Vol.14 白ワインを3つのタイプに分ける
ソムリエの松岡正浩さんから学ぶ「料理人のためのソムリエ試験対策」第14回目は、二次試験の白ワイン攻略法について。ブラインドテイスティングと考えると難しそうに感じますが、パターン化した上で分析することでブドウ品種を絞り、得点に繋げることが可能です。ポイントは「外観」→「香り」→「味わい」の順で判断する3つのタイプ分けです。
-

-
松岡正浩(「合同会社 まじめ2」代表 / 大阪・北新地『空心 伽藍堂』シェフソムリエ)
兵庫県出身。山形大学に進学後、県内のホテルに就職。東京『タテル ヨシノ 芝』にて本格的にフランス料理の世界に入り、その後、渡仏。『ステラ マリス』を経て、パリの日本料理店『あい田』ではシェフソムリエとして迎えられた。帰国後、和歌山『オテル・ド・ヨシノ』にて支配人兼ソムリエを務め、2016年、日本料理『柏屋』へ。こちらでも支配人兼ソムリエを務め、ワイン・日本酒を織り交ぜたペアリングコースを提案。レストランガイド「Gault&Millau(ゴ・エ・ミヨ)2021」にてベストソムリエ賞受賞。2022~23年、京都・御所東のフランス料理『Droit(ドロワ)』においてギャルソンとして勤務。23年6月より、大阪・北新地の中国料理『空心 伽藍堂』にてシェフソムリエを務める。
Vol.9において、主要白ブドウ品種の特徴についてお伝えしました。それらを頭に入れた上で、白ワインを3つのタイプに分類することを目指します。
白ワインの3タイプ
何事もそうですが、得意なパターンを持っている方は物事を優位に進められるものです。二次試験も同様で、ただやみくもにテイスティングし分析するのではなく、できる限り簡素にパターン化し、自身の中に落とし込むことで道筋が見えてきます。
ということで、二次試験では、白ワインを「3タイプ」のいずれかに分類することを前提にテイスティングを進めます。
①スッキリ、溌剌、柑橘類の香りの「爽やかタイプ」
柑橘類のスッキリ爽やかな香り、鋭角な酸味によってキリリとしているタイプです。
該当主要品種: ソーヴィニヨン・ブラン、ミュスカデ、甲州
【外観】
濃淡は「淡い」から「やや濃い」程度でそれほど濃くはありません。さらに「グリーン」のニュアンスを感じることができれば、このタイプを代表するブドウ品種、ソーヴィニヨン・ブランが最有力候補になります。
【香り】
模範解答には、白い花等のコメントも並びますが、レモン・ライムなどの柑橘類の香りが主体です。
一方で、スッキリした印象でほんのり柑橘香を感じるけど、いまいち明確な特徴がとらえられない場合は、ミュスカデ、甲州のニュートラル品種の可能性が浮上します。
【味わい】
アタックは軽めで、鋭角な酸を感じます。しっかりどっしりした雰囲気はありません。
全体的に爽やかで、余韻に程よい渋みを伴うことが多く、味わいにおいても柑橘の印象が特徴的です。
②白い花やリンゴ、桃のような甘い香りの「華やかタイプ」
ブドウ品種由来の華やかな香りが特徴です。
該当品種: リースリング、ゲヴュルツトラミネール
【外観】
「グリーン」のニュアンスを感じることが少なく、どちらかといえば「レモンイエロー」、濃淡は「非常に濃い」とまではいかない感じです。このタイプは外観だけで判断することは難しいかもしれません。
【香り】
白や黄色の花、リンゴ、カリン、モモ、ライチなど、リッチで甘やかな香りが特徴的です。柑橘の香りや爽やかさも見え隠れしますが、華やかさが勝ります。
特に、ゲヴュルツトラミネールは「ライチ」の香りが非常に個性的で、他の白ワインと一線を画しています。
【味わい】
上記の「爽やかタイプ」のキリリとした酸とは違い、落ち着ついた滑らかな酸が特徴、全体的に重心が低いと言えます。また、ねっとりとまではいきませんが、しっかりとした質感を感じます。
ただ、このタイプのブドウ品種は、比較的冷涼な気候を好むため、アルコールのボリュームはそれほど強くはありません。
③樽のニュアンスがはっきりわかれば「シャルドネ」
二次試験的に「樽香=シャルドネ」と考えます。
【外観】
樽に入れることによって「グリーン」のニュアンスが失われ、「イエロー」に向かって濃くなっていきます。
【香り】
樽の風味がワインに移り果実香と馴染むため、角が取れて丸くなりバランス良く感じられるようになります。
【味わい】
空気に触れることで味わい的にもまろやかになります。また、どちらかといえば、しっかりとした白ワインを樽に入れることが多く、そのため果実味とアルコール感を感じる可能性が高くなります。
※近年、樽のニュアンスの無いシャルドネも出題されておりますが、そこを意識すると二次のテイスティングが一気に難しくなります。ですから、樽香を感じられないシャルドネ(シャルドネと判断することがとても難しいのですが)は上記①の「爽やかタイプ」と割り切り、ブドウ品種は諦めて、テイスティングコメントで得点を稼ぎます。
この3タイプいずれかに分けることができれば(ブドウ品種を外したとしても)、テイスティングコメントはそのタイプごとに似通っているため、得点につながります。

白ワインを3つのタイプに分けてみる
①外観で大まかにイメージする
白ワインは一般的に新しいものほどグリーンの印象が強く、年月が経つにつれてグリーンが減り、徐々にイエローが濃くなり褐色を帯びていきます。ワインは酸化熟成なので、鉄が錆びるように赤く(褐色に)なるイメージです。
ただ、グリーンの印象はブドウ品種による個性でもあり、ソムリエ試験的にはソーヴィニヨン・ブランの特徴といえます。
また、温暖な産地のブドウは良く熟し、アルコールのボリュームが強くなる可能性が高いため、粘性も強くなります。
これらのことをふまえ、外観をしっかりと観察しながらこの先の道筋をイメージします。
・色調と濃淡
白ワインの外観については、なによりも「グリーン」のニュアンスが感じ取れるかどうか、濃淡がどうなのかに注目します。
「グリーン」を感じ、淡いと判断した場合、「爽やかタイプ」、そしてソーヴィニヨン・ブランをぼんやりイメージします。ただ、ここで決めつけることはせず、グリーンのニュアンスは若々しいワインの特徴でもあるため、少なくとも樽香を感じるシャルドネはないであろうと想定し、香りに進みます。
「グリーン」のニュアンスが少なく、または感じられず、「淡い」から「やや濃い」程度のあまり濃くない場合がとても悩ましいです。一呼吸置いて、さまざまな可能性があると思いつつも「華やか系」かも…とイメージしましょう。
ミュスカデ、甲州であればグリーンが少なく、より「淡い」可能性が高いのですが、この段階ではあまり深追いせず、香りの段階で「爽やかタイプ」なのに…と違和感があると思った時に思い出す程度で十分です。
一方で、グリーンでやや濃いかなと思った場合は、温暖産地のソーヴィニヨン・ブランの可能性があります。
※甲州種の果皮は赤紫色で、その色調が感じられるものがあります。ですから、淡くてどことなく「ほんのり赤み」を感じた時は甲州の可能性を考えてもよいと思います。
明確に「レモンイエロー」「イエロー」を感じ、淡くはない場合はセオリー通り、シャルドネをイメージしましょう。さらに、その濃さによっては温暖な産地をイメージすることになります。
・粘性
いかにトロリとしているかということ。
大まかに「爽やかタイプ」→「華やかタイプ」→「樽=シャルドネ」の順に、イエローが強くなるにしたがって粘性も増す傾向です。
また、粘性はアルコール度数に影響されるので、暖かい地域のワインの特徴でもあります。
ただ、粘性を感じ取ることはなかなか難しいものです。アルコールのボリュームに連動することが多いので、「味わい」のあとに戻って確認するようにしましょう。
このようにイメージを持って香りに進むことがとても大切なのですが、この段階でタイプやブドウ品種を決めつけることは危険です。あくまでパターンとしてこうであればよいなと想定しつつ、柔軟な姿勢で先を急ぎましょう。
②香りで3つのタイプに分ける
外観で想定したイメージをもとに、香りでタイプ分けの分析をしつつ、冷涼産地なのか、温暖産地かのというところまで意識します。
まずは、外観でのイメージと香りの第一印象からどのタイプに近いのかをぱっと決めてしまいましょう。ご存知のように嗅覚はすぐに慣れてしまい、香りをあまり感じなくなります。ですから、最初の印象はとても大切です。この時に感じた第一印象は、テイスティング用語選択用紙の端にでも書き留めておくとよいかもしれません。
ただ、ワインの温度が低かったり、開いていない時は香りが取りづらく、外観からここまでの流れでいまいちイメージが持てない場合は、後回しにして次のワインのテイスティングに進むべきです。
外観で(グリーンの有無にかかわらず)「爽やかタイプ」をイメージした場合、フレッシュハーブを刻んだ時のような青い香りが感じ取れるかどうかを確認しましょう。また、NZのソーヴィニヨン・ブランはフレッシュハーブより強い青さ、私は夏の日の草原にいるような香りを感じます。この青い香りを感じたらソーヴィニヨン・ブランであろうと想定して先に進みます。
外観で「爽やかタイプ」をイメージしたにもかかわらず、上記の「青い香り」をほとんど感じなかった場合、ミュスカデ、甲州、そして(難しいのであきらめるべき、固く引き締まった)リースリングの可能性があります。
ミュスカデ、甲州は香りの要素、ボリュームが圧倒的に乏しく、特にミュスカデは果実香以上に、ミネラル、塩味・潮の風味(例えるなら昆布出汁のような)が主体です。甲州は日本酒や丁子(クローブ)の香りが特徴と言われます。
「華やかタイプ」は外観ではイメージしづらいため、香りで判断できるようになることが重要です。
白色や黄色の花、カリン、モモ、ライチなどと表現される甘くて華やかな香りが前面にでており「爽やかタイプ」のような溌剌としたニュアンスは感じません。また、樽のニュアンスもありません。リースリングとゲヴュルツトラミネールはブドウが持つ特徴がそのままワインに表れると言われています。
そして、華やかで甘やかな香りが感じ取れればリースリングらしい香りがあるかを探ります。特徴と言われるペトロール香(石油香)を見つけることができればリースリング確定ですが、感じ取れないワインもあり、少なくとも「爽やかタイプ」でも「樽=シャルドネ」でもない…と思った場合、よくわからないけどリースリングかなというイメージで味わいに進むとうまくいくことが多いように思います。
ゲヴュルツトラミネールは主要品種に入れなくてもよいのですが、ライチ香といわれる非常に個性的な香りを持つため、とてもわかり易いです。
外観でグリーンを感じず、レモンイエローからイエロー、やや濃いから濃いと判断した場合、「樽香」を感じることができればラッキーです。
シャルドネはブドウ品種由来の特徴的な香りを感じることが少なく、樽由来のバターやナッツの香りを感じます。加えて、マロラクティック発酵の影響で香りが丸く、まろやかになっている可能性が高いと言えます。
この濃い系の外観で、樽香を感じ取れない場合は「華やかタイプ」の可能性があると知っておきましょう。
これらのタイプ分けに加え、果実香の強さ、凝縮感から冷涼産地なのか、温暖産地なのかまでイメージします。
例えば、ミュスカデはフランス・ロワール地方のブドウ品種なので、果実香から強さは感じられず、冷涼な印象です。このタイミングで「タイプ分け」のイメージが持てなくても、少なくとも冷涼な産地であることが判断できれば、コメントの強弱で得点を拾うことができます。
③味わいで最終確認
外観で大まかなイメージを持ち、香りでタイプ分けし、さらに、冷涼産地なのか温暖産地なのかを判断できていれば最高の状況です。味わいで最終確認という流れになります。
ただ、全てのワインにおいて、スムーズにタイプ分けまで進んでいるとは考えにくく、「爽やかタイプ」とも「華やかタイプ」とも言い切れない微妙なワインも出題されます。それでも、イメージを持ちつつパターンを意識してテイスティングすることが二次試験攻略の最短距離だと私は考えております。
さて、味わいで特に感じ取るべきは酸味とアルコールのボリュームです。
・酸味
酸味をどのように感じるのかを確認しましょう。
「爽やかタイプ」が最もわかりやすく溌剌とした酸味を感じます。ソーヴィニヨン・ブランは果実味、酸味ともにしっかりと感じる一方で、ミュスカデは果実味に乏しく、やや単調で酸味とミネラルが際立っています。ただ、甲州は溌剌というほど酸味が強いわけではありません。
このミュスカデと甲州を「爽やかタイプ」の違和感として感じられるようになれば合格は目の前です。
「華やかタイプ」は、なめらかで落ち着きのある酸味が特徴です。ただ、時折リースリングで酸味を鋭角に感じるものがあります。これらは「爽やかタイプ」をイメージし、ブドウ品種は外すことになりますが、テイスティングコメントで得点を稼ぐことができれば十分に合格に届きます。
「樽香=シャルドネ」はマロラクティック発酵由来のなめらかな酸味、香りに引き続き全体的に丸い印象です。
また、ワイン全般に言えることですが、冷涼産地の方が酸味を鋭角に感じ、温暖産地は酸味が穏やかな分、より果実味が主張します。
・アルコールのボリューム
アルコールのボリュームを感じることも慣れないうちは難しいと思います。ですから、果実味がどのレベルまで凝縮しているのか、というところからアルコールを意識してテイスティングを続けてください。
一般的に、冷涼産地(ドイツ・フランス)は果実味もリンゴのように爽やかで、アルコールのボリュームも軽めになります。一方で、温暖産地(新世界)はマンゴーのように力強い果実の凝縮感を感じ、アルコールも強めになります。
「爽やかタイプ」のアルコールのボリュームは「軽め」から「中程度」である可能性が高く、ただ、新世界のソーヴィニヨン・ブランは「やや強め」になることもあります。
「華やかタイプ」のブドウ品種はどちらかといえば冷涼な産地を好むため、アルコールをそれほど強く感じることはありません。
「樽香=シャルドネ」の場合、上記諸々の理由により、樽香、果実味、酸味がバランス良く感じられ、何かの要素を突出して感じることが少ないです。
それでも、そのバランスの中で、酸味が優位なのか、果実味が主体なのかを感じて、冷涼産地(フランス)なのか、温暖産地(新世界)を判断する必要があります。
このように酸味とアルコールのボリュームはワインのタイプ分け、また冷涼産地or温暖産地の判断における最終確認のポイントとなります。しっかりととらえられるように頑張りましょう。
さて、白ワインのタイプわけ、ご理解いただけましたでしょうか。一度や二度、こちらをお読みいただいただけでは理解することは難しいと思いますが、「外観」→「香り」→「味わい」の流れの中で、3タイプに分類することを意識してテイスティングを繰り返すことで、見えてくることがあると思います。そして、このパターン化を理解することで、二次のテイスティングの道筋が見えるようになってきます。
二次試験を純粋なブラインドテイスティングとしてとらえると、非常に難易度の高い試験になります。しかし、このように簡素化しパターンに落とし込むことで、二次のテイスティングは攻略可能になります。
次回は、赤ワインのタイプ分けについてお伝えします。
▼料理人のためのソムリエ試験対策 他の回はコチラから。
Vol.1 概要編
Vol.2 一次試験対策前にすべきこと
Vol.3 一次試験対策の準備と春先までの勉強法
Vol.4 一次試験対策、教本と過去問を利用した勉強法
Vol.5 二次試験対策の準備
Vol.6 二次試験対策として意識すべきワインについて
Vol.7 テイスティングして書き留める
Vol.8 ワインの酸とアルコール
Vol.9 主要白ブドウ品種の特徴
Vol.10 主要黒ブドウ品種の特徴 その1
Vol.11 主要黒ブドウ品種の特徴 その2
Vol.12 ラストスパート!一次試験前二ヶ月間の一次試験対策
Vol.13 二次試験を意識したテイスティング
Vol.15 赤ワインのタイプ分け
Vol.16 二次のテイスティング対策最終章~「模範テイスティングコメントを暗記する」
Vol.17【最終回】三次試験・サービス実技対策
フォローして最新情報をチェック!