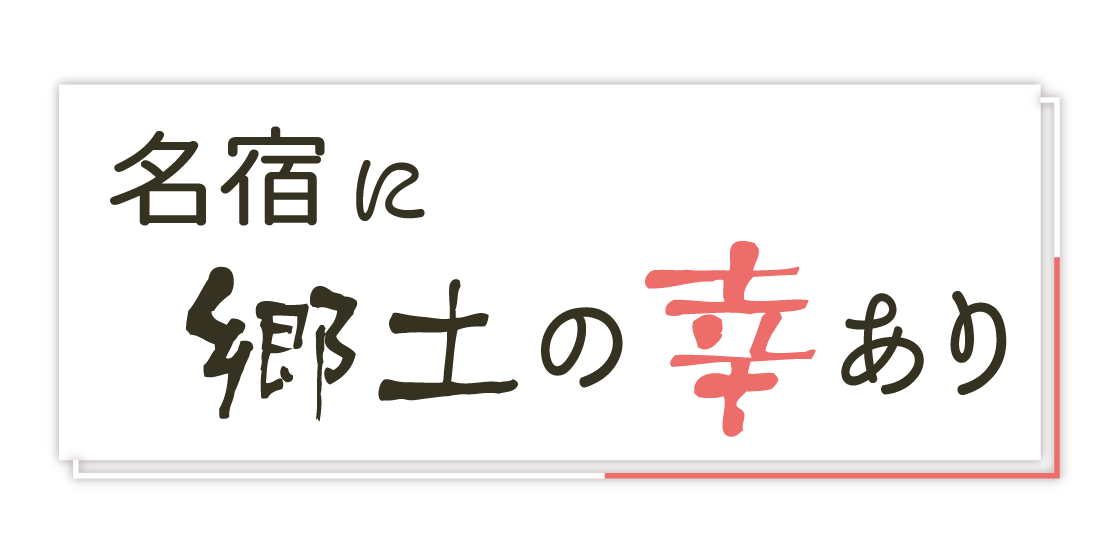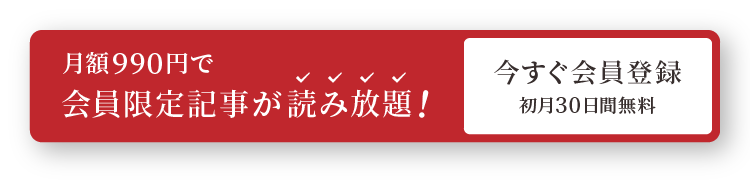京都・宮津『amano₋hashidate 幽斎』の丹後食材だけで仕立てる“京新感和食”
“海の京都”と呼ばれる丹後半島は、海山里の幸に恵まれた環境に加えて、人の営みによる産物も豊富です。そんな土地で100年以上続く料理旅館の四代目が、新たに興した和のオーベルジュ『amano-hashidate 幽斎』。料理は、ほぼ100%地元産、生産者の顔が見える素材で作られる“京新感和食”。固定概念に囚われない自由な発想で生み出される新しい味わいは、地元の人さえ驚かせ、伝統の食材に新しい息吹を与えています。初夏の名産・丹後とり貝づくしのコースを例に、詳細ルポをお届けいたします。
1日2客の和のオーベルジュ

日本三景・天橋立といえば山上からの股覗(またのぞ)きが有名だが、橋立を横から眺めるユニークな景勝地に、和モダンな館が建っている。和のオーベルジュ『amano-hashidate 幽斎』は、静かな阿蘇の海を目の前に、広々としたダイニングと大小の個室で昼夜食事のみのゲストを迎え、メゾネットタイプの2部屋で1日2客の宿泊も受ける。
亭主の岸和田安弘さんは、宮津市内で100余年続いた旅館の四代目だ。大阪の調理師学校に学び、そのまま3年間、日本料理の教授の助手として食材調達の仕事に就いた。その後、京大阪の有名料亭で経験を積んで、実家の旅館へ。
「毎日200食の仕出し弁当と、時には60人規模の宴会料理を作っていました」。
自分が本当に食べたい料理、作りたい料理ができずに欲求不満が募る日々。それが実に20年に及んだ頃、老朽化した旅館を建て直すことになり、思い切って「和のオーベルジュ」として新築移転に踏み切った。2010年のことだ。
そうして、抑えていた料理への情熱をぼうぼうと燃やすように岸和田さんが取り組んでいるのが、名付けて“京新感和食”。「固定概念に囚われず、地の物で“美味しい”を追求する」のが信条だ。
「丹後には海鮮はもちろん、野菜や山菜、牛や豚などの肉類。上質な調味料もあるんです」と、四季折々ほぼすべての食材を地元産でまかなっている。しかも、地元の人さえ、「へぇこれがお馴染みのアレかいな!」と驚くような新しい調理法も続々とあみ出しているのだ。
初夏は名産・丹後とり貝づくしがイチオシ。はてさて、どんな姿で登場するのだろう。
ひねりを加えて5個以上、丹後とり貝づくしコース
 丹後とり貝は小、中、大、特大、特特大、特選と6段階に選別されるが、『幽斎』で使用するのは大サイズ、150~169g以上のもの。ちなみに特大は170~189g、特特大は190~219g。
丹後とり貝は小、中、大、特大、特特大、特選と6段階に選別されるが、『幽斎』で使用するのは大サイズ、150~169g以上のもの。ちなみに特大は170~189g、特特大は190~219g。
「丹後とり貝」としてブランド化された育成のトリ貝は、大型で肉厚で味も濃厚と近年つとに有名で、京阪神はもとより東京でも引く手あまた。そのトリ貝を『幽斎』では地元の威信をかけて、「動くとり貝料理 地産厳選素材でもてなす究極の味」と題し、全13品のうち漬物、デザートを除くすべてに使う。その量、1人前で5個以上だ。
しかも、「温度を変えることで異なる食感を楽しませたい」と岸和田さん。
付き出しの冷製豆乳蒸しには、90℃で10秒ボイルしてオン。小気味よい弾力を楽しませる。
次のおしのぎは、大ぶりな姿をダイレクトに見せるにぎり。1カンは10秒ボイルしてから炙り、もう1カンはなんと西京漬けに。「味も凝縮するし、香ばしさも増します。トリ貝の新たな表情を楽しんでもらえるかな、と思って」。
ほぼオール丹後産と謳うだけあって、主役の丹後とり貝を支える名脇役たちも地元の幸づくし。付き出しに使うキュウリは宮津産、豆乳も与謝野町の豆腐屋から。
寿司に添えた甘酢漬けのショウガも、煮物の「とり貝と山菜沢煮」の野菜や山菜も、宮津や伊根で作られたもの。そこに、時折、自家菜園の椎茸や木の芽が加わる。
さらに、味噌やオリーブ油などの調味料も、岸和田さんが道の駅などで探し集めて来たもの。それらを、一つ一つ奥さんの史子さんがサービスしながら解説し、ゲストの旅情をくすぐる。
 付き出しは、冷製の豆乳蒸し。トリ貝は、独特のシャクッと軽やかな食感と、ミルキーな甘みを引き出すため、90℃で10秒ボイル。由良産レモンを2年寝かせて手作りした塩レモンポン酢を掛けてあり、爽やかな幕開けだ。
付き出しは、冷製の豆乳蒸し。トリ貝は、独特のシャクッと軽やかな食感と、ミルキーな甘みを引き出すため、90℃で10秒ボイル。由良産レモンを2年寝かせて手作りした塩レモンポン酢を掛けてあり、爽やかな幕開けだ。
 おしのぎとして供す、にぎり。90℃とり貝炙り煮ツメはワサビで。とり貝西京漬け炙りは柚子胡椒で。寿司飯は、地元の米を使い、宮津『飯尾醸造』の「富士酢」などで味付け。
おしのぎとして供す、にぎり。90℃とり貝炙り煮ツメはワサビで。とり貝西京漬け炙りは柚子胡椒で。寿司飯は、地元の米を使い、宮津『飯尾醸造』の「富士酢」などで味付け。
食感と食べ方にも変化をつけて
「宮津の漁師たちはトリ貝を醤油煮にして食べていましたが、改めて最適温度を探しつつ、一品ずつトリ貝料理を増やしていきました。産地でも造りか炙り、味付けも醤油醬油か酢味噌ばかりで、がっかりしたという声を耳にしていたので」と岸和田さん。
「動くトリ貝を楽しんでもらうために考えました」と言うお造りは、塩で揉むとハクが取れてしまうので、60℃で5秒の湯洗いに。箸の先でつつくと、うねりと動く様も楽しませる。塩とオリーブ油で勧める、というのも独創的だ。
 トリ貝は身、ヒモを湯洗いにし、サワラ焼き霜、鯛と鯛の子昆布じめ、白バイ貝と盛り合わせて。魚介はすべて地元の海から。自家製梅味噌、醤油の他、由良産のオリーブ油と丹後の海水を4日間焚いた網野の「翁乃塩」を添えて。オリーブ油とにがりが少し残った塩の組合せが貝の甘みを際立たせる。
トリ貝は身、ヒモを湯洗いにし、サワラ焼き霜、鯛と鯛の子昆布じめ、白バイ貝と盛り合わせて。魚介はすべて地元の海から。自家製梅味噌、醤油の他、由良産のオリーブ油と丹後の海水を4日間焚いた網野の「翁乃塩」を添えて。オリーブ油とにがりが少し残った塩の組合せが貝の甘みを際立たせる。
焼物は、陶板焼きからの和風アヒージョという2段構えで。
まずは、濃口醤油・みりん・地酒で少し甘みのある味付けを施し、トリ貝を焼く。身をくねらせた後、レアな一瞬を逃さず、「今が食べ頃ですよ!」と史子さん。
トリ貝の旨みが出た残り汁にオリーブ油とニンニク、レンコ鯛、モンゴイカを加え、その美味しいオイルもパンに吸わせて余さず味わわせるという趣向だ。
 アヒージョにする前、「肝は二つのうち一つは残しておいてください」と史子さんがアナウンス。肝の旨みがオイルに移り、味の深みがぐんと増す。
アヒージョにする前、「肝は二つのうち一つは残しておいてください」と史子さんがアナウンス。肝の旨みがオイルに移り、味の深みがぐんと増す。
トリ貝づくしのラストを飾るのは、トリ貝のヒモと、神馬草(ジンバソウ)と呼ばれる海藻、野菜をかき揚げにしてのせた天茶。食べたことのないトリ貝の姿と食感をさまざまに楽しめるユニークなコースになっている。
 酒ももちろん地元産づくし。「丹後には10以上の酒蔵があるんですよ」と岸和田さんセレクトの地酒は左から、伊根『向井酒造』の「京の春 益荒猛男(ますらたけお)」、久美浜『木下酒造』の「玉川 無濾過生原酒 雄町」、与謝野『谷口酒造』の「蕪村翁(ぶそんおう)」。上世屋(かみせや)村でベルギー人と日本人のご夫婦が営むマイクロブルワリー『kohachi beerworks』のクラフトビールも揃える。
酒ももちろん地元産づくし。「丹後には10以上の酒蔵があるんですよ」と岸和田さんセレクトの地酒は左から、伊根『向井酒造』の「京の春 益荒猛男(ますらたけお)」、久美浜『木下酒造』の「玉川 無濾過生原酒 雄町」、与謝野『谷口酒造』の「蕪村翁(ぶそんおう)」。上世屋(かみせや)村でベルギー人と日本人のご夫婦が営むマイクロブルワリー『kohachi beerworks』のクラフトビールも揃える。
上世屋(かみせや)村からジビエも届く
実は八寸には、さりげなくジビエが組み込まれていた。
「鹿のカマボコ、鹿カマです(笑)」と岸和田さん。
鹿のスネ肉や端肉のミンチに、実山椒や世屋の手作り味噌、塩、ネギをよく混ぜて蒲鉾板に塗り、オーブンで焼き抜き、軽くスモークしたオリジナルな一品だ。
鹿肉も、もちろん地元産。宮津の山間にある上世屋村に獣肉を扱う店が出来たとのことで、冬場は猪肉も仕入れていると言う。
 八寸。左手前が夏鹿カマ。トリ貝は、ヒモを90℃ボイルで、糸もずく酢と。肝も塩焼きにして添える。煮サザエ、スズキ和風マリネ、鯛ふくさ焼、空豆。赤大根に挟んだのは鰆のへしこディップ。
八寸。左手前が夏鹿カマ。トリ貝は、ヒモを90℃ボイルで、糸もずく酢と。肝も塩焼きにして添える。煮サザエ、スズキ和風マリネ、鯛ふくさ焼、空豆。赤大根に挟んだのは鰆のへしこディップ。
リクエストがあれば、ジビエを使った一品も仕立てる。これまた岸和田流の工夫が凝らされていて愉しい。
鹿のヘレ肉は、火入れしない生の世屋味噌に自家製の甘酒を加えた床で2時間ほど幽庵漬けにし、63℃で30分の低温調理。「鹿肉はパサつくイメージなので」、温泉卵にした黄身と一緒に食べてもらう。
「でも、上世屋の鹿肉は処理が良いせいか、結構しっとりしているんです」。確かに、柔らかくジューシーな肉だ。
“花びらカツ”と命名したのは、「鹿肉は火を入れると硬くなるのでペチャンコにしてみました」と言う極薄い鹿カツ。ソースは、地元のブランド牛・京たんくろ和牛の端肉を煮込んで作ったドミグラスに、ビーツとイチゴ(あきひめ)を加えたものだ。

奥が鹿ヘレの幽庵漬け。白身は地鶏の甘酒塩麹漬けで、55℃で50分の火入れ。中央の黄身は地鶏の初卵。右は冨士酢で漬けた庭の菜園のプチトマトと青唐辛子。メキシコのサルサ風の薬味。
 左/奥は鹿カマ。手前は地鶏の燻製。与謝野の桜のチップで燻製したオイルをまぶして。小玉ネギの浅漬け、自家菜園のバジルと。右/鹿ロースの花びらカツ。与謝野のルッコラを添えて。
左/奥は鹿カマ。手前は地鶏の燻製。与謝野の桜のチップで燻製したオイルをまぶして。小玉ネギの浅漬け、自家菜園のバジルと。右/鹿ロースの花びらカツ。与謝野のルッコラを添えて。
純国産鶏の卵を朝食の目玉に
岸和田さんは「ずーっと厨房にいるんですよ」と史子さんが笑うほどの料理好き。ドレッシングも、朝食に土鍋で供するたっぷりの豆腐や干物も、すべて自家製だという。その中で目を引くのは、たっぷりのだしを湛えた、薄黄色のだし巻き玉子だ。
その卵も、もちろん地元産。伊根の『三野(みつの)養鶏場』から“もみじ”と呼ばれる純国産鶏の卵を仕入れている。色も味も濃い高級卵の黄身とは違って、サイズも小ぶりで、淡い色。ナチュラルな優しい味がする。
実は、夕餉に幽庵漬けの鹿ヘレ肉と共に出された白身は、同養鶏場の鶏。温泉卵も「三野さんとこの初卵です」と岸和田さん。
 ホウレン草のお浸しや木の芽ジャコなど小鉢に至るまで丁寧な手作りで。すくい取りの豆腐は加悦(かや)町の『才本とうふ店』の豆乳と、網野の『山と海with日本海牧場』のにがりで作る。干物は、根付きのアジ酒干しやイワシみりん干しで、ほっくりとした身がジューシー。土鍋ご飯は丹後コシヒカリ。具だくさんの味噌汁に、自家製ハム。1人前2個使うという特大のだし巻きは、みりん多めのちょい甘で、フワフワ。
ホウレン草のお浸しや木の芽ジャコなど小鉢に至るまで丁寧な手作りで。すくい取りの豆腐は加悦(かや)町の『才本とうふ店』の豆乳と、網野の『山と海with日本海牧場』のにがりで作る。干物は、根付きのアジ酒干しやイワシみりん干しで、ほっくりとした身がジューシー。土鍋ご飯は丹後コシヒカリ。具だくさんの味噌汁に、自家製ハム。1人前2個使うという特大のだし巻きは、みりん多めのちょい甘で、フワフワ。
 ウエルカムスイーツは『三野養鶏場』の卵と久美浜の「ヒラヤミルク」で手作りする焼きプリン。庭のハッカと、与謝野町のサクランボを添えて。あっさりミルキーな味わい。
ウエルカムスイーツは『三野養鶏場』の卵と久美浜の「ヒラヤミルク」で手作りする焼きプリン。庭のハッカと、与謝野町のサクランボを添えて。あっさりミルキーな味わい。
トリ貝の季節が終われば、次は岩牡蛎やアワビ。冬にはもちろん松葉ガニ、ブリもある。京たんくろ和牛や地鶏、鹿に猪などのジビエと肉類も通年食べられる。由良川のほとりではオリーブが植えられ、黒米、赤米などの古代米栽培も盛んだ。丹後の食材は確かにバラエティーに富んでいる。
が、それにしてもなぜ、ここまで地元産にこだわるのか。
「どこまで宮津、丹後を感じてもらうか。それが、わざわざここまで来てくださったお客様への一番のもてなしでしょう」と岸和田さん。
「今日は100%丹後でいけました」と、魚介も野菜も調味料に至るまで、出自と来歴を嬉々として話す。
代々地元に暮らしてきた地の利と人脈、「前職の食材調達の経験も生きてますね」と言うが、アンテナは常に張り巡らせている。
それに「とにかく料理をするのが楽しい」とも。「小学生の頃かな。うちの旅館でトリ貝を出してたんですが、貝柱が残るでしょ。美味しそうやなと思って、バターで炒めて醤油をポタポタ落としてオヤツにしてました。今思えば、私の発想の原点かもしれません」。
これからも地元愛と料理好きの両輪で、岸和田さんの“京新感和食”はますます進化していくに違いない。
 宿主の岸和田安弘さん。「化学調味料や出来合いのものは使用せず、あしらい、調味料なども手作りする。「大変かって? いえいえ楽しみながら料理してます」というご本人の言葉を横で聞いていた奥さんの史子さんが、「本当に楽しそうで、厨房から出てきません」と笑う。
宿主の岸和田安弘さん。「化学調味料や出来合いのものは使用せず、あしらい、調味料なども手作りする。「大変かって? いえいえ楽しみながら料理してます」というご本人の言葉を横で聞いていた奥さんの史子さんが、「本当に楽しそうで、厨房から出てきません」と笑う。
 宿泊の客室はデザインの異なる2部屋。共に1階のダイニングで食事を楽しむ。2階はベッドルーム。バストイレ付き。大きな窓から天橋立が眺められる。
宿泊の客室はデザインの異なる2部屋。共に1階のダイニングで食事を楽しむ。2階はベッドルーム。バストイレ付き。大きな窓から天橋立が眺められる。
 細川幽斎がこの景観を気に入り、2本の松を植えたことから、「二本松」と呼ばれる地に建つ。阿蘇の海は目の前だ。
細川幽斎がこの景観を気に入り、2本の松を植えたことから、「二本松」と呼ばれる地に建つ。阿蘇の海は目の前だ。
【住所】京都府宮津市字須津2653
【電話番号】0772-46-6878
【営業時間】in15:00〜、out~10:00
【お料理】1泊2食コース37400円~(丹後とり貝づくしコースは45100円~)。
https://www.you-sai.net
フォローして最新情報をチェック!