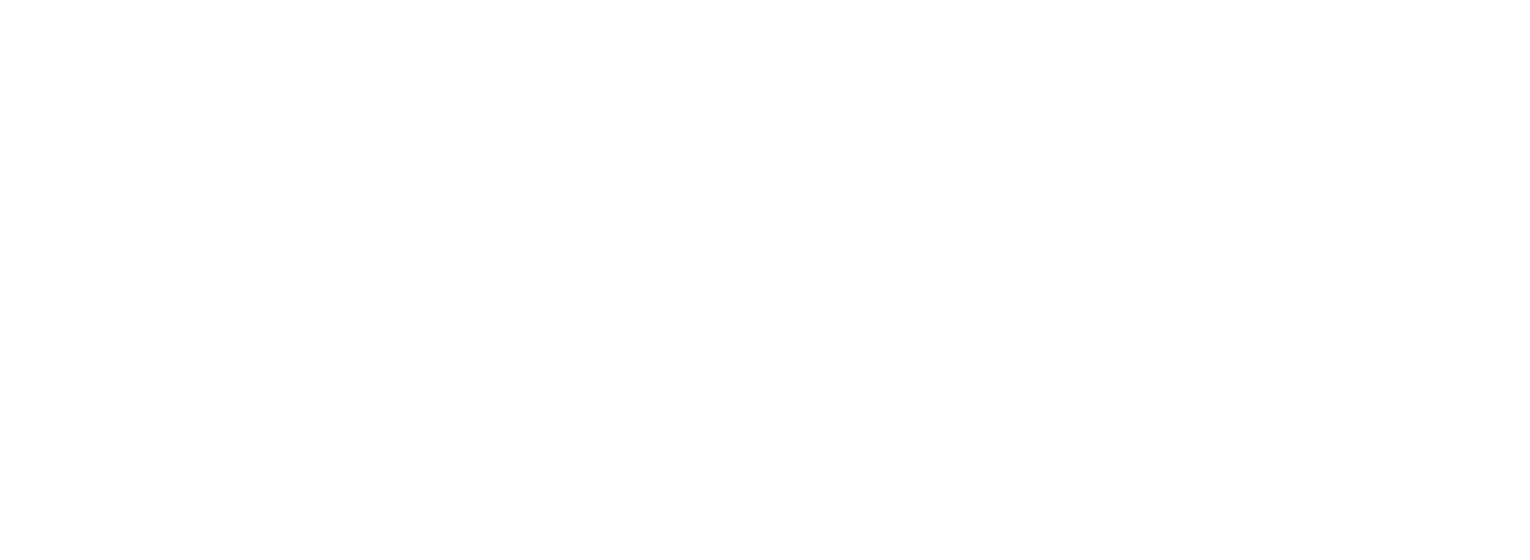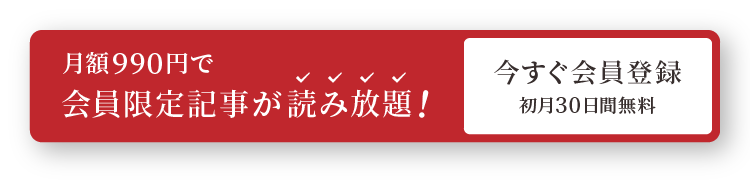高級食材として重宝された、奈良の伝統野菜
真夏の太陽を浴びて風に揺れる大きな緑の葉っぱ。長く伸びた茎を見ると、1本1本に新聞紙や厚紙が巻き付けてある。
「これで太陽光を遮断して育てることで、軟らかく真っ白な芋茎(ずいき)になるんです」。陽灼けした顔で話すのは、奈良市狭川(さがわ)地区でただ一人、「軟白ずいき」の栽培に取り組んでいる木本芳樹さんだ。
「軟白ずいき」とは、昭和の初め頃から狭川地区を始め、奈良県のごく一部で栽培されてきた大和伝統野菜のひとつ。トウノイモを種芋として育てるずいきの中でも、葉柄(ようへい)に光を当てない軟白栽培によって作られ、その美しい白さや軟らかくてえぐみやクセのない味わいから、かつては京都や大阪の高級料亭などで好んで使われてきた。ちなみに、軟白せずに育てたものは「紅ずいき」「赤ずいき」などと呼ばれ、乾物などでも食される。
最盛期には狭川地区だけで20軒ほどの栽培農家があったというが、高齢化などで次第に衰退。もはやこのエリアでは、1軒の栽培農家も残っていない状況だった。それを2018年に復活させたのが木本さんだ。
復活に協力した、大和伝統野菜の研究家であり、大和野菜を使ったレストラン『粟 ならまち店』と『清澄の里 粟』を経営する「プロジェクト粟」の代表・三浦雅之さんによれば「手間がかかる割に儲からない。そこで、高級食材としてブランド化をはかったことで生産量も生産地域も限定した。それが結果として衰退に繋がってしまったのではないでしょうか」。
一株一株に紙を巻く。栽培は太陽光との戦い
狭川地区の農家に生まれた木本さんだが、家業は継がず大阪の大手家電メーカーの会社員として働いていた。ある時、ふと立ち寄った本屋で何気なく手に取った雑誌で「幻の白ずいき」という文字を見つける。そこには、「軟白ずいき」の生産が途絶えてしまったことが書かれていた。
「子どもの頃、夏になるとよく食べていたあれが、もう食べられなくなるんや」。
ちょうど定年後のことを考え始めていた時期でもあり、生まれ育った狭川地区が産地の中心だったことにも心を動かされた。
三浦さんを通して栽培方法を知る人を紹介してもらったり、文献を漁ったり。試行錯誤の末、「軟白ずいき」の再生に成功したのだ。
野菜の一部に光を当てずに育てる軟白栽培には長い歴史があり、長ネギやホワイトアスパラなどは土をかぶせ、ウドや黄ニラ、チコリなどは遮光したハウスなどで栽培される。だが「軟白ずいき」の場合は、そう単純にはいかない。大きな葉にはたっぷりと太陽光をあてて光合成を促しながら、一方で葉柄は光を完全に遮断して白く育てなければならないからだ。
「育つにつれて背丈も伸びるし太くもなる。新聞や米袋を何度も巻き足していかないといけないんです」。
雨や台風で紙が破れてしまうこともある。隙間から少しでも光が入ると、その部分が赤くなってしまうことも。
「一瞬も気が抜けない、太陽光との戦いです(笑)」。
盛りは8月。軟白ずいきの食べ方
木本さんのご自宅で、絶滅の危機から蘇った「軟白ずいき」の酢物と漬物をご馳走になった。
さっぱりとした甘酢で和えたずいきは、シャクシャクとした独特の食感。真夏の畑で汗をたっぷりかいた後にはぴったりの爽やかな味わいだ。キュウリやミョウガなど夏野菜と一緒に塩でもんだ浅漬けは、木本さんにとって「子どもの頃、夏になると必ず食卓にあった定番の味」だとか。
近鉄奈良駅近くで人気の日本料理『奈良 而今(にこん)』の店主・清水唱二郎さんは、毎年夏になると木本さんの軟白ずいきが届くのを待ちわびている。
「だしを含みやすいので、味がよくのるんです。炊いても煮崩れしないし、あの独特の食感も市場のものとは全然違いますね」。
ゴマクリームと和えて八寸に入れたり、吸い物にしたり。叩いたオクラなどネバネバと合わせて食感のコントラストが出る料理に使うことも多いそう。
「アワビと一緒に炊いて吉野葛を流して椀物にしてもいい。味に強い主張がないので何とでも合わせられる。デザートっぽく、温かいぜんざいに入れて、食感のアクセントを楽しんでもらうのもいいと思います」。
三浦さんの店『粟』では、自家栽培の赤ずいきと組み合わせ、紅白の甘酢和えを出すこともあるとか。「芋は世界中で食べられていますが、ずいきを食べる民族は、おそらく日本人だけ。そういう意味ではまだまだ余白だらけ。いくらでも料理の幅が広がる可能性を秘めている食材です」。
湯葉や豆腐と同じく上品な白さ。その上、夏の一時期しか収穫できない旬の短さも、季節感を大切にする和食にとっては魅力的だ。
今は流通量も限られているが「栽培したいという人が増え、大阪や京都でも食べてもらえるようになったら嬉しいね」と木本さん。
ぜひ名乗りを上げる農家が増えることに期待したい。
木本芳樹さん
https://www.facebook.com/profile.php?id=100040972894037
『奈良 而今』
【住所】奈良市鍋屋町3
【電話番号】0742-31-4276
【営業時間】18:00〜20:30入店
【定休日】日曜、祝日の月曜
【お料理】コース13000円。※サ5%別。
『粟 ならまち店』
【住所】奈良市勝南院町1
【電話番号】0742-24-5699
【営業時間】11:30〜15:00LO、17:30〜21:00LO
【定休日】火曜
【お料理】昼/「収穫祭」御膳3190円、コース4290円~、夜/コース4290円~。









フォローして最新情報をチェック!