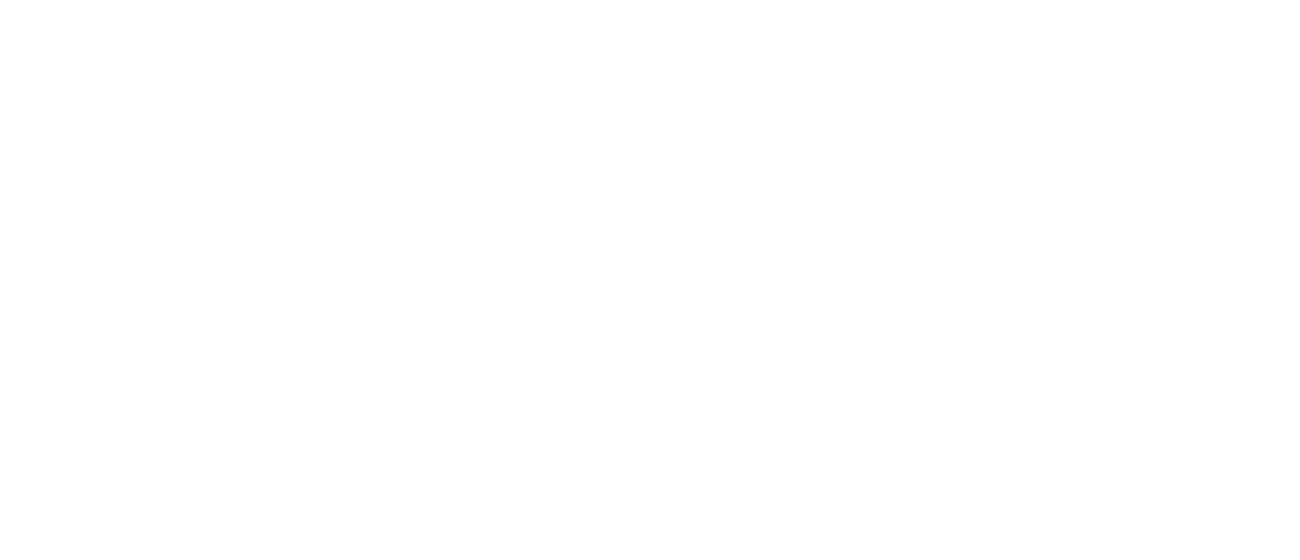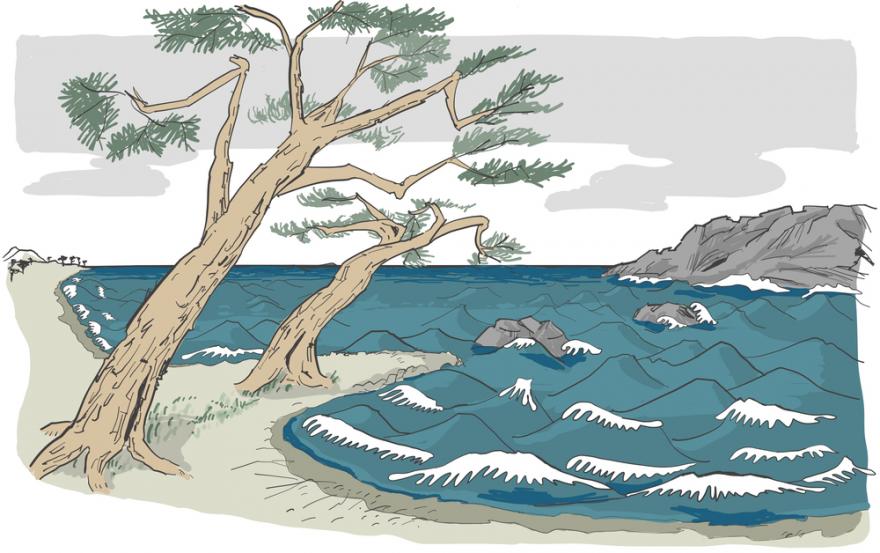控えめにして心を温める、師走の器
師走になると寒さは一気に増し、料理に合わせて器も冬ものに衣替えします。十一月の華やかな紅葉と一月のおめでたい新年の意匠に挟まれる十二月の器は少し控えめになりますが、味わい深い名品が揃います。
『本湖月』では「フグ」に「福」という字をあて、盛るにふさわしい茶事のお道具が登場。ご主人、穴見秀生さんに料理人として、数寄者として、冬本番を迎える十二月の器への想いを語っていただきました。
先付——「柚味噌皿」は、柚子皮に通ずる手触りの名品を

十二月の先付は、柚釜をお出ししています。寒い中、お越しいただいたお客様にまずは暖をとってもらい、ほっこりと温まっていただくため。器は樂の九代目・了入の向付で、「柚味噌皿」の名がつく、柚釜のための器です。樂家の代々が手がけている器ですが、この赤樂は秀作だと思います。他はもっと表面がつるんとしているんですが、これは土に砂を混ぜて焼いているのか、ざらっとしているんです。
使っているうちに気づいたことで、作り手も意図していたことかも分かりませんね。触ると凸凹があって、それが味わい深く、柚子の皮面に通ずるものがあるんです。器だけで見ると地味ですが、柚子が1個入っただけでパッと華やかになり、黄色が映えます。
 先付/柚釜 器/柚味噌皿(樂 了入作)
先付/柚釜 器/柚味噌皿(樂 了入作)
向付——雪の中に佇む「福良雀」で「福」を呼ぶ

「福良雀(ふくらすずめ)」は丸々と膨らんだ雀の呼び名で、冬の寒さから身を守るために羽を逆立てて膨らませている雀のことを言います。この器はその姿を形にした向付で、おっとりとした福福しさが気に入っています。雪の中でじっと寒さに耐える過酷な環境にありながら、ふくよかな姿が豊かさや繁栄を感じさせることから縁起の良い鳥とされ、「福良雀」「福来雀」と書きます。
この器に何を盛ろうか、器をどう生かそうかと思った時、ふっと浮かんだのが「フグ」でした。フグは大阪の冬の風物詩とも言える魚で、ところによっては「フク」と呼ばれ、『本湖月』では「福」の字をあてています。
料理屋でフグを出すようになったのは最近のことで、私が修業した『𠮷兆』でも白子くらいで、てっさや焼きフグは出していませんでした。お客様から要望があれば専門業者から届けてもらう、料理屋の料理ではなかったんです。
薄造りや焼きフグをそのままお出しするのでは料理屋として芸がないと思い、造りは薄くへいだ身を霜降りにて細く切り、せん切りにした皮と合わせて素麺状の糸造りにしています。上には雪に見立て、裏濾した白子をかけ、上から香ばしく揚げた米をひと振りしてお出しします。これは、お腹を空かせた雀に、ご機嫌になってもらえるように。お供の器は、雀が雪の中にいると感じてもらえるように雪輪の小付を。でも、この趣向に気づかれるお客様はまずなく、お尋ねがなければ説明もしていません。
これは、私だけの器遊び。一人楽しんでいますが、器は喜んでくれているかも分かりません。側から見たら思い入れが強すぎて、なんとも痛い演出かもしれませんが(笑)。
続きを読むには
無料で30日間お試し※
- 会員限定記事1,000本以上、動画50本以上が見放題
- ブックマーク・コメント機能が使える
- 確かな知識と経験を持つ布陣が指南役
- 調理科学、食材、器など専門性の高い分野もカバー
決済情報のご登録が必要です。初回ご登録の方に限ります。無料期間後は¥990(税込)/月。いつでもキャンセルできます。
フォローして最新情報をチェック!