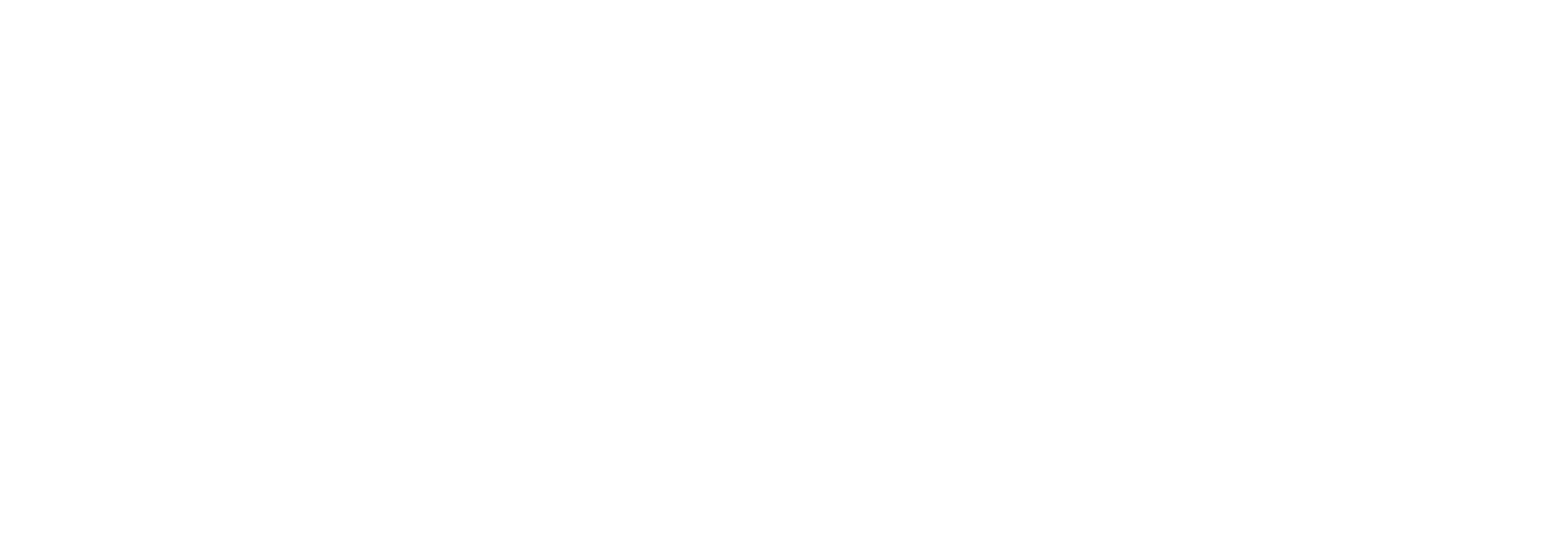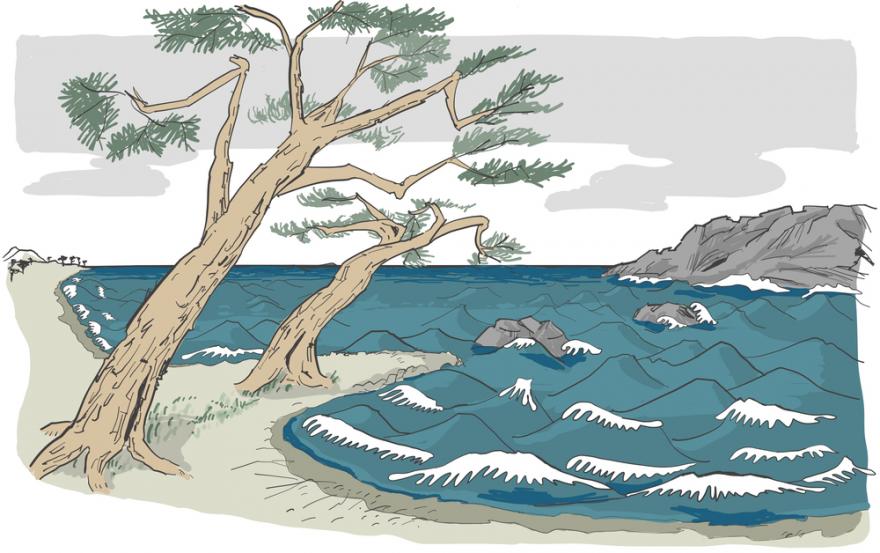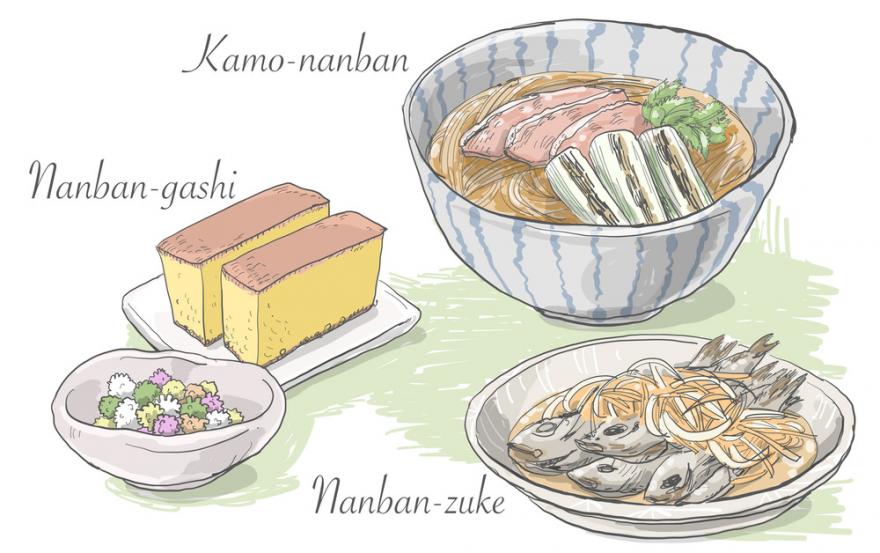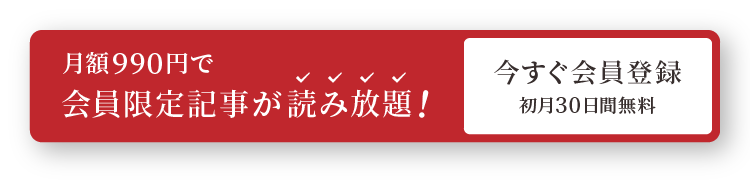おこわ【御強】
おこわは、もち米を蒸したものです。主に赤飯のことを言い、それ以外では栗おこわや山菜おこわなど、加えた具が分かるような名にします。漢字で書くと「御強」。元は「強飯(こわいい)」と呼ばれていましたが、室町時代の宮中の女官たちが「お」を付けて後ろを省略したようです。そして、その異名の方が一般化し、定着したのです。今回は、強飯の成り立ちを紐解きながら、女房たちの独特な言葉の世界へご案内します。

言葉の始まりは、室町時代朝廷に仕える女房(=宮中の女官)が、強飯を「御強」「御強供御(おこわくご※)」などの異名で呼んでいたことから。女房たちは特に衣食住に関わる言葉に関して、一種の隠語ともいうべき独特な言葉を用いていました。いわゆる女房詞(にょうぼうことば)です。
※「供御(くご)」は召し上がり物のこと
おこわは、言葉の頭に〈お〉をつけて、後ろを省略するという、女房詞の作り方の典型例です。ちなみに同様の例に、田楽の「おでん」、冷やし水の「おひや」、萩の餅の「おはぎ」があり、どれも一般化しています。
では、なぜ女房たちは、このような異名を用いたのでしょう。一説によると、庶民の食べ物が食膳にのぼるようになった際、同じ言葉を露骨に口にするのを避けたのが理由だとか。
室町時代前期の有職書『海人藻芥(あまのもくず)』(1420年)には、宮中ではすべての食べ物に異名を付けたこと、また将軍家の女房も異名を使ったことが書かれています。
当初は飲食物中心だったのが、衣・住などの範囲にも語彙を増やし、江戸時代になると裕福な町家の女性たちにも広がります。さらに、当時の標準語であった「上方ことば」にも入り込み、庶民文化の勢いと共に東京へ伝わって全国へ拡大。明治以降も受け継がれます。身につけるべき言葉遣いとして、世の女性がお手本にするようになり、一般の言葉として定着しました。
ところで、おこわの本来の名称である「強飯」は、なぜ「強(こわ)い」と表記されるのでしょう?
「強い」とは「硬い」という意味です。つまり、「強飯」の語意は「硬く仕上がったご飯」。そこには、蒸すという調理法が深く関係しています。
強飯の作り方は、甑(こしき)という底に孔(あな)があいた鉢型の器に米を入れ、湯を沸かした甕(かめ)の上に重ねて、蒸気で蒸(ふ)かすというもの。甑は古墳時代から現れる調理道具です。
平安時代の漢和辞書『和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』(931~938年頃)の項目には「古八伊比(こわいい)」という和名が記されており、解説文から蒸した米であると推察できます。
蒸した米には噛み応えがあったことから、次第に「強飯」と表現されるようになったのでしょう。また平安の末には、強飯に対して、炊いたご飯を「姫飯(ひめいい)」と呼んで用いていました。「姫」は「軟らかい」の意。このことからも、強飯が硬いご飯を意味していたと言えるでしょう。
さらに、現在は蒸すのはもち米、炊くのはうるち米がセオリーなので、もち米の食感も「強い」と表現される一因ではないか?とも考えられますが…。実は、昔から強飯=もち米であったとは断定できません。
ただ、平安の頃にはもち米の記録も確認されますし、女房たちが口にした強飯も、次第にもち米が定着していったと考えられます。
他の米より白く不透明で、搗(つ)くと餅になるのも特異。もち米は、普通の米とは異なる「特別な米」と見なされるようになります。
もち米の強飯は、ハレの食や重要な儀礼食の性質を強めていきました。その特別感が、赤飯をはじめとする現在のおこわの位置づけにも影響したのでしょう。このように、おこわは古くから続くご馳走なのです。
ちなみに、料理屋ではおこわを「飯(いい)蒸し」と呼ぶことがあります。よく使うのは、お凌(しの)ぎといって、コース仕立ての献立で小腹を落ち着かせる程度のものを出す時。合わせて覚えておくとよいでしょう。
※「辻󠄀調理師専門学校」の日本料理の先生によるレシピ「百合根と帆立のおこわ」はコチラから
フォローして最新情報をチェック!