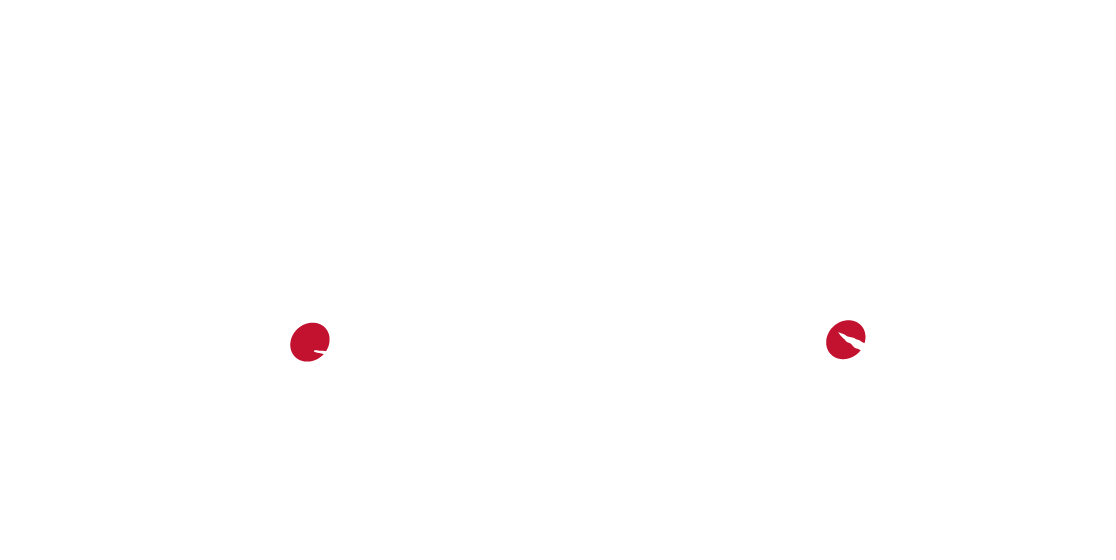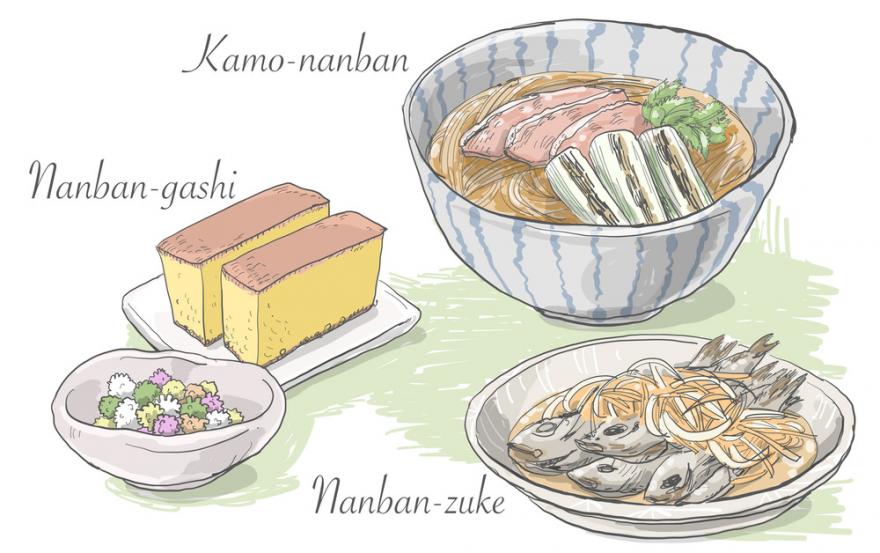旧暦9月9日「重陽の節句」の料理や器、設え
WA・TO・BIではこれまで、五節句のひとつ、旧暦9月9日の「重陽の節句」に関する記事をいくつか配信してきました。別名「菊の節句」であることから料理や器に「菊」を取り入れ、さまざまに表現。暦通り9月から、はたまた新暦の季節感に合わせて提供するなど、各店の考えによって提供期間が異なるのも参考になります。料理人に加え、古美術商、和菓子屋主人など、見識の高い方々の記事もピックアップします。※記事は配信当時のまま掲載。
大阪『柏屋』流、重陽のもてなし
大阪『柏屋』で提供する菊尽くしのコースから、重陽の節句のもてなしを主人の松尾英明さんに解説していただいた。菊尽くしのコースは、二十四節気の秋分〜霜降の前日に提供(記事を掲載した2022年は9/24~10/22)したものだ。
 撮影/ハリー中西
撮影/ハリー中西
Vol.1は器と設え編。菊をモチーフにした器が続々と登場する。色絵や蒔絵で葉や花をストレートに描き出したものもあれば、黄交趾(きこうち)や黄南京のように色合いで語る器、盃コレクションなど、実にバリエーション豊か。室礼も菊尽くしで、見るだけでも優美な気分になれる。
Vol.2は料理編。花を食材として使うほか、他の食材で花形を表現したり、色使いで菊を連想させたりするなど、さまざまな手法を駆使する。
「菊は時代ごとで捉えられ方が変わる興味深い存在」と語る松尾さん。菊酒と先付、煮物椀で表現するのは、不老長寿の妙薬として伝わった奈良時代。菊の高貴さに魅了された王朝貴族が歌を添えて競い合った平安時代の「菊くらべ」は造りで。八寸は、菊を愛でる文化が町衆にも広がった、江戸時代に盛んになった菊花壇に見立てた。
▼大阪『柏屋』流、重陽のもてなし Vol.1 器・設え編の記事はコチラ(2022年9月16日掲載)
▼大阪『柏屋』流、重陽のもてなし Vol.2 料理編の記事はコチラ(2022年9月17日掲載)
京都『梶 古美術』に教わる、菊の意匠について
京都『菊乃井』の村田知晴さんが『梶 古美術』の梶 高明さん・燦太さんから器について学ぶ連載。「菊の節句」にちなみながらも、季節を問わず使われる「菊の意匠」の知識を広く教わった。
 撮影/竹中稔彦
撮影/竹中稔彦
【前編】では、皇室の紋章である「菊の御紋」や「菊桐」の話、高貴で位が高いとされている水辺の菊(菊水)の文様のこと、【後編】では永楽の菊形鉢や北大路魯山人が造った菊割平向付など多彩な菊の器について。また、菊の器を使う際の注意点など、参考になる話を展開した。
▼菊の意匠【前編】の記事はコチラ(2023年8月29日掲載)
▼菊の意匠【後編】の記事はコチラ(2023年9月1日掲載)
京都『千本玉壽軒』の9月の和菓子
 撮影/岡森大輔
撮影/岡森大輔
中国から伝わった重陽の節句だが、日本独自の風習として根付いた「着せ綿」をテーマにした一菓。白の菊には黄色い綿、黄色ならば赤い綿、赤系には白い綿をかぶせるという決まりを踏襲しつつ、まだ夏のように暑い新暦の9月9日でも涼やかに感じられるよう、生地や仕立てを工夫している。季節の境目だからこそ施す、細やかな技にご注目を。
▼『千本玉壽軒』の9月の和菓子の記事はコチラ(2021年9月1日掲載)
大阪『本湖月』、菊のお道具と組合せの妙
 撮影/竹中稔彦
撮影/竹中稔彦
大阪『本湖月』では、新暦10月に菊の器でお客をもてなす。写真左は主人・穴見秀生さんが骨董屋に通いに通って手にした樂家四代・一入(いちにゅう)の作。この「菊平皿」と、同じ一入のもので深さのある「菊向付」の2種を使い、交互に提供。「開いた菊とつぼみの菊が並んでいるようで、その姿がまた素晴らしい」と話す。この他、永楽の菊の葉皿や菊蒔絵の椀などを使うという。
さらに、お座敷の床の間(写真右)には大阪を拠点に明治から大正期にかけ活躍した日本画家・菅 楯彦(すが たてひこ)の「紅菊」のお軸。「あまり菊づくしにはしたくないので、花は秋の風情に」と、バランスをとる。
▼大阪『本湖月』、菊の器と料理の組合せの妙の記事はコチラ(2021年10月8日掲載)
奈良『白(つくも)』の「器遊び」と「言葉遊び」
“世界No.1フーディー” 浜田岳文さんが、革新的な料理や店づくりに感銘を受けた和食店を巡る本企画。奈良『白』では「店主・西原理人(まさと)さんのストーリーテリング(物語を紡いで伝えること)が素晴らしい」と3回にわたってお届け。
Vol.2では、「ストーリーある料理の作り方」について対談を展開し、その中で西原さんが9月に提供している料理が登場。「白(つくも)の日 重陽の菊“白紫黄紅赤(はくしおうこうせき)”」という前菜で、発想は「器遊び」と「言葉遊び」から。
 撮影/Rina
撮影/Rina
菊の節句に飾る菊の生け花は、格の高い色「白紫黄紅赤」の順で活けるとされている。大根で作った白い菊、紫・黄の揚げたジャガイモ、紅大根……。最後の赤は、樂家・九代 了入の赤樂をもって、赤菊を表現している。
そして、9月9日を並べて書くと99、漢字で書くと九十九(つくも)。百から一を引いた『白(つくも)』の店名の由来でもある。重陽の節句と“『白』の日”が重なった、特別おめでたい日ということも一番上に白菊を咲かせている所以だ。
▼奈良『白(つくも)』の「器遊び」と「言葉遊び」の記事はコチラ(2023年11月30日掲載)
フォローして最新情報をチェック!