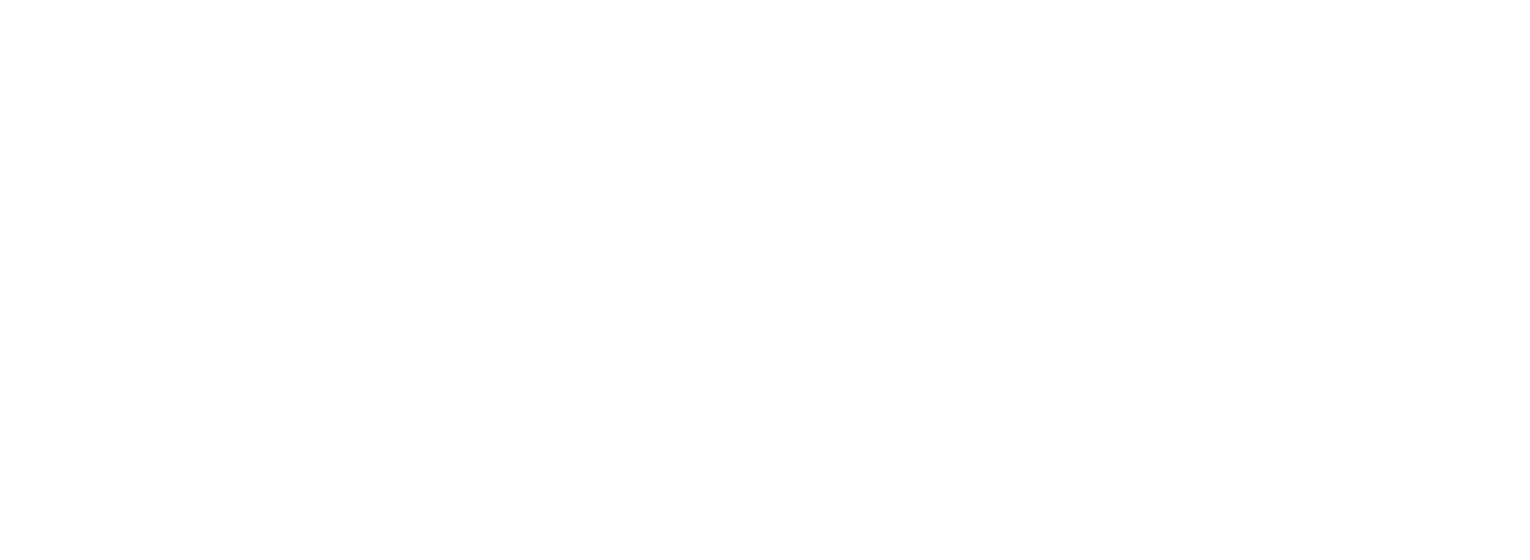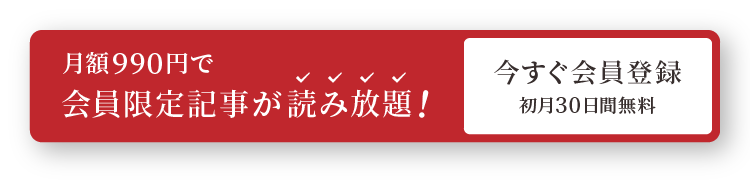「のと115」から厳選される超大型椎茸「のとてまり」
金沢から車で2時間ほど、石川県鳳珠(ほうす)郡能登町にある、田端二郎さんが原木椎茸を栽培するハウスを訪れた。途中、穴水で合流した「奥能登原木しいたけ活性化協議会」の脊戸(せと)大樹さんの案内がなければ、辿り着くのは難しかっただろう。
「今日は雪が少なくてよかったですね」とハウスの前で出迎えてくれた田端さん。取材に訪れたのは12月下旬、ちょうど数日前に能登は暴風雪に見舞われたばかり。雪が残る日本海を見下ろす台地に建つ4棟のハウスと隣接する木立の中に、椎茸の原木が萌芽の時を待ちながら整然と並んでいた。
田端さんが栽培しているのは「のと115」という、石川県の珠洲(すず)市・輪島市・穴水町・能登町の2市2町で作られている原木栽培のブランド椎茸。肉厚で弾力のある食感と旨み、香りが特長だ。さらに「のと115」の中でも特に大きく形のよいものは検査場に集められ、傘の大きさ8cm以上、厚み3cm以上、巻き込み1cm以上という厳格な規格を満たすものだけが、最高級ブランド「のとてまり」として認定される。
「今は出始めたばかりで数は少ないですが、年明けにはハウス内が椎茸でいっぱいになりますよ。今ある中では、これが『のとてまり』に認定されるかもしれませんね」と、田端さんは柄の先に小さなミラーがついた点検鏡を、ひときわ大きな椎茸の傘の下に当てて覗き込んだ。
「うん、傘の大きさも、巻き込みも充分ありそう」と言い、そっと愛しげに両手を添えて収穫する。その瞬間、数m先までふわりと芳香が漂ってきた。上品でやわらかな、椎茸の香り。摘みたての瑞々しさ、清々しさまで伝わってくる。これは食感だけでなく、火を入れたとき、口に含んだときの風味も期待を超えてきそうだ。
森の生命力を凝縮した、圧倒的な存在感と風味
収穫直後の「のとてまり」を炭火で焼いて試食することができた。七輪で炙り始めてしばらくすると、傘の内側に美しく並んだヒダに小さな水滴が浮かび、香気と湯気が立ち始めた。じっと見守り続けると、さらに旨みを湛えた水滴が溢れ、傘の外側からも溢れ出してくる。
タイミングを見計らって火から下ろし、熱々を根元から割く。分厚い傘の中心部は、ゼリーのように半透明で艶やかな乳白色。そこに溢れんばかりの旨みが詰まっているのが、見ただけで伝わってくる。今回はあえて調味料を付けず素焼きでいただく。
うまい。内面からの輝きが抑えきれないスターの原石に出合ったような感覚だ。肉厚な傘はほどよい弾力で歯切れがよく、噛むと芳醇な旨みが口中に広がる。香りは主張しすぎず品がよく、すっと鼻腔を抜け、穏やかな余韻が心地よく続く。
現地では「柄(あし)」と呼ばれる軸の部分はさらに弾力があり、傘とは違うしっかりした歯応えと凝縮した旨みがある。柄だけで主役の一品ができる存在感。刻んで真薯などに混ぜ込むのもいいかもしれない。
以前「能登とり貝」の産地ルポとレシピ紹介で登場いただいた、石川県七尾市の日本料理店『一本杉 川嶋』の川嶋 亨(とおる)さんも「のとてまり」や「のと155」は手を加え過ぎない調理法を勧める。
「ホイルで包んで日本酒と能登の塩、一滴の醤油で炭火焼きしたものが絶品。色気がないかもしれませんが、酒と塩だけでも悶絶の美味しさです。シンプルな炭火焼きが『のとてまり』の香り、食感などの魅力を一番に感じられる調理法」と言う。
炭火焼きやステーキのほか、天ぷら、吸い物、煮物、蒸し料理などでも主役を張れる逸品で、調理法には水分、香り、旨みを逃さない工夫が肝要だ。他の食材との相性もよく、マヨネーズや乳製品などともよく合う。和食はもちろん、イタリアンやフレンチ、スペイン料理などの地元シェフたちも注目している。
栽培の秘訣は、奥能登の風土とひと手間にあり
「のとてまり」は目を見張るほど大きい。一般的な菌床栽培と比べると、まるで大人と幼児といった具合だ。そして半球よりも巻き込んだ丸い姿、食べ応えのある太い軸はどうしたら生まれるのか。何か特別な品種なのだろうか──。
「全国で流通している『菌興(きんこう)115号』という品種ですよ。現在開発されているどの品種よりも肉厚で大型化しますが、石川県の『のと115』の『のとてまり』、鳥取県の『とっとり115』の『鳥取茸王(たけおう)』は、全国のジャンボ椎茸界でも特に大きく、質が高いことで知られています。能登の気候が適していたこともありますが、生産者の手間暇かけた栽培から違いは生まれているようです」と脊戸さん。
「まさに『山のアワビ』という例えがぴったり。こんなに美味しい椎茸は他にない。すっかり惚れ込んでしまい、自分自身が毎日食べたくて原木栽培を始めました」と田端さんは話す。
田端さんは地元JAの椎茸部会の部会長も務めるが、本格的に「のと115」の生産を始めたのはわずか5年前。現役の大工でもあり、持ち前の創意工夫と丁寧な仕事で、就農から瞬く間に頭角を現した。現在100名ほどいる生産者の中でも注目される優良生産者で、2020年度に「のとてまり」を最多生産した“椎茸の匠”だ。
「のと115」は干し椎茸もあるが、持ち味を最大限に味わえるのは12月から3月にかけて出荷される生椎茸。2021年度は産地全体で2.6万玉の「のと115」、約3000玉の「のとてまり」が出荷された。まだまだ希少で9割が石川県内の市場へ、残りが東京や関西などへ出荷され、主に飲食店で使用される。特に1玉数千円(時価)の「のとてまり」となると、お目にかかれるのは高級店やホテルなどになってくる。
原木椎茸栽培は、原木を育て、森を守り育てること
秋、山から伐採されたコナラは、枝付きのまま乾燥させ、水分が抜けると1mの長さに切り揃えられる。椎茸の素となる菌を植えるのは、2月から4月頃。春から秋にかけ、原木は屋外で恵みの雨を受け、暑さや風通しに気を配りながら管理され、11月にハウス内へと移される。ハウスは雪深い奥能登で降雪や温度変化などの影響を防ぐ効果があり、大きく形よく育てる上で欠かせない。
「5000本の原木を管理していますが、この中から『のとてまり』が発生するのはわずか。原木の太さにもよりますが、1本に30〜40の穴を開けて菌を植え付けます。夏を越した最初の冬に、穴から白い蓋を押し退けるように大型の椎茸が生え、穴の数の1割にあたる3、4本が『のとてまり』の候補。『のとてまり』に育つものは最初から大きく、傘になる部分がペットボトルのキャップや500円玉ほどあります」と田端さん。
乾燥を避けるため、芽が3cmほどに成長すると、一つ一つに袋がかけられる。ハウスは直射日光が当たらないよう70%に遮光され、スプリンクラーによる散水、扉の開閉などで気温や湿度が適切に保たれ、ゆっくり時間をかけて育てられる。
椎茸は低温系(春出)のキノコで、気温8℃以下で1週間の低温刺激が必要だ。露地栽培であれば3月頃から発生するが、ハウス栽培は初冬に屋外で低温刺激を受けた原木を暖かいハウス内へ移すことで、春が来たと勘違いさせて発生を早めている。また、原木をハンマーなどで叩いて刺激を与えると活性化する性質があり、原木の移動も椎茸の発生・生育を促進する刺激になる。
「ハウスに移すのは植菌して1年目から3年目の原木。『のとてまり』級が発生するのは1年目の原木で、2年目から発生数は増えるがサイズは大型化しにくくなります」と田端さん。4年目からはハウスに移し替えることなく露地栽培し、干し椎茸用に使っている。
5、6年目になると寿命を迎え、原木は山に還され土に戻る。椎茸の原木栽培は、年を通じて原木を育てることであり、里山の森とも密接につながっている。
ブランド椎茸「のと115」「のとてまり」誕生の背景
奥能登で椎茸の原木栽培が行われるようになったのは、今から60年ほど前のこと。平地が少ないため米作りが難しく、目ぼしい作物もないため、椎茸の原木栽培が苦肉の策として選ばれた。
当初は干し椎茸の生産が主で、今のように生椎茸が出荷されるようになったのは、道路が整備され交通の便がよくなってから。それまでは新鮮なうちに遠い消費地へ運ぶことができず、保存がきく干し椎茸に加工せざるを得なかったのだ。
1990年代から「菌興115号」を使った生鮮用に力を入れると、奥能登の風土との抜群の相性で上質な椎茸が採れるようになり、「のと115」のブランド化が進む。そのフラッグシップとして「のとてまり」がデビューしたのは2011年のこと。
もともと天然のキノコ類も多く生育する土地で、強い風が吹き抜け、適度な湿度と寒暖差が大きい気候が、椎茸の栽培に非常に適していた。田端さんのハウスがある場所も、海を見下ろす高台で立地が非常によかったという。
しかも、奥能登は昔から塩田の塩作りが盛んで、塩を煮炊きする薪や炭を得るための雑木林が豊富にあったことも幸いした。塩田の衰退や燃料の転換で炭の需要が減り、用途を失いかけていた雑木林が、椎茸の原木栽培で新たな活路を見出すことになった。
杉は切れば終わりだが、コナラなどの広葉樹は伐採しても脇芽が出て何度も蘇る。逆に、自然のまま放置するとナラ枯れを起こして朽ち、山全体が荒廃する。人が木の伐採や山菜採りで足を踏み入れることで、森は新陳代謝を繰り返すことができるのだ。
「のと115」「のとてまり」は、手間を惜しまぬ生産者のたゆまぬ努力の結晶であり、奥能登の人々が長い年月をかけて守り継いできた里山、広葉樹の森の恩恵であることを忘れてはならない。








「奥能登原木しいたけ活性化協議会」
【住所】石川県鳳至郡穴水町字平野3-2-3 JA全農いしかわ穴水事務所
【電話番号】0768-52-1240
【Facebook】https://www.facebook.com/nototemari
【Instagram】https://www.instagram.com/nototemari.noto115
フォローして最新情報をチェック!