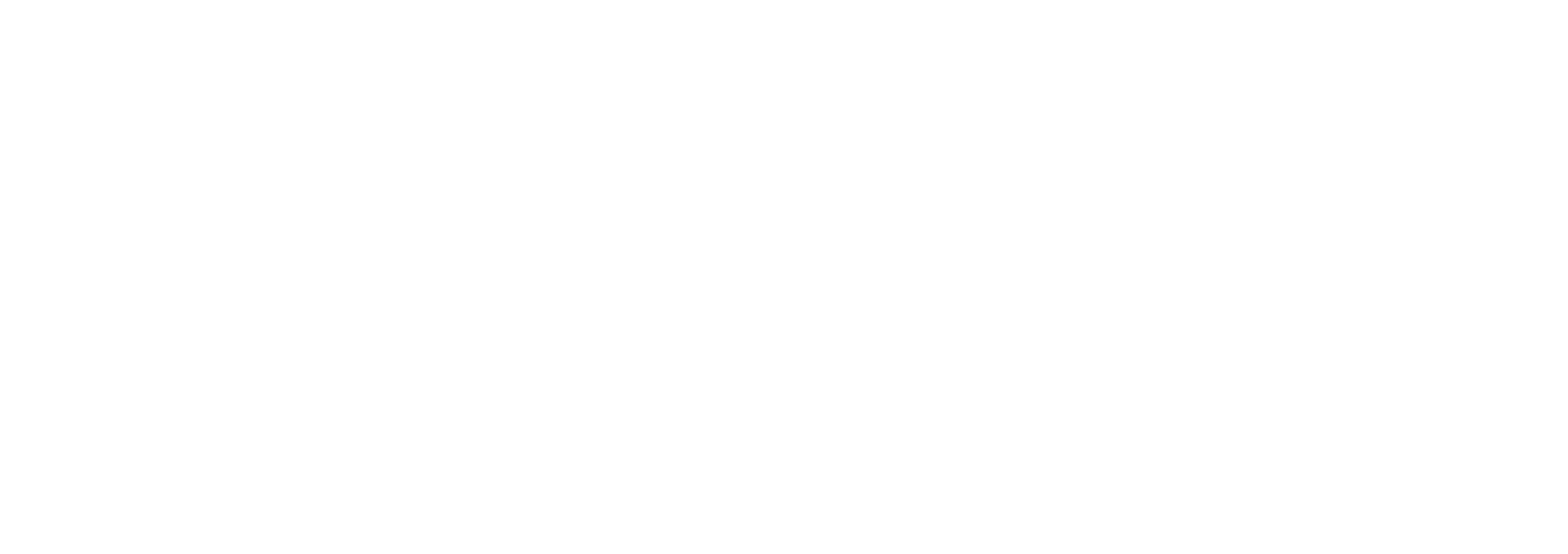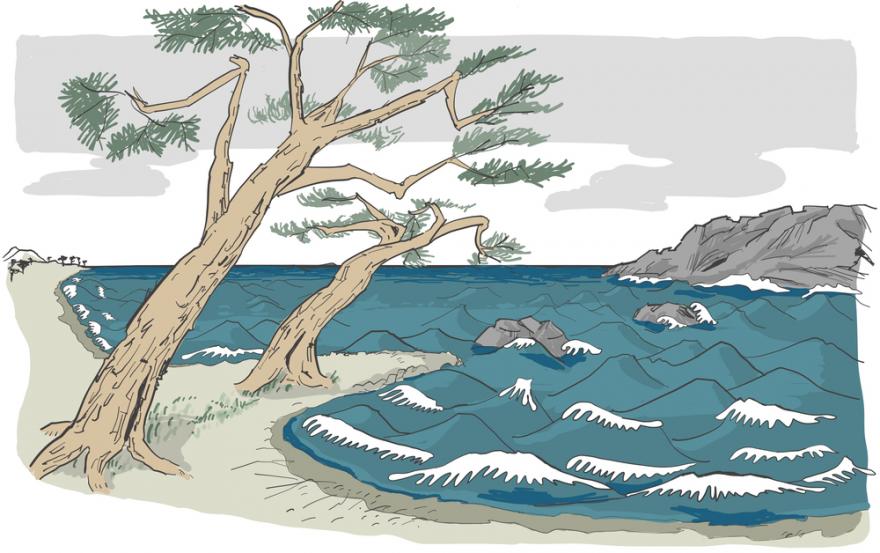料理人のためのソムリエ試験対策 Vol.2 一次試験対策前にすべきこと
なるべく最短で、今後のワイン人生を豊かにする「料理人のためのソムリエ試験対策」をソムリエの松岡正浩さんから学ぶ企画第2回目。今回は、一次試験対策前に知っておくべきこと、理想的な受験日程、今から行っていたら記憶の定着に役立つことを教わります。
-

-
松岡正浩(大阪・北新地|中国料理『有 伽藍堂(う がらんどう)』/シェフソムリエ)
兵庫県出身。山形大学に進学後、県内のホテルに就職。東京『タテル ヨシノ 芝』にて本格的にフランス料理の世界に入り、その後、渡仏。『ステラ マリス』を経て、パリの日本料理店『あい田』ではシェフソムリエとして迎えられた。帰国後、和歌山『オテル・ド・ヨシノ』にて支配人兼ソムリエを務め、2016年、日本料理『柏屋』へ。こちらでも支配人兼ソムリエを務め、ワイン・日本酒を織り交ぜたペアリングコースを提案。レストランガイド「Gault&Millau(ゴ・エ・ミヨ)2021」にてベストソムリエ賞受賞。2022~23年、京都・御所東のフランス料理『Droit(ドロワ)』においてギャルソンとして勤務。23年6月より、大阪・北新地の中国料理『有 伽藍堂』にてシェフソムリエを務める。
一次試験はいつ受験するべきか
前回、ソムリエ試験がどのような内容で、どの程度勉強しなくてはならないのかについてお伝えしました。半年くらいの努力なら頑張ってみようと思われた方、本当に素晴らしいと思います。
今回はソムリエ試験対策のメインともいえる、一次試験対策の取り組み方についてお伝えします。
一次試験は例年7月20日から8月31日まで開催され、その間に二度ご自身で受験日を決めることができます(ソムリエ呼称、ワインエキスパート呼称共通)。また、二次試験が10月上旬に(2024年度は10月7日)、三次試験は11月半ば(2024年度は11月18日、ソムリエ呼称のみ)に行われます。
そして、二次試験の日程を見据えて一次試験の受験日を検討するのですが、一次試験の一度目を7月末日までに、二度目を8月10日頃、遅くとも15日までに設定することがこれまでの経験上、最適です。
一次試験が始まり一週間ほどすると、その期間に受験した方の合否報告や感想がそれとなく聞こえてきます。近年、ソムリエ協会は一次試験問題漏洩(ろうえい)に対し厳しい措置をとっており、出題された問題そのものを確認することはできないかもしれませんが、「昨年より難しく感じた」「全くわからない問題もあったけど、基本問題をしっかり押さえただけで合格できた」など、実際に受験してきた方の生の声は精神的にも良い影響をもたらすはずで、一次試験開始一週間後に挑戦する意味があると言えます。
また、一度目を受験する時(7月27日前後がベスト)には一通り一次試験対策が終わっているという想定で、少し早めの意識で試験勉強を進めることで、より緊張感をもって暗記作業に取り組めるようになっていただきたいと思っております。
さらに、一度目で突破できなくても二度目の受験日まで約二週間あります。一度受験することで感覚をつかみ、なんらかの手ごたえを感じることでしょう。あやふやであった箇所や、確認不足であった項目を洗い出し、総復習することが可能です。
そして、早めの一次試験突破を目指すべき最大の理由は、テイスティング対策と論述試験対策にしっかりと時間を取る必要があるからです。テイスティング対策は一次試験対策と並行して必ず行うべきですが、一次試験を突破することによってより集中して取り組むことができます。また、論述試験対策はこの頃から始めて問題ありませんが、それでも「文章を書く」という人によっては日常的にあまり行わないことが求められるため、ここも時間をかけたいところです。
※前回もお伝えしましたが、論述試験は二次のテイスティングと同じ日に実施され、三次試験扱いとなります。
このような理由から、一次試験開始一週間後(7月27日前後)に一度目を、その約二週間後(8月10日前後)に二度目を設定することで、二次のテイスティング対策と、意外と難しい論述試験対策に二カ月ほど時間を費やすことができます。一方で、一次試験を最終日近くに突破した人は、この二つの対策を一カ月と少しで乗り越えなくてはなりません。
この差が合否を左右するとまでは言いませんが、しっかりと腰を据えて、特にテイスティング対策を行うことができれば、より合格に近づくというわけです。
注意が必要な事柄としては、出願日により一次試験の受験日受付開始時期が異なる点です。「3月1日から5月31日まで」と「6月1日から7月12日まで」にわかれており、前者の期間に申し込まなければ、希望する日程で受験できない可能性があります。
ですから3月中に、遅くとも4月に入った時点で出願すると常に意識しつつ、この頃には一次試験対策が軌道に乗っていることが合格の絶対条件と言えます。さらに、出願後よりペースを上げ、6月半ばからのラストスパートにつなげるというイメージで一次試験対策を進めていただきたいと思っております。
※この出願日についての詳細はソムリエ協会のホームページにてご確認ください。

一次試験対策はいつスタートする?
ということで、7月末の受験を目指し、一度で一次試験を突破するためにも、理想としては「お正月明け」を明確にスタートと決めて試験対策を始めましょう。
ご存知の通り、年末年始というのは特別な期間で、お正月は大きな節目でもあります。気分も新鮮で前向きな気持ちをもちやすい時期であり、新たに何かを始めるにはとても良いタイミングです。一方で、気持ちの良い分、そのままダラダラしてしまうと一月、二月はあっという間に過ぎてしまいます。
ですから、なんとしてもこの貴重なタイミングで、良いリズムを掴みつつ試験対策をスタートさせてください。受験すると決意し、周りの方に宣言したあと、次に大切なことが、このスタートです。
気持ちの良いスタートを切ることができると、その後も良いリズムを維持しやすいものです。反対にスタートでつまずいたり、一度勢いを失ってしまうと、そこから元に戻すことはとても難しいものです。
朝、いつもより一時間早く起きて勉強する。お昼と夜の営業の間に休憩が取れる方はその時間を利用する。夜、家に帰ってから机に向かう。また、通勤に電車やバスを利用される方はその時間にテキストを開く。
例えば、夜に勉強しようと考えている場合、日々のルーティン(食事やシャワーなど)を終えた直後、もしくはその前に“止まらず”に試験勉強を始めるんです。ちょっと休憩してからというのが一番ダメな流れで、一度止まってしまうとそこから動き始めるにはとてつもない労力を要します。反対に始めてしまえば、疲れていてもなんとかなることが多いものです。
生活様式は人それぞれですから、こうあるべきというものはありませんが、必ず決めたタイミングで物事を始めるように習慣化することが、労力を最小限に抑え、かつ最大の成果を挙げる方法の一つです。
確かに仕事をこなしながらの試験勉強はとてもつらいものです。机に向かってペンを取り、テキスト等を読むという生活から長らく離れていらっしゃる方も多いかと思います。ですから、最初は30分だけでもいいんです。勉強を終えてからのんびりしましょう。
行動科学においても「三日間続けば継続力がつき、三週間続けば習慣になり、三カ月間続けば結果となる」と言われており、この「習慣化する」ことがいかに大切かということをご理解いただけるかと思います。
お正月明けから試験対策を始め、毎日少しでも勉強する生活習慣を築くことが合否を左右すると言っても過言ではありません。

試験対策を始める前に、今できること
さて、スタート(お正月)まで数カ月あります。軽くウォーミングアップのつもりで、読みやすそうなワインの本を読んでみましょう。来年にはソムリエ有資格者になるわけです。ワイン本の数冊くらいは読んでおきたいものです。ですから、試験対策に入る前のこの時期に読むことをお勧めします。この時の経験が試験本番で役立つことがあるんです!
また、お店でワインを扱っている方はそれらのワインが、どの国のなんというブドウから造られたものか、そのブドウがどのような特徴を持っているのかまで調べてみましょう。ソムリエがいる場合は、それぞれのワインをなぜ選んだのかということも聞いてみましょう。
私は勉強に限らず、ある事柄をさまざまな側面から見ることがとても有意義であると考えております。ソムリエ試験対策も同じです。書物や日々の仕事、生活から得たワインの情報は、試験勉強を通して頭の中で整理され、系統立った知識となります。一方、勉強で得た知識は他の媒体(書籍、メディア、お店、知人との会話など)を通して見聞きすることで確実に理解が深まります。
ということで、ワイン本を読み始めましょう。そして、興味を持てるようになってきましたら、デパートやワインショップに出かけてみましょう。実際にワインを手に取って見ることはとても良い勉強になります。本物のエチケットを目の当たりにすることで強い印象を脳裏に焼き付けることになるからです。
しばらくして、一般の雑誌やテレビ等において、これまでは目にとまらず聞き流していたワインの銘柄や生産地名が飛び込んでくるようになればかなり前進している証拠です。
このように、試験対策に入る前のこの時期にワイン本を読むことによって、暗記作業が格段に楽になり、知識の定着率が上がります。また、ソムリエ呼称は論述試験が課されますが、その時にただ暗記しただけではない知識が大いに役立ちます。
さらに、細かいことは後回しにして、ワインを飲む機会を作りましょう。ワインなんてよくわからないからほとんど飲んだことがないという方もいらっしゃるでしょう。最初は飲み比べても違いなどわからないものです。美味しいと思わないかもしれません。
私はこの業界に入るまで、ほとんどワインを飲んだことがありませんでした。
二十数年前のある日、宴会場で働いていた私は披露宴で提供した赤ワインの残りをこっそり飲んでみました。
その時、「なんだ!! この渋くて酸っぱい微妙な味わいの液体は…」と、とても美味しいとは思えず、その何とも言えない感覚を今でも覚えております。
その時から私のワイン人生が始まったのですが、今ではワインが大好きになりました。
このような過程を経て試験対策を始め、その後、暗記やテイスティングしたワインの知識と経験が皆さんの血となり肉となっていくのです。
次回は、具体的な一次試験対策についてお伝えします。
▼料理人のためのソムリエ試験対策 他の回はコチラから
Vol.1 概要編
Vol.3 一次試験対策の準備と春先までの勉強法
Vol.4 一次試験対策、教本と過去問を利用した勉強法
Vol.5 二次試験対策の準備
Vol.6 二次試験対策として意識すべきワインについて
Vol.7 テイスティングして書き留める
Vol.8 ワインの酸とアルコール
Vol.9 主要白ブドウ品種の特徴
Vol.10 主要黒ブドウ品種の特徴 その1
Vol.11 主要黒ブドウ品種の特徴 その2
Vol.12 ラストスパート!一次試験前二ヶ月間の一次試験対策
Vol.13 二次試験を意識したテイスティング
Vol.14 白ワインを3つのタイプに分ける
Vol.15 赤ワインのタイプ分け
Vol.16 二次のテイスティング対策最終章~「模範テイスティングコメントを暗記する」
Vol.17【最終回】三次試験・サービス実技対策
フォローして最新情報をチェック!