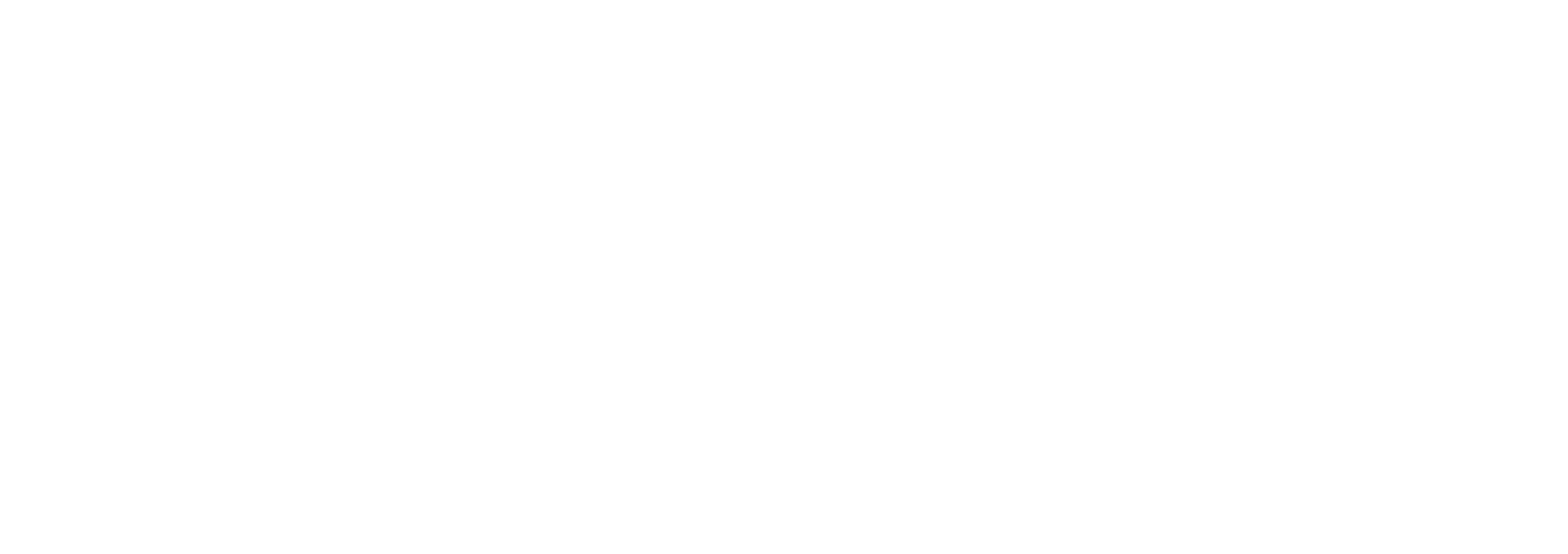料理人のためのソムリエ試験対策 Vol.5 二次試験対策の準備
ソムリエの松岡正浩さんから学ぶ「料理人のためのソムリエ試験対策」第5回目は、いよいよ二次試験のテイスティングについてです。今回は、二次試験対策に挑むための心構えと、事前に読んでおきたいオススメの本をご紹介します。
-

-
松岡正浩(「合同会社 まじめ2」代表 / 大阪・北新地「空心 伽藍堂」シェフソムリエ)
兵庫県出身。山形大学に進学後、県内のホテルに就職。東京『タテル ヨシノ 芝』にて本格的にフランス料理の世界に入り、その後、渡仏。『ステラ マリス』を経て、パリの日本料理店『あい田』ではシェフソムリエとして迎えられた。帰国後、和歌山『オテル・ド・ヨシノ』にて支配人兼ソムリエを務め、2016年、日本料理『柏屋』へ。こちらでも支配人兼ソムリエを務め、ワイン・日本酒を織り交ぜたペアリングコースを提案。レストランガイド「Gault&Millau(ゴ・エ・ミヨ)2021」にてベストソムリエ賞受賞。2022~23年、京都・御所東のフランス料理『Droit(ドロワ)』においてギャルソンとして勤務。23年6月より、大阪・北新地の中国料理『有 伽藍堂』にてシェフソムリエを務める。
ワイン初心者でも合格できる!
皆さんが一次試験以上に不安を抱いているかもしれない二次試験のテイスティング。でも、ご心配なく。ソムリエ試験合格レベルであれば、なんとかなります。実際にワイン名はおろか、極論すればブドウ品種を当てる必要もありません。これまで、ワインをほとんど飲んだことがない方でも大丈夫です。
今回は二次試験として行われるテイスティング対策についてお伝えします。
テイスティング試験の概要
例年、10月前半から中旬に実施される二次試験は、一次試験を突破した方が対象です。グラスに注がれたワインやリキュール類をその場でテイスティングしながら解答するスタイルで進められます。
二次試験会場は主にホテルなどの宴会場で、細長いテーブルが数十から百ほど整然と並べられており、事前にテイスティングアイテムが卓上に準備されています。受験者は受験票に記載された番号の席に座るように指示され、定刻になると試験が一斉に開始されます。
解答はマークシート方式で、ワインに関しては以下の4つのカテゴリーからさらに細分化された各項目について100以上のマークを、リキュール類は名称のみを選択肢から選ぶように指示されます。
【ワインの評価】
・外観
・香り
・味わい
・総合評価
直近20年の出題パターンは以下の通りです。
【ソムリエ呼称】
・ワイン3種(白・白・赤または白・赤・赤)
・リキュール類2種
【ワインエキスパート呼称】
・ワイン4種(白・白・赤・赤)
・リキュール類1種
また、ソムリエ呼称の受験者のみ、テイスティングの後に論述試験(三次試験対象)が課されます。
二次のテイスティングは難しくない!
二次試験のテイスティングはそれほど難しいことが問われるわけではありません。出題されるブドウ品種や解答パターンもおおよそ決まっているため、より特化した対策が可能です。
目隠しでワインを飲み、100%“当てられる”人は漫画やドラマの世界の話であり、実際にソムリエコンクールの決勝等においても、出場者達が正解を大きく外すことは珍しくありません。
また、香りに敏感だとか味覚に優れているという必要も全くありません。もし特別な能力を問われるのであれば、これまでに数万人もの合格者がいるはずはないでしょう。少なくとも二次のテイスティングレベルであれば、半年程度の努力でなんとかなります。
テイスティングも独学可能
さて、それほど難しくないとは言え、実際にワインをテイスティングし、経験を積むことを避けては通れません。一方で、「テイスティングしなさい」と言われても、これまで経験の少ない方にとっては、何をどう始めてよいのかわからないものです。
ワインスクールに通うことができれば、一次試験対策以上に体系的にかつ効果的に学ぶことができます。ワインの感じ方やコメントの基準などは独学ではなかなか習得が難しいからです。
私がソムリエ試験を受験したのは20数年前、当時は地方都市に住んでおり、近くにワインスクールはありませんでした。職場はホテルの宴会場で、披露宴で提供していた安価なワインにふれる機会はあったものの、日々ワインに向き合いながらテイスティングできる環境ではありませんでした。さらに、インターネットも普及しておらず、情報を得る手段がほとんどなかったため、よくわからないまま自宅で一人黙々とワインが見えないように部屋を真っ暗にしてグラスを傾けては首をかしげておりました。
振り返れば、受験当時の私はテイスティングに関して何もわかっていませんでした。結局、そのわからないまま受験会場に足を運びましたが、なんとか合格することができました。そして、合格した時に「この程度でいいんだ」と思ったものです。
現在はテイスティング対策に関しても様々な情報がインターネット上に公開されており、私の時代のようにほぼ手探りで独学ということはなくなったように思います。また、ソムリエ有資格者の数も飛躍的に増えました。私の頃は5000人に満たないくらいでしたが、今や、多くの飲食店にソムリエが在籍しており、料理人でソムリエ資格を持つ方も増えております。おそらく、身近に一人や二人ソムリエ有資格者がいると思われますので、困ったことやわからないことがあれば聞いてみることもできるはずです。
私はここ10数年にわたってテイスティングの指導を行ってまいりました。そして、独学で合格された方々をたくさん見てきました。その中には地方にお住まいで、ワインスクールに通えない人も多数含まれております。 多くの料理人はワインスクールに定期的に通う時間的余裕がないと思われます。それでも、半年間、正しい方法でしっかり努力すれば、テイスティングも独学で十分に合格を目指すことができます。
二次のテイスティングにおける重要な2つのポイント
最も意識すべきポイントは大きくわけて二つです。
1.ワインのタイプわけ
白ワイン、赤ワインをそれぞれ2~3のタイプに分類することです。
例えば、白ワインの場合、「柑橘のニュアンスやハーブ的な香りが主体の爽やかなタイプ」なのか、「甘い果実や花の香りが主体の華やかなタイプ」のどちらかに振りわけるといったイメージ。白ワインの場合、この2種のタイプの違いを理解するだけで、ひとまずOKです。
主要ブドウ品種数種の特徴を理解することは必須ですが、試験においてブドウ品種を当てなければいけないというわけではありません。例年、ブドウ品種正解ゼロで合格する方が多数いらっしゃいます。
2.ワインの各コメント(解答)を「用語選択用紙」から選択できるようになる
解答は、ソムリエ協会が準備した「用語選択用紙」から選び、マークシートに記載する形式で行われます。つまり、ご自身の感覚や印象ではなく、ソムリエ協会が正解と定めたコメントを適切に選ぶ必要があるということです。
テイスティングにおいて、感じたことを自分の言葉で表現することと、準備された用語の中から適切なものを選択することは全くの別物です。この点を理解した上でテイスティング対策を進める必要があります。
試験の時間配分として、ソムリエ呼称で40分、ワインエキスパート呼称で50分となっており、外観・香り・味わいなど約100項目をマークしなくてはなりません。そのため、二次試験直前には、用語選択の訓練を繰り返すことが重要になります。
二次のテイスティング対策はこの「ワインのタイプわけ」と「ソムリエ協会の求めるコメントを適切に選択する」ことに尽きると言っても過言ではありません。
そして、ポイントをこの二つに絞ることによって、二次のテイスティングがより試験的に攻略可能になります。過去の出題傾向を踏まえて、ある程度パターン化することができるからです。
そして、まず最初に取り組むべきは、「ワインのタイプわけ」ができるようになるための訓練です。この件に関しては、次回詳しくお伝えいたします。
テイスティング対策のおすすめ本
具体的なテイスティング対策に入る前に、読んでいただきたい本を数冊ご紹介いたします。
まずは、前回もご紹介した受験者必読の書、ソムリエ協会副会長の石田 博さんのこちらの本です。
「10種のぶどうでわかるワイン」(日経BPマーケティング)
二次試験における最重要ポイントの一つ、「ソムリエ協会の求めるコメントを適切に選択する」についての考え方の指針が述べられています。本書では、ベリー系の香りを例に取りながら、ブルーベリー、カシス、ブラックベリー、ブラックチェリーといった香り(コメント)が赤ワインの強弱とどう関係しているかについて、ソムリエ協会の視点に基づいて丁寧に解説されています。
これらのコメントの持つ意味を理解することが、二次試験突破の鍵となります。
本書を繰り返し読み込み、著者である石田さんが伝えたいポイントを理解し、コメント選択の基準を持てるよう意識しましょう。
続きまして、テイスティング対策おすすめ3冊のご紹介です。
・「ワインテイスティング―ワインを感じとるために」佐藤陽一著(アム・プロモーション)
・「最新版 ワインテイスティングバイブル」谷宣英著(ナツメ社)
・「ワインテイスティングの基礎知識」久保 將著(Kindle版、新星出版社)
これらの本はいずれも、トップソムリエやワイン業界のエキスパートによって執筆されており、テイスティングについて丁寧にわかりやすく解説されています。
とはいえ、テイスティングを言葉で学ぶことは容易ではありません。本来、香りや味わいは体感すべきものであり、著者または言葉との相性がとても重要になります。ですから、2~3冊購入して読み比べてみてください。それぞれの本から「腑に落ちる言葉」を少しずつ拾い上げることで、確実に学びが深まります。そして、それらを少しでも多く積み重ねることができれば本の価格など安いものです。
また、初めてテイスティングを学ぼうという方は、最初からすべてを理解する必要はありません。むしろ、最初はワインの世界をざっくりとイメージするだけで十分です。慣れない表現や未知のコメントに出会っても、立ち止まらずに読み進めることがとても大切です。「わからなくても大丈夫」「また戻って確認すればいい」と思えば、気持ちも楽になります。
試験対策に限らず、学びの基本は「進むこと」です。完璧を目指すより、一歩一歩積み重ねることを大切にしましょう。
これらの本を読めばおわかりいただけると思いますが、ワインのテイスティングに特別な能力は必要ありません。特にソムリエ試験に合格するレベルの利き分けなら誰でもそれなりの努力で成し得るものです。
次回は具体的にテイスティング対策として何をすべきかというところから続けたいと思います。
▼料理人のためのソムリエ試験対策 他の回はコチラから
Vol.1 概要編
Vol.2 一次試験対策前にすべきこと
Vol.3 一次試験対策の準備と春先までの勉強法
Vol.4 一次試験対策、教本と過去問を利用した勉強法
Vol.6 二次試験対策として意識すべきワインについて
Vol.7 テイスティングして書き留める
Vol.8 ワインの酸とアルコール
Vol.9 主要白ブドウ品種の特徴
Vol.10 主要黒ブドウ品種の特徴 その1
Vol.11 主要黒ブドウ品種の特徴 その2
Vol.12 ラストスパート!一次試験前二ヶ月間の一次試験対策
Vol.13 二次試験を意識したテイスティング
Vol.14 白ワインを3つのタイプに分ける
Vol.15 赤ワインのタイプ分け
Vol.16 二次のテイスティング対策最終章~「模範テイスティングコメントを暗記する」
Vol.17【最終回】三次試験・サービス実技対策
フォローして最新情報をチェック!