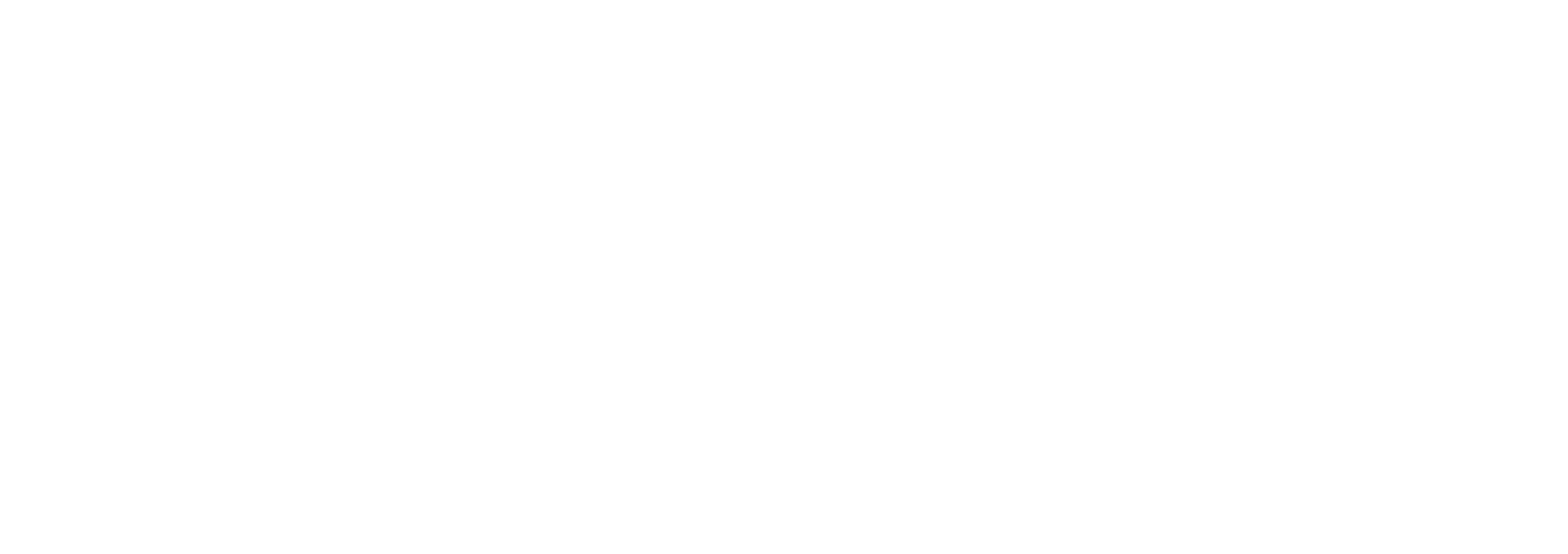料理人のためのソムリエ試験対策 Vol.4 一次試験対策、教本と過去問を利用した勉強法
「料理人のためのソムリエ試験対策」をソムリエの松岡正浩さんから学ぶ企画4回目。今回は、試験対策に必須といえる過去問の攻略、ソムリエ教本をうまく使っての勉強法についてお教えいただきます。
-

-
松岡正浩(「合同会社 まじめ2」代表 / 大阪・北新地「空心 伽藍堂」シェフソムリエ)
兵庫県出身。山形大学に進学後、県内のホテルに就職。東京『タテル ヨシノ 芝』にて本格的にフランス料理の世界に入り、その後、渡仏。『ステラ マリス』を経て、パリの日本料理店『あい田』ではシェフソムリエとして迎えられた。帰国後、和歌山『オテル・ド・ヨシノ』にて支配人兼ソムリエを務め、2016年、日本料理『柏屋』へ。こちらでも支配人兼ソムリエを務め、ワイン・日本酒を織り交ぜたペアリングコースを提案。レストランガイド「Gault&Millau(ゴ・エ・ミヨ)2021」にてベストソムリエ賞受賞。2022~23年、京都・御所東のフランス料理『Droit(ドロワ)』においてギャルソンとして勤務。23年6月より、大阪・北新地の中国料理『有 伽藍堂』にてシェフソムリエを務める。
試験対策の定石は過去問の攻略
今回はより具体的に、何を意識してどのように勉強すると良いのか、また、試験対策終盤に向けての気持ちの持ちようについてお伝えします。
なによりもまず、ソムリエ試験合格を目指しましょう。ワインがわかるようになるとか、お客様とワインの話ができるようになるとか、そのようなことは後回しで。ソムリエ資格を取得することで見えてくる事がら、つながる世界がありますから。
ということで、試験問題が解けるようになることが最優先。ソムリエ試験に限らず試験対策において効果的なのは過去問主体の学習です。過去の出題傾向を把握し、数多く取り上げられてきたテーマに絞って対策を進めることが定石といえます。公認会計士の友人も「過去問を徹底的に攻略することが合格への最短距離」と言っておりました。レベルは違うんでしょうけど。
正直、半年くらい勉強したからといって、ワインがよくわかるようになるわけではありません。しかし、それでもソムリエ試験に合格できるレベルには到達することができます。ですから、真正面から分厚い教本に取り組むよりも、出題頻度の高い項目に絞って効率よく暗記することを目指しましょう。過去問を活用しながら、知識の定着を図り、試験に対応できる力を養います。
この学習法が、最少の努力でソムリエ有資格者になる最短の方法であると私は考えております。そして、前回紹介した「ちょっとまじめにソムリエ試験対策こーざ(以下こーざ)」はその最短距離を進めるように構成されています。
過去問を通して、暗記の定着を図る
「こーざ」は「フランス・ボルドー」や「ギリシャ」などのテーマごとに、過去に出題された試験問題をもとにまとめた要点が、二日に一度のペースで更新されます。そして、必要な箇所には解説が加えられています。さらに、各回の最後には、公開されていた時代の過去問やCBT試験以降の想定問題が十数問掲載されており、実践的な対策を講じることができるようになっています。
その回の要点に目を通し理解しつつ、その文字列を絵的なイメージとして目に焼き付けるように努めてください。(もちろん、一度や二度で覚えることはできないと思いますが…)。そして、その後すぐにその覚えたてのイメージをもって過去問や想定問題に挑戦してみるんです。なお、正解は掲載されていない為、わからない問題があれば、解説やテキストに戻って確認する必要があります。
私はこの答えのない過去問や想定問題に大いに意味があると考えています。一次試験対策はとにかく暗記が中心で、その量も膨大です。簡単に頭に入るものではなく、覚えては忘れ…の繰り返し。しかし、何かきっかけがあったり、苦労して覚えた事がらは忘れにくいものです。
問題を解いている時に「わからない」「えっと、何だっけ?」と思うことは、その事がらに対して意識を強く向けている状態です。そのため、その後、解答にたどり着いた後の記憶の定着率が格段に高まります。暗記のために字面を追ったり、書きなぐっている時とは頭の働き方が全く違うからです。
また、どれだけ調べても解答がわからない場合は無理に解決しようとせず、いったん放置しても問題ありません。潜在意識は私たちが気づかないうちにも、そのような事がらを意識し続けていると言われています。そして、時間が経ち何らかの形で解決した時に単なる暗記を超えた深い知識や理解につながるものです。
このように過去問や想定問題を利用して、暗記作業を進めてください。繰り返し、問題を解くことで記憶の定着率がどんどん上がり、一次試験突破に近づきます。
ソムリエ教本を手に入れたら
3月に入り、ソムリエ教本を手にしたタイミングでギアを一段上げ、これまで以上に試験対策に時間を取れるよう生活スタイルを改善しましょう。
そして、ここからはソムリエ教本中心の学習スタイルに切り替えます。とはいえ、分厚い教本を最初から読む必要はありません。1月から始めた「こーざ」や、参考書、他の媒体等、そのまとめられている要点を教本に反映させていきます。蛍光ペンでも赤ペンでもよいので、重要箇所を目立つようにマークしていく作業を始めてください。
さらに、復習をかねて教本を手に入れる前に勉強していた項目にも、同様にマークを付けていくようにしましょう。
もう一つのポイントとして、教本の各生産国の最初に記載されている「プロフィール」だけはサラッと読んでからその国の勉強に取り組みましょう。その生産国の特徴や全体像をつかみ、イメージを持って学習に入ることで、より理解が深まると思います。
以降はこの繰り返しです。「こーざ」や参考書の要点を教本にマークし、その後、過去問や想定問題に挑戦しながら確認し、暗記していく。このプロセスを一次試験対策の該当範囲全般にわたって行います。並行して、復習にも力を入れなくてはいけません。一度や二度の学習で全てを覚えられる人はいないんですから。
6月半ばからのラストスパート
一次試験開始の1カ月と少し前、6月半ばからが一番の頑張り時。時には睡眠時間を削ってでも、集中して試験対策に取り組まなければならない本気モードに突入する時期です。
ここまでなんとかたどり着いた方は、ソムリエ試験に向けて多くのワインの知識を身につけてきたことでしょう。最初は全く意味を成さなかった横文字が、半年近く学習を続けたその頃には、少なくともワインを表す言葉として理解できるようになっているはずです。
そして、このタイミングで教本の各生産国の「プロフィール」を改めてしっかりと読み込むことがとても重要です。読み進めながら、これまで勉強した内容が自然とまとまり、腑に落ちるような感覚を得られるようになれば、一次試験突破はもう目前です。
また、CBT方式の一次試験になって以降、この「プロフィール」を読んだおかげで、試験中にわからなかった問題も何とかなりました!という報告も多く寄せられています。
ということで、6月半ばから一次試験対策のラストスパート。この時期は寸暇を惜しんで、全力でソムリエ試験に向き合わなくてはいけません。
最後に
ほとんどの方が、学生時代と比べて「記憶力が落ちている」と感じるはずです。まるでザルで水をすくうかのように、覚えたはずの事がらがどんどん抜け落ちていく感覚に悲しくなることもあるでしょう。私も経験したのでよくわかります。
それでも、合格するためには慣れない試験勉強を続けなくてはなりません。そして、最後まで「あきらめなかった」方だけがソムリエ資格を手に入れるのです。
繰り返しますが、合格する為に大切なことは、自身で決めたルーティン通り、テンポ良く勉強を始めるよう習慣付けること。それらを毎日、明日ではなく今日頑張ることです。だって、その日にやらない人は次の日もやりませんから。
次回は、この一次試験対策と並行して始めてほしいテイスティング対策についてお伝えします。
▼料理人のためのソムリエ試験対策 他の回はコチラから
Vol.1 概要編
Vol.2 一次試験対策前にすべきこと
Vol.3 一次試験対策の準備と春先までの勉強法
Vol.5 二次試験対策の準備
Vol.6 二次試験対策として意識すべきワインについて
Vol.7 テイスティングして書き留める
Vol.8 ワインの酸とアルコール
Vol.9 主要白ブドウ品種の特徴
Vol.10 主要黒ブドウ品種の特徴 その1
Vol.11 主要黒ブドウ品種の特徴 その2
Vol.12 ラストスパート!一次試験前二ヶ月間の一次試験対策
Vol.13 二次試験を意識したテイスティング
Vol.14 白ワインを3つのタイプに分ける
Vol.15 赤ワインのタイプ分け
Vol.16 二次のテイスティング対策最終章~「模範テイスティングコメントを暗記する」
Vol.17【最終回】三次試験・サービス実技対策
フォローして最新情報をチェック!