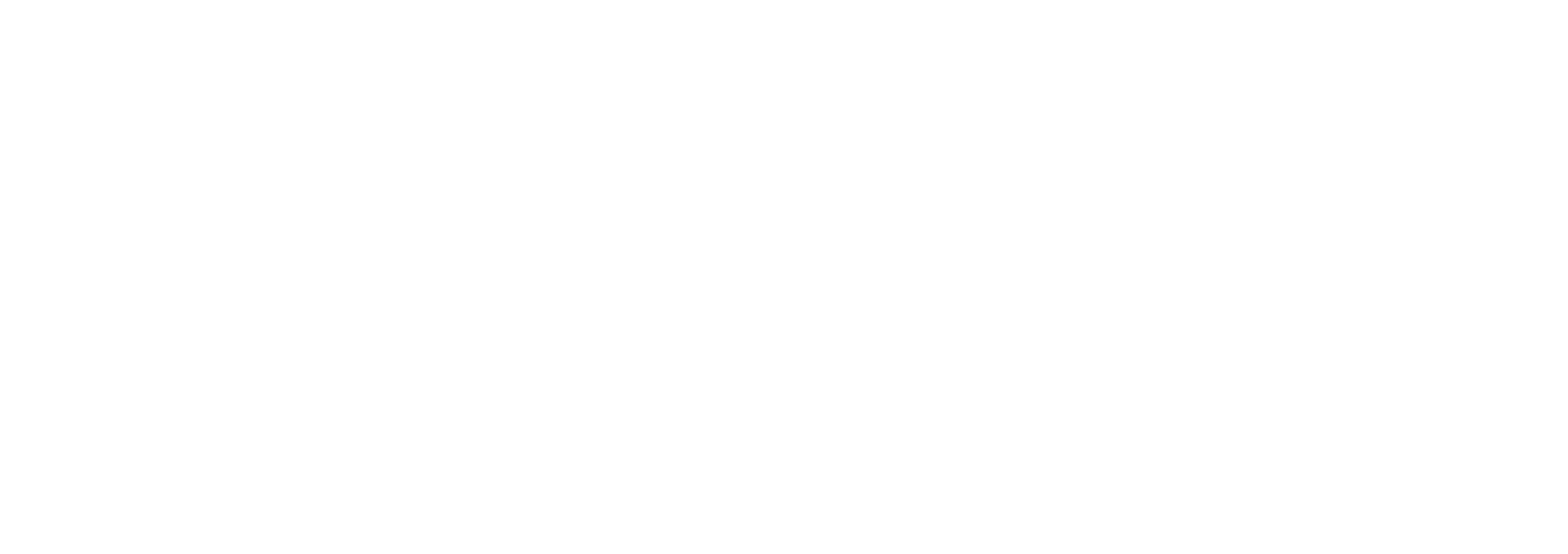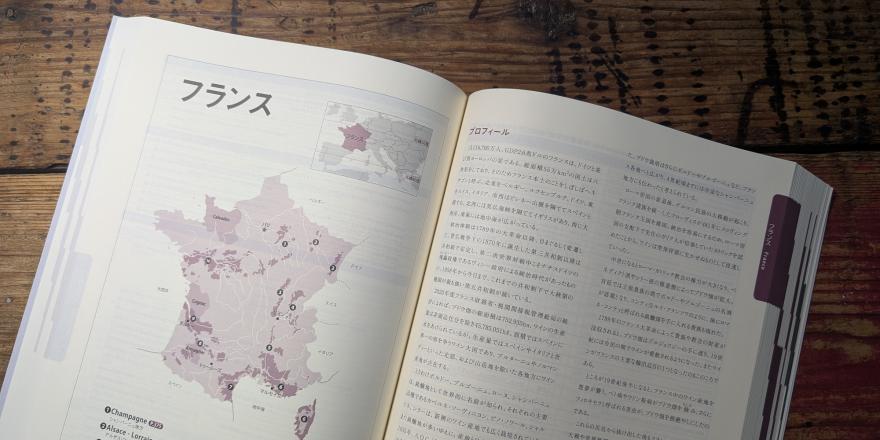料理人のためのソムリエ試験対策 Vol.15 赤ワインのタイプ分け
ソムリエの松岡正浩さんから学ぶ「料理人のためのソムリエ試験対策」。第15回目は、二次試験の赤ワイン攻略法について。前回の白ワインと同様、「外観」→「香り」→「味わい」の順でタイプ分けすることにより、着実に得点に繋げることができます。今回の判断基準を意識しながら、練習しましょう。
-

-
松岡正浩(「合同会社 まじめ2」代表 / 大阪・北新地『空心 伽藍堂』シェフソムリエ)
兵庫県出身。山形大学に進学後、県内のホテルに就職。東京『タテル ヨシノ 芝』にて本格的にフランス料理の世界に入り、その後、渡仏。『ステラ マリス』を経て、パリの日本料理店『あい田』ではシェフソムリエとして迎えられた。帰国後、和歌山『オテル・ド・ヨシノ』にて支配人兼ソムリエを務め、2016年、日本料理『柏屋』へ。こちらでも支配人兼ソムリエを務め、ワイン・日本酒を織り交ぜたペアリングコースを提案。レストランガイド「Gault&Millau(ゴ・エ・ミヨ)2021」にてベストソムリエ賞受賞。2022~23年、京都・御所東のフランス料理『Droit(ドロワ)』においてギャルソンとして勤務。23年6月より、大阪・北新地の中国料理『空心 伽藍堂』にてシェフソムリエを務める。
主要黒ブドウ品種の特徴を把握した上で、最終的に赤ワインも3つのタイプに分類できるようになることを目指します。
赤ワインの外観は白ワイン以上にブドウ品種や熟成による差が顕著に現れるため、二次のテイスティングにおける大きなポイントとなります。
外観で「淡い系」か「濃い系」かを判断し、その先をイメージしつつテイスティングを進めます。そして、どこかで大いなる違和感を覚えた時のみ、3つ目のタイプを検討するという手順です。赤ワインは構成要素がより複雑なので、シンプルな考え方が有効です。
赤ワインの3タイプ
①「淡い系」の色調で赤い果実が主体の華やかなタイプ
該当主要品種:ピノ・ノワール、ガメイ、マスカット・ベーリーA
色調は淡く、グラスの向こう側の文字が透けて見えます。ピノ・ノワールならいいなと願いつつ、赤い果実の華やかな香りと奥行きのある余韻が続けば確定的。もしかすると、ガメイやマスカット・ベーリーAの可能性もありますが、香りと味わいはより単調です。
②「濃い系」の色調で黒い果実が主体の複雑で力強いタイプ
該当主要品種:カベルネ・ソーヴィニヨン、シラー/シラーズ
紫から黒に近い濃い外観。黒果実主体の若々しく複雑な香りとしっかりとした骨格が特徴。そして、この流れで違和感を覚えなければ、他のブドウ品種を検討する必要はありません。このタイプに属するメルロ、マルベック、グルナッシュなども出題されてきましたが、これまでほとんどの受験者がブドウ品種を答え切れていないことを考えると、無視して進めた方が悩む時間も無駄にならず効率的です。
③フレッシュな果実味以上に土っぽさや熟成感が前面に出る「熟成系」タイプ
該当主要品種:ネッビオーロ、サンジョヴェーゼ、テンプラニーリョ
外観でちょっと違和感…。「淡い」けど、どこかくすんだ印象で若々しいとは思えない時はネッビオーロの可能性があります。「淡い」とも「濃い」とも言い切れない微妙な色調のワインも多く、「濃い系」に分類されるものもあります。ワインのエッジ(ワインの液面がグラスに接する縁の部分)に赤みを帯びていることが多いです。
香りは赤果実や黒果実と判断する以前に、そもそもフレッシュな果実香がしない、少ない。加えて、どことなく土っぽく、独特の強さ、ひねた感じを大いなる「違和感」ととらえた時にのみ検討します。最初から想定する必要はありません。
【外観】~「淡い系」or「濃い系」の二択からスタート
Vol.13にてお伝えした通り、試験会場では入場時やオリエンテーション時にテーブル上に並んだグラスを眺め、外観を確認してください。赤ワインは「淡い系」なのか「濃い系」なのかを判断、ここから全てが始まります。
「淡い系」と判断した場合
真っ先に思い浮かべるのはピノ・ノワールです。ガメイ、マスカット・ベーリーAもこのタイプですが、「淡い系」と判断したのであれば、基本的にピノ・ノワールのみを想定して先に進みます。(ネッビオーロも「淡い」色調です)
「濃い系」と判断した場合
ワインのエッジに紫のニュアンスを感じることが多く、その場合はカベルネ・ソーヴィニヨンまたはシラー/シラーズを想定し、この二品種に意識を集中します。
粘性について
一般的に粘性は「淡い系」より「濃い系」の方が強くなります。ただ、ブドウ品種の特徴である以上に、気候(地理的要因)に起因するため、粘性の強弱を感じて冷涼産地か温暖産地のどちらかをイメージします。
また、「淡い系」とも「濃い系」とも判断できない微妙なワインも出題されるのですが、ひとまずここは二択で進めたいところです。
【香り】~イメージをさらに膨らませる
外観と同様にセオリー通りに進める
外観で「淡い系」と判断したならピノ・ノワールの赤い果実が主体の華やかな香りを、「濃い系」ならカベルネ・ソーヴィニヨンかシラー/シラーズの黒い果実が主体の複雑な香りをそれぞれ感じることができれば、余計なことは一切考えずにそのまま先を急ぎましょう。
「私の知っているピノ・ノワールの香りと違う」、「これまでテイスティングしたシラーはこんな感じではなかった」などと思うことも多々あるのですが、ここはグッとこらえて、「淡い系」の外観から「赤い果実香」の流れであればピノ・ノワール、「濃い系」から「黒い果実香」の時は該当二品種に絞って進めた方がうまくいく確率が高いと、過去の受験者の報告からも明らかです。
香りの強弱、凝縮感を感じる
また、この段階で、赤い果実香または黒い果実香の印象がどの程度強いのか、フレッシュな果実なのか、凝縮感やジャムのようなニュアンスがあるのか、そして、この香りが外観の印象とどの程度リンクしているのか、ということまで意識し、冷涼産地なのか温暖産地なのかをイメージしてください。
最終的にブドウ品種までたどり着けばラッキーくらいの気持ちで
そして、外観から香りと順調に進んだ時は、ブドウ品種ごとの特徴的な香り、例えばカベルネ・ソーヴィニヨンのピーマン香などを探ります。私がシラーからオリーブの香りを感じるように、特徴的に感じるポイントをとらえることができれば最高です。
特に、「濃い系」の場合は果実香の強さ、凝縮感に注目し、冷涼産地(フランス)なのか、温暖産地(新世界)なのかを判断します。
冷涼産地と想定した場合、「酸味のしっかりとした三角形のシラー」または「複雑で八角形のカベルネ・ソーヴィニヨン」の違いに注目します。詳細はVol.9にてお伝えしていますので、ご覧ください。
一方で、温暖産地と判断した場合、この三角形も八角形も共に各辺が果実の凝縮感やアルコールのボリュームによって膨らんだ印象になる為、その差はわかりづらくなります。ですから、ブドウ品種は確率1/2、当たったらラッキーくらいで十分です。テイスティングコメントに大きな違いはありません。
セオリー通りにいかない時
上記のように、理想通りにテイスティングが進むとよいのですが、そう簡単にいかないものです。
「淡い系」の外観で香りからもフレッシュな赤果実を感じ取れるのですが、どうしてもピノ・ノワールとは思えず、軽さや単調さを感じてしまった時のみ、ガメイ、マスカット・ベーリーAの可能性を考えるようにしましょう。
それでも、この違和感には目を瞑り、ピノ・ノワールのみで勝負しても概ねテイスティングコメントは似通っているので、味わいの強弱さえきっちりと選択できれば全く問題ありません。何よりも「タイプ分け」が最優先です。「ガメイ、マスカット・ベーリーAを捨てる」作戦の方が悩む時間のロスがない分、合格に近づくように思います。
※日本のメルロについて
日本ワイン推しのソムリエ協会は時折、日本のメルロを出題します。難しいので、あきらめた方がよいと思っておりますが、二次試験における重要性は年々増しています。
日本のメルロは多くの場合、「淡い系」の外観、ややチャーミングな黒果実主体の香りのスタイルが多いと言えます。このワインも違和感を覚えると思いますので、そこをしっかりと感じつつ、(ブドウ品種はあきらめてもよいので)コメントはしっかり取れるように集中しましょう。ちなみに、フランス、及び世界のメルロは「濃い系」に分類されます。
違和感を覚えた時のみ「熟成系」を検討する
フレッシュな果実香がほとんど感じ取れない、どう考えても土っぽさが果実香を上回っていると、大いなる「違和感」を覚えた時にのみ初めて、③の「熟成系」を検討します。
この「熟成系」は淡い外観であればネッビオーロ、濃い外観であればサンジョヴェーゼまたはテンプラニーリョの可能性が高いです。
香りの段階で、方向性が決まると言っても過言ではありません。ですが、鼻はだんだんマヒしていきます。いまいち手ごたえを感じない時は、時間をかけずに次のテイスティングアイテムに進みましょう。
【味わい】~最終確認
味わいでポイントとなるのは「果実の凝縮感」「渋味」「酸味」「アルコールのボリューム」です。皆さんの中でこの基準がどこまで出来ているか、味わいにおける大きなポイントになります。
渋味を感じる
基本的に「濃い系」の方が、そして冷涼産地の方が渋みを強く感じます。新世界産のワインにもしっかりとした渋味があるのですが、果実の凝縮感やアルコール、樽の影響によってマスキングされるため突出して感じないということです。
ただ、「淡い」外観ですが、ネッビオーロが最も渋みの強い品種で、次にカベルネ・ソーヴィニヨン、シラーと続きます。
酸味を感じる
ネッビオーロを含む「淡い」外観の方が酸味をしっかりと感じます。また、渋み同様に新世界産は酸が穏やかになります。さらに、ガメイ、マスカット・ベーリーAは大らかな印象で酸味も穏やかです。「濃い系」ではシラー(仏)の酸味がわかりやすいと言えます。
果実の凝縮感とアルコールのボリュームを感じる
特に「濃い系」/温暖産地からは果実の凝縮感とアルコールのボリュームをしっかりと感じます。「熟成系」からも強さを感じますが、「濃い系」/温暖産地には及びません。
味わいでは、タイプ分けの最終確認を行いつつ、各要素の強弱を感じて、それらを的確にコメントとして選択することが重要です。ここが合否のポイントの一つであることは間違いありません。
まとめ
外観で「淡い系」or「濃い系」を判断し、香りでタイプ分けし、味わいで強弱を見極める。この基本的な流れを意識してテイスティングを進め、明確な違和感を覚えた時のみ「熟成系」を考慮する。そして、ブドウ品種にこだわり過ぎない。
赤ワインのテイスティングは、できる限りシンプルに考えることが成功のカギです。
「タイプ分け」までたどり着けば、ブドウ品種の特定であまりにも悩むようなら該当主要品種を当てはめるだけで十分です。何度も言いますが、ブドウ品種正解の配点はそれほど高くはなく、タイプ分けとワイン各要素の強弱さえしっかりコメントできれば、十分に合格ラインを超えます。ブドウ品種正解ゼロで合格する方がいらっしゃる現状から考えると、ブドウ品種を悩みすぎてリズムを崩し、パニックになったり時間不足に陥ったりする方が、失敗する可能性が高いと思います。
大切なことは迷わない勇気です。6~7割正解すれば合格です。完璧を目指すのではなく、着実に得点を積み重ねることが大切です。
▼料理人のためのソムリエ試験対策 他の回はコチラから。
Vol.1 概要編
Vol.2 一次試験対策前にすべきこと
Vol.3 一次試験対策の準備と春先までの勉強法
Vol.4 一次試験対策、教本と過去問を利用した勉強法
Vol.5 二次試験対策の準備
Vol.6 二次試験対策として意識すべきワインについて
Vol.7 テイスティングして書き留める
Vol.8 ワインの酸とアルコール
Vol.9 主要白ブドウ品種の特徴
Vol.10 主要黒ブドウ品種の特徴 その1
Vol.11 主要黒ブドウ品種の特徴 その2
Vol.12 ラストスパート!一次試験前二ヶ月間の一次試験対策
Vol.13 二次試験を意識したテイスティング
Vol.14 白ワインを3つのタイプに分ける
Vol.16 二次のテイスティング対策最終章~「模範テイスティングコメントを暗記する」
Vol.17【最終回】三次試験・サービス実技対策
フォローして最新情報をチェック!