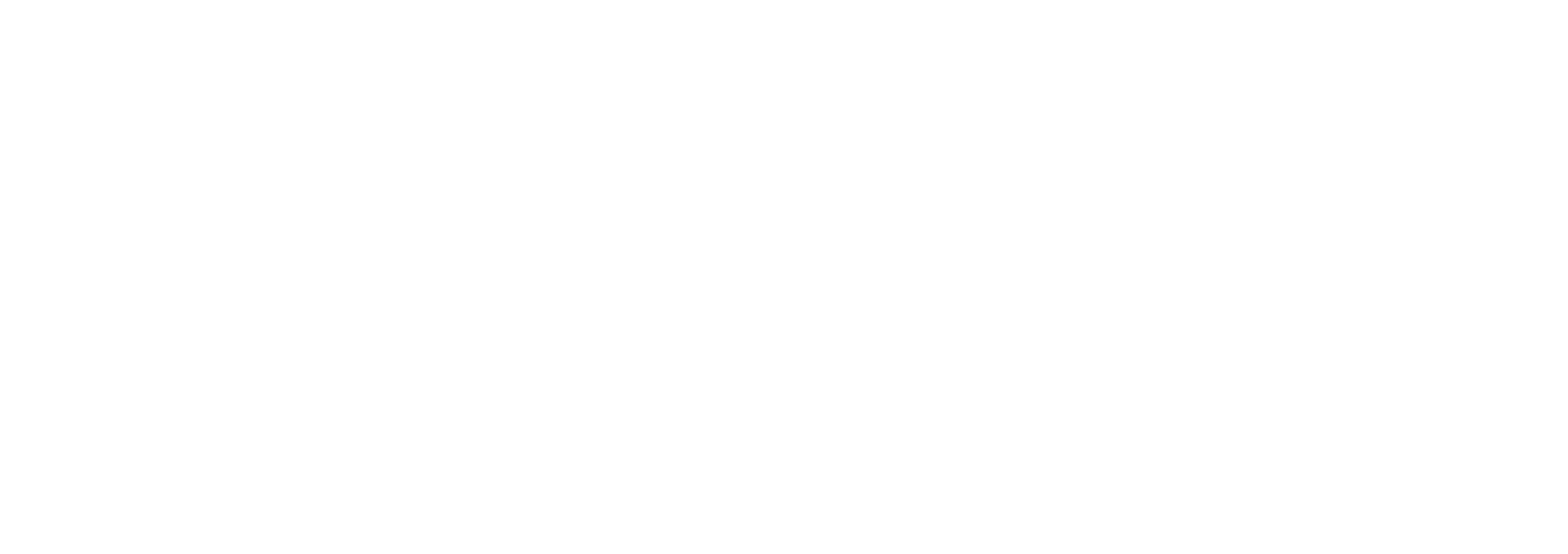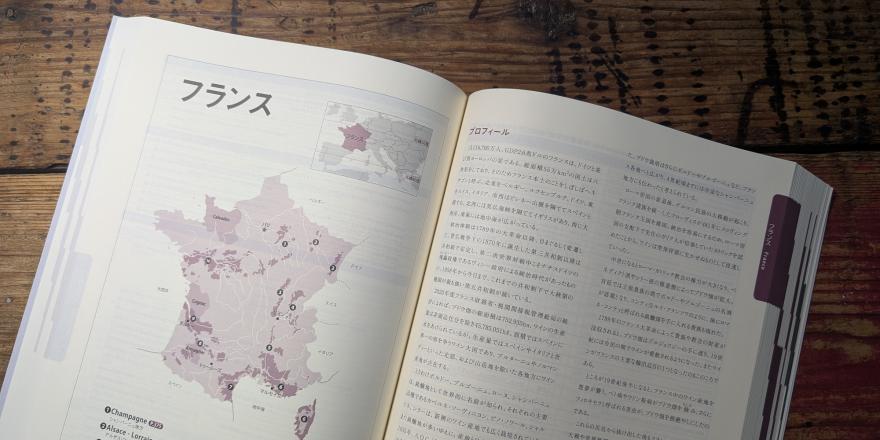料理人のためのソムリエ試験対策 Vol.16 二次のテイスティング対策最終章~「模範テイスティングコメントを暗記する」
ソムリエの松岡正浩さんから学ぶ「料理人のためのソムリエ試験対策」も、いよいよ終盤です。10月6日の二次試験に向け、対策に励んでいる方も多いかと思います。今回は、二次のテイスティング対策の最終章をお届けします。テイスティングをして感じたことを書き留めることができていた人、また、できなかった人にも、最後に取り組んでいただきたいことをお伝えします。
-

-
松岡正浩(「合同会社 まじめ2」代表 / 大阪・北新地『空心 伽藍堂』シェフソムリエ)
兵庫県出身。山形大学に進学後、県内のホテルに就職。東京『タテル ヨシノ 芝』にて本格的にフランス料理の世界に入り、その後、渡仏。『ステラ マリス』を経て、パリの日本料理店『あい田』ではシェフソムリエとして迎えられた。帰国後、和歌山『オテル・ド・ヨシノ』にて支配人兼ソムリエを務め、2016年、日本料理『柏屋』へ。こちらでも支配人兼ソムリエを務め、ワイン・日本酒を織り交ぜたペアリングコースを提案。レストランガイド「Gault&Millau(ゴ・エ・ミヨ)2021」にてベストソムリエ賞受賞。2022~23年、京都・御所東のフランス料理『Droit(ドロワ)』においてギャルソンとして勤務。23年6月より、大阪・北新地の中国料理『空心 伽藍堂』にてシェフソムリエを務める。
一次試験が終わり、ホッと一息、二次試験に向けて頑張っているところですね。
この連載を始めた頃、「テイスティングして感じたことを書き留めてください」と言い続けましたが、実行していただけましたでしょうか。確かにとても面倒で、うまく書けない時期もあったかと思います。
わからないながらもしっかりと「書くこと」を続けた方は、香りや味わいを言葉にすることに少しずつ慣れてきており、ワインを言葉に変換することを受け入れられるようになってきているはずです。いまいち実感がないかもしれませんが、今、その努力が大きく花開こうとしています。
戦略の転換、模範解答の暗記
これまではワインをご自身の言葉で表現してきましたが、これからは「過去にソムリエ協会が発表した模範テイスティングコメントを暗記し、当てはめる」という今までとは反対のことを行い、合格を目指します。
長時間働いていらっしゃるであろう料理人の方にとって、二次のテイスティングに正攻法で取り組むことは時間的に難しいと思われます。 ですから、ワインを言葉に変換することで得た感覚を元に、「模範テイスティングコメントを暗記」し、そのコメントをイメージしながらテイスティングを繰り返す。そして、二次試験本番では、「タイプ分け」した後にそれぞれ該当する暗記した模範テイスティングコメントをただただ当てはめる。これが最も効率的なアプローチであると十数年の経験から確信しております。
一方で、言葉にすることを実行しなかった方、ここまで来た以上は仕方がありません。付け焼き刃ですが、同様に「模範テイスティングコメントを暗記する」作戦で乗り切りましょう。今からご自身でワインから感じたことをテイスティングコメントにしても多くの場合、正解には程遠く、現実的ではありません。
協会発表の模範テイスティングコメント
ソムリエ協会に属する多くのソムリエ達は、ワインの外観を見て、香りを感じ取り、一口口に含んだ瞬間に、外観、香り、味わいに関して、暗記した種別のテンプレートのコメントの中からいずれかを選択し、答えるという訓練を受けています。
ソムリエコンクールの決勝等をご覧になられるとおわかりいただけるのですが、出題されたワインを瞬時に判断し答えなくてはならず、香りや味わいを一つ一つ感じてコメントしている時間的余裕は一切ありません。例えば、カベルネ・ソーヴィニヨンと想定したなら、外観はダークチェリーレッド…、香りはブラックベリー…と準備した定番のコメントを一気に述べるといった感じです。
このように訓練されたソムリエ達が二次のテイスティングの模範解答を作るので、ある程度パターンに則った、言い換えればタイプごとに似通ったテイスティングコメントになるというわけです。
「タイプ分け」して「模範テイスティングコメントを当てはめる」
ワインのテイスティングに100%正解というものはありません。人はそれぞれ感じる領域があるようで、ある人にとっては顕著に感じられることが、他の人には全く感じられないということがあると聞きます。
例えば、ワインの劣化に「ブショネ」があり、強烈な不快感をもたらすのですが、極稀に全く感じない方もいるようです。また、これだけが要因ではないと思いますが、食べ物の好き嫌いや食の好みがわかれることも、この感じ方の違いに起因するのではと私は考えております。
二次のテイスティングは、その100%の答えのないワインをマークシート方式で解答させる試験です。ワインから感じたことをそのままコメントにして評価するという純粋な官能試験ではありません。
Vol.14、Vol.15にて「ワインのタイプ分け」についてお伝えしました。このタイプ分けを二次のテイスティングにおける最重要ポイントの一つ目としました。(Vol.5参照)
過去のソムリエ協会発表の模範解答を見る限り、タイプごとの模範テイスティングコメントは多少の違いはあるものの似通っており、ブドウ品種を取り違えても、それほど大きな失点にはならないからです。
そして、最重要ポイントの二つ目は「ワインの各コメント(解答)を『用語選択用紙』から選択できるようになる」ですが(Vol.5参照)、こちらを「暗記した模範テイスティングコメントを当てはめる」に置き換えます。
つまり、二次試験においては、個人の感覚で勝負するよりも、ソムリエ協会が求める方向性に則り、大きな枠組みをしっかりととらえることの方が得点につながりやすいということです。
模範テイスティングコメントを手に入れる
模範テイスティングコメントを暗記するかどうかは別として、過去にどのようなコメントが正解とされてきたかを知ることがとても大切です。一次試験対策に過去問が有効であったように、例えば、ソムリエ協会がフランスのソーヴィニヨン・ブランに対してどのようなコメントを正解としてきたかを知ることに意味があります。経験の少ない受験者が感じたコメント以上の価値があります。(ちなみに、WSET等、ソムリエ協会以外にもワインの団体がいくつか存在しますが、考え方や表現方法が違う為、テイスティングコメントも異なります)
ソムリエ協会が発表した模範テイスティングコメントですが、インターネットを駆使するとどこかに残っていると思います。また、それらを解説したサイト、ブログ等も見つかるはずです。もしくは、ワインスクール等から情報を得ることも一つだと思います。
ここは多少お金をかけてでも模範テイスティングコメントを手に入れてください。そして、そのテイスティングコメントを分析し、そのコメントの意味を感じながらテイスティングを続けることが合格への道だと信じてみてください。
この連載を始めた頃にもお伝えしましたが、私は11年間「ちょっとまじめにソムリエ試験対策こーざ」というサイトを運営していました。そして私は終始一貫して、二次のテイスティングは「ワインのタイプ分け」と「模範テイスティングコメントを暗記する」という二本柱で、二次試験を乗り切るようにお伝えしてきました。そして、毎年多くの合格者を輩出してきたと自負しております。
受験報告を読む
「ちょっとまじめにソムリエ試験対策こーざ」には過去10年間の受験報告がアップされています。受験会場の雰囲気から試験の流れ、試験中の葛藤など、実際に受験された多くの方の生の声が赤裸々に書かれています。また、その時々においての考え方や対処法に関して、私なりの助言も行ってまいりました。この受験報告を読むだけで二次のテイスティングの流れが理解できるのではと思っているくらいです。
そして、その受験報告の中で「模範テイスティングコメントを暗記する」ことがいかに有効であったかということを、多くの方に証言していただいております。ぜひ、お読みいただき、そしてこの暗記法を信じて合格を勝ち取っていただきたいと思います。
最後に
二次のテイスティングはとにかく「シンプルに考える」ことです。素直に「タイプ分け」して、「暗記した模範テイスティングコメントをあてはめる」。悩んで時間をロスするくらいなら、ブドウ品種の正解をあきらめた方が良い結果につながります。
例えば「私の知っているピノ・ノワールはこんな感じではなかった」と思うものですが、「淡い系」で「赤い果実香」を感じたなら、「こんなピノ・ノワールもあるんだな」とセオリー通りに考えた方がうまくいくと、上記の受験報告からも読み取れます。
最後まであきらめてはいけません。あきらめたらそこで…、有名なバスケットボール漫画にもあるように、最後まであきらめなかった方が合格を手にします。あと少しです。試験の流れをイメージしつつ、暗記した模範テイスティングコメントをあてはめながらテイスティングを続けてください。
▼料理人のためのソムリエ試験対策 他の回はコチラから。
Vol.1 概要編
Vol.2 一次試験対策前にすべきこと
Vol.3 一次試験対策の準備と春先までの勉強法
Vol.4 一次試験対策、教本と過去問を利用した勉強法
Vol.5 二次試験対策の準備
Vol.6 二次試験対策として意識すべきワインについて
Vol.7 テイスティングして書き留める
Vol.8 ワインの酸とアルコール
Vol.9 主要白ブドウ品種の特徴
Vol.10 主要黒ブドウ品種の特徴 その1
Vol.11 主要黒ブドウ品種の特徴 その2
Vol.12 ラストスパート!一次試験前二ヶ月間の一次試験対策
Vol.13 二次試験を意識したテイスティング
Vol.14 白ワインを3つのタイプに分ける
Vol.15 赤ワインのタイプ分け
Vol.17【最終回】三次試験・サービス実技対策
フォローして最新情報をチェック!